なんじ【汝・爾】の語源・由来
「汝・爾」という言葉は、元々「なむち」という形で存在しました。 これは、「汝(な)」と「貴(むち)」の2つの語から成り立っています。 「汝」は、ここでの意味としては「おまえ」という言葉で、より目下や親しい相手を指す二人称...
 な行
な行「汝・爾」という言葉は、元々「なむち」という形で存在しました。 これは、「汝(な)」と「貴(むち)」の2つの語から成り立っています。 「汝」は、ここでの意味としては「おまえ」という言葉で、より目下や親しい相手を指す二人称...
 な行
な行「南京豆」とは、私たちがよく知っている落花生やピーナッツの別称です。 この名称は、豆の実を殻から取り出したものを指します。 この名前の背景には、日本への渡来の経緯が関わっています。 江戸時代の前期に、中国から日本へこの豆...
 な行
な行「成程」という言葉は、「成る」と「程」という二つの語から成り立っています。 「成る」は「実現する」という意味を持ち、「程」は程度を示す言葉です。 この組み合わせは当初「できるだけ」という意味を示していました。 しかし、時...
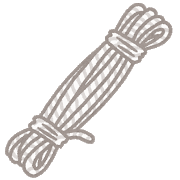 な行
な行「縄」という言葉は、植物の繊維、例えば藁や麻、棕梠の毛などを綯って作られるものを指し、このものは物を結んだり縛ったりするのに使われます。 この「縄」の名称の起源には、二つの説が考えられています。 一つ目の説は、「綯う(な...
 な行
な行「ならず者」という言葉は、その本来の意味から、今日の一般的な意味に変化してきた言葉です。 起源としては、「ならず者」はもともと「成らず者」と書かれていました。 これは動詞「成る」、つまり「なる」という言葉に、打消しを意味...
 な行
な行「奈落の底」という言葉は、深くて底が見えない場所や状況、または物事の最も悪い状態や最終の場所を指す表現として使われます。 その起源は仏教語にあります。 「奈落」は、サンスクリット語で地獄を意味する「naraka」という言...
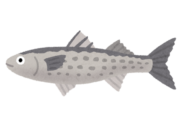 な行
な行「ナヨシ」、または「名吉・鯔」は、ボラやイナとも呼ばれる魚の異称です。 この名称の背景には縁起をかつぐ文化が関わっています。 ナヨシは出世魚の一つであり、成長の過程でその名前が変わるという特徴があります。 このような出世...
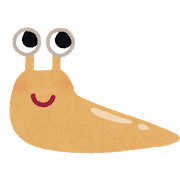 な行
な行「ナメクジ」という言葉は、陸生の巻貝の中で殻が退化した生物を指す総称です。 特に、ナメクジ科に属する一種が一般的にこの名で知られています。 この生物は体長が約6センチメートルで、淡褐色の体に3条の暗褐色の帯があります。 ...
 な行
な行「生半可」という言葉は、中途半端や不十分な状態を表すものとして使われます。 この言葉の成り立ちは、接頭語「生」に、「半可通」という言葉の略である「半可」を組み合わせたものです。 まず、「生」という接頭語は、不完全や未完成...
 な行
な行なまはげは、秋田牡鹿半島地方などで行われる正月15日の夜の伝統的な行事です。 この行事では、青年たちが大きな鬼面をかぶり、蓑を着て、木製の刃物や幣束、桶、箱などを持って家々を回ります。 各家を訪れると、彼らは酒宴の供応を...
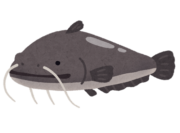 な行
な行「なまず」という名前は、その特徴的な体の質感と生息地に関連しています。 まず、ナマズの体表はなめらかで鱗が存在しないため、この特徴から「なま」という部分が名前に付けられました。 「なま」は「なめらか」を意味しています。 ...
 な行
な行「なます」という言葉は平安時代に既に使用されており、和名抄において「奈万須(なます)」や「細肉完(肉)也(なり)」という形で記述されています。 この言葉の起源は、生の肉を細かく切ることから生まれたものとされています。 具...
 な行
な行「ナマコ」という言葉の起源は、古くは単に「コ」として呼ばれていました。 時間が経つにつれて、「ナマ」という接頭辞が付けられました。 この「ナマ」には複数の説があります。 一つ目の説は、「ナマ」が「生」を意味し、ナマコが生...
 な行
な行「なまじっか」は、「生強い(なまじい)」から派生した言葉であり、具体的には「なまじ」が促音化して「なまじっか」となったものです。 この「なまじ」の意味は、何かを行うことを仮定した際、強引にそうしない方がよい、または、むし...
 な行
な行「名前」という言葉は、人や物の区別をするための呼び名を意味しています。 この中の「名」という部分は、古くから物や人を指す名称として用いられてきました。 一方、「前」という部分は敬称として使われることが多かったのです。 時...
 な行
な行「生意気」という言葉は、年齢や地位がそれほどでもないにも関わらず、知ったかぶりをしたり、出しゃばった態度をとることを指します。 この言葉の背景には、二つの主要な要素「生」と「いき」が含まれています。 「生」の部分は、未熟...
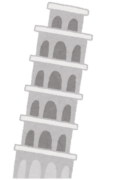 な行
な行「斜め」という言葉は、基準方向に対して垂直でも並行でもない、傾いていることを指します。 この言葉の由来は古い時代に遡ります。 古くは、漢文の訓読文で「ななめ」という読みが見られました。 一方、和文では「なのめ」という形が...
 な行
な行七草粥は、正月の7日に特定の春の七草を用いて炊いた粥であり、正月15日には、米や粟、稗、黍、小豆など、異なる7種類の食材を炊き合わせた粥を指すこともあります。 この風習は、寒さの中で緑の食材が少ない時期に、これらの草を食...
 な行
な行ナナカマド(七竈)は、バラ科に属する落葉の小高木で、山地に自生し、高さはおおよそ10メートルまで成長します。 この木は、街路樹や庭木としての植栽にも用いられることが多いです。 夏の7月には小さな白色の花が群れて咲き、秋に...
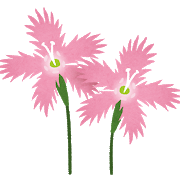 な行
な行撫子(ナデシコ)は、ナデシコ科に属する多年草で、秋の七草の一つとしても知られています。 この花は、日当たりの良い草地や川原などで自然に生えており、秋の8~9月頃に淡紅色の花を咲かせます。 花自体はとても魅力的で、5枚の花...
 な行
な行「懐かしい」という言葉は、現代の日本語で「思い出されてしたわしい」という意味でよく使われますが、その原点は少し違った意味合いを持っていました。 この言葉は、動詞「なつく(懐く)」の形容詞形から派生したものです。 元々の意...
 な行
な行「夏」という言葉は、四季の中で最も暑い時期を指す言葉として使われます。 この言葉の語源については、アルタイ諸語、特に朝鮮語の「nierym(夏)」や満州語の「niyengniyeri(春)」などと関連があるとされています...
 な行
な行「菜種梅雨」という言葉は、春の3月下旬から4月にかけて、菜の花が一番盛りとなる時期に降る雨を指します。 「菜種」は、もともと菜の花の種子を指す言葉ですが、同時に菜の花そのものの別称としても使われています。 この時期に特有...
 な行
な行「なぞなぞ」という言葉は、物事や事象を隠して、何であるかを問いかける遊戯のことを指します。 この言葉の由来は、何ぞ何ぞと問いかける行為からきており、「なぞなぞ」と言われるようになったとされています。 古くから日本にはこの...
 な行
な行茄子(ナス)は、ナス科の野菜として多くの人々に親しまれています。 この名前「ナス」の由来にはいくつかの説が存在しています。 一つの説は、茄子が夏の時期に旬を迎えることから、「夏の実」や「夏味」という言葉が元になっていると...
 な行
な行「梨の礫」という言葉は、便りを出しても相手からの返事や反応が一切ない状態を表す言葉です。 この表現の中には、日本語の遊び心や言葉の面白さが詰まっています。 「梨の礫」の「梨」は、実際の果物の「梨」とは関係なく、「無し」と...
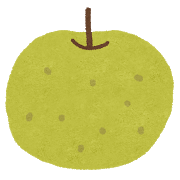 な行
な行「梨」を日本語で「なし」と呼ぶ語源や由来には、いくつかの説が存在します。 まず、一つの説としては、果実の中央部分が白いことから「中白(なかしろ)」と呼ばれていたものが、時が経つにつれて略されて「なし」となったというもので...
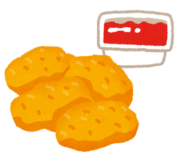 な行
な行「ナゲット」という言葉は、英語の「nugget」から来ており、元々は金塊や金属の塊を指す言葉として使われていました。 しかし、この言葉が食品の名前として使われるようになった背景には、その見た目の関連があります。 具体的に...
 な行
な行「泣きべそをかく」という言葉は、泣きそうな顔つきや、今にも泣き出しそうな様子を表す言葉です。 この言葉の背後にある「べそ」という部分の起源には、いくつかの考え方や変遷があります。 まず、「べそ」は、口をへの字に曲げる様子...
 な行
な行「長月」は、陰暦の9月を指す日本の古い異称です。 この言葉の起源については、確固たる結論がありませんが、いくつかの主要な考え方や推測が存在します。 一つの説は、9月が夜が長くなり始める月であることから、「夜長月」という名...