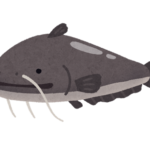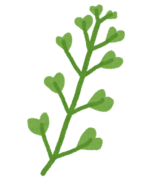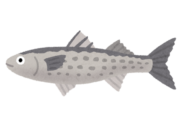「なます」という言葉は平安時代に既に使用されており、和名抄において「奈万須(なます)」や「細肉完(肉)也(なり)」という形で記述されています。
この言葉の起源は、生の肉を細かく切ることから生まれたものとされています。
具体的には、「生」に「肉(しし)」を組み合わせた「生肉」という言葉が時間の経過とともに「なます」という形に変化していったと考えられます。
また、時代とともに「なます」の材料として魚を使用することが一般的になりました。
この変化に伴い、魚の部分を示すために「魚偏」を持つ漢字「鱠」が用いられるようになりました。
さらに、野菜や果物のみを使用して作られる「なます」には、「月」を偏に持つ「膾」という漢字が使用され、これは「精進膾」とも呼ばれることがあります。
なます【膾・鱠】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「なます」の語源やその変遷をカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 歴史的記述 | 平安時代に「奈万須(なます)」や「細肉完(肉)也(なり)」として和名抄に記述。 |
| 語源の起源 | 生の肉を細かく切ることから。 |
| 言葉の変化 | 「生」に「肉(しし)」の組み合わせから「生肉」として、その後「なます」という形に変化。 |
| 魚を使用する「なます」 | 時代とともに魚を材料として使用することが一般的になり、「鱠」という漢字が使われるように。 |
| 野菜や果物を使用する「なます」 | 「月」を偏に持つ「膾」という漢字が使用され、「精進膾」とも呼ばれる。 |