えんにち【縁日】の語源・由来
「縁日」は、特定の神仏に関連する特別な日に行われる祭典や供養の日を指します。 この日に寺院や神社に参詣すると、特に大きな功徳が得られるとされています。 例えば、毎月5日は水天宮、25日は天満宮、8日は薬師、18日は観音、...
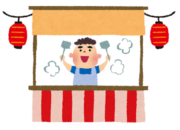 え行
え行「縁日」は、特定の神仏に関連する特別な日に行われる祭典や供養の日を指します。 この日に寺院や神社に参詣すると、特に大きな功徳が得られるとされています。 例えば、毎月5日は水天宮、25日は天満宮、8日は薬師、18日は観音、...
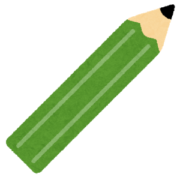 え行
え行「鉛筆」は、基本的には黒鉛と粘土を混ぜて作られた筆記具です。 名前はかつて鉛粉を用いて書く筆が中国で「鉛筆」と呼ばれていたことに由来します。 ただし、現在一般的な鉛筆は実際には鉛を含まず、黒鉛と粘土で作られています。 そ...
 え行
え行「エンスー」という言葉は、英語の「enthusiast」から派生した日本語スラングです。 「enthusiast」は、熱心な愛好者や熱狂者、ファンといった意味を持っています。 この「エンスー」という略称が日本で広まったの...
 え行
え行エンゲル係数という言葉は、ドイツの社会統計学者であるエンゲル(Engel)の名前に由来しています。 エンゲルは19世紀にベルギーの労働者の家計に関する調査を行い、その結果からこの指標を提唱しました。 彼が発見したのは、所...
 え行
え行縁側(えんがわ)という言葉は、日本の家屋における特定の場所を指す用語であり、その由来は歴史的にも変遷を遂げています。 平安時代においては、この細長い板敷きの通路は単に「縁」と呼ばれていました。 この「縁」という名称は、家...
 え行
え行演歌の語源と由来は、日本の歴史と密接に結びついています。元々、明治初期には自由民権運動が活発で、その壮士たちは政府に対して強い意見を持っていました。 しかし、当時の政府は演説に対して厳しい取り締まりを行っていたため、これ...
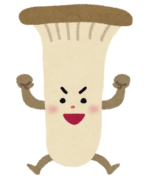 え行
え行エリンギの名前は、その学名「Pleurotus eryngii」から来ています。 この学名は、エリンギが元々セリ科の植物「エリンギウム・エリンジウム」の枯死した根に寄生していたことに由来します。 この関連性から、エリンギ...
 え行
え行「エメラルド」は、美しい緑色の宝石であり、その名前は多言語の影響を受けています。 もともとは、サンスクリット語で「緑色の石」を意味する「スマラカタ」という言葉から派生しています。 この言葉はギリシャ語に取り込まれ、「スマ...
 え行
え行「恵方巻」は、日本の節分の日に特定の方向(恵方)を向いて食べる巻きずしのことです。 その名前は、恵方という概念に由来しています。 恵方とは、もともとは正月に神が来る方角を指していましたが、暦術が取り入れられてからは、その...
 え行
え行「エプロン」という言葉は、日常生活や様々な業務で使用される前掛けを指しますが、その語源は英語の「apron」に由来しています。 この英語の単語は、かつてはラテン語の「mappa」という言葉が起源であり、これは「布ぎれ」や...
 え行
え行「エノコロヤナギ(狗尾柳)」という名前は、この柳の花穂が子犬の尾に似ているとされることから来ています。 「エノコロ」とは「犬の子」を意味し、この言葉が名前の一部となっています。 一方で、この柳は「ネコヤナギ」とも呼ばれま...
 え行
え行干支(えと)とは、日常的には主に年を表すための暦の一種ですが、その背後には「十干」と「十二支」という二つの要素が組み合わさっています。 十干は、五行(木、火、土、金、水)を元に、それぞれに陽と陰の要素を加えて名前がつけら...
 え行
え行猿公(えてこう)という言葉は、猿(えて)を擬人化した形で使用されます。 この語源は、日本語で「サル」を意味する「えて」という言葉と、人物に親しみを込めたり、卑しめるときに使われる俗語「公」が組み合わさっています。 「えて...
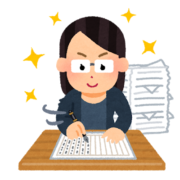 え行
え行エッセイという言葉は、主に随筆や小論を指す文学ジャンルですが、その語源は英語の「essay」とフランス語の「essayer」に遡ります。 英語の「essay」はフランス語の動詞「essayer」から来ており、このフランス...
 え行
え行「得体(えたい)」は、何かの正体や本性を指す言葉です。 この語源については複数の説が存在します。 一つ目の説は、「得体」が「為体(ていたらく)」の音読み「イタイ」から転じたものだとするものです。 為体は事の成り行きや状況...
 え行
え行エストラゴンという名前は、フランス語の「Estragon」に由来しています。 このフランス語の単語は「小さな竜」を意味しており、この植物の特徴がいくつかの面で「竜」に似ているとされています。 具体的には、エストラゴンの細...
 え行
え行「エスケープ」という言葉は、英語の「escape」から来ており、その意味は「逃亡する」または「脱出する」です。 この英語の「escape」自体は、ラテン語の「excappa」に由来しています。 このラテン語の単語は「マン...
 え行
え行「荏胡麻(エゴマ)」は、シソ科の一年草で、インドや中国が原産地です。 油料作物としても利用され、その種子から「エゴマ油」または「荏油(えのあぶら、えのゆ)」が採取されます。 この油は食用に使われるほか、防水材としても用い...
 え行
え行“依怙贔屓”(えこひいき)は、特定の人や物事を不公平に優遇するという意味で使われる日本語の四字熟語です。 この言葉は、それぞれ独立した二つの部分「依怙」と「贔屓」から構成されています。 「依怙」の...
 え行
え行エクレアは、細長い形状のシュークリームで、表面には通常チョコレートやチョコレート風味のフォンダンが塗られています。 このお菓子の名前はフランス語で「éclair」から来ており、”éclair” は...
 え行
え行エープリルフールは、毎年4月1日に行われる風習で、この日には軽い嘘をついて人を驚かせることが許されています。 この風習の起源にはいくつかの説がありますが、一つの有力な説は、16世紀フランスで起こった変化に関連しています。...
 え行
え行「エアロビクス」は、持続的に酸素を摂取しながら行う運動の一形態で、特にダンスやジョギング、水泳、サイクリングなどが含まれます。 この言葉は英語の「aerobics」から来ています。 英語の「aerobics」は「エアロビ...
 え行
え行「似非」という言葉は、何かが本物に似ているが、実際には本物ではない、すなわち「見せかけだけの」といった意味で使われます。 この言葉の語源にはいくつかの説があり、一つには「似て非なるもの」という意味から派生したとする当て字...
 え行
え行「演説」は、元々は漢籍、つまり中国の古典文献に由来する言葉で、声を用いて道理や教義を説くという意味で使われていました。 この言葉は日本でも古くから存在し、仏典や歴史文献「太平記」などにもその使用例が見られます。 一方で、...
 え行
え行演繹法の語源は、英語の「deduction」が日本語に翻訳された形です。 この翻訳において、「演繹」という用語が採用されました。 元々「演繹」は、漢籍、すなわち古典的な中国の文献に存在する言葉で、一つの事柄を基にして、そ...
 え行
え行「衛星国」という言葉は、大国の政治的影響下にある小国を指す用語です。 この表現は、英語の「a satellite state」を直訳したものです。 ここでの「衛星」は、惑星の周りを回る天体であり、その引力によって自由に動...
 え行
え行「閻魔帳」という言葉は、地獄の王である閻魔大王に関連しています。 伝説によれば、閻魔大王は死者の生前の行為や罪悪を詳細に記録する帳簿を持っており、この帳簿に基づいて死者を審判するとされています。 この神話的な背景から、閻...
 え行
え行「閻魔顔」という言葉は、地獄の王である閻魔に由来しています。 閻魔は、人の生前の行為を審判する存在とされ、その顔つきは一般に恐ろしいものとされています。 彼は憤怒の表情で描かれることが多く、その特徴的な顔つきは「閻魔顔」...
 え行
え行「恵比須顔(えびすがお)」とは、にこにこと笑顔でいることを指す表現です。 この言葉は、日本の七福神の一つである「恵比須(または恵比寿)」神に由来しています。 恵比須神は、商家や漁師の守り神として広く信仰されており、その姿...
 え行
え行縁起(えんぎ)という言葉は、もともと仏教用語であり、その根は梵語の「pratitya-samupada」という概念に由来しています。 この梵語の概念は、一切のものが種々の原因や縁によって生じる、すなわち「因果関係」に基づ...