うんしゅうみかん【温州蜜柑】の語源・由来
「温州蜜柑」は日本のミカンの代表的な種類で、多くの場合「ミカン」といえばこれを指します。 この名前にはちょっとした誤解があります。 名前の「温州」は中国浙江省の温州市に由来していますが、実はこのミカンの原産地は中国の温州...
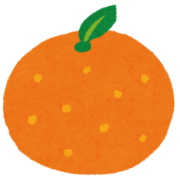 う行
う行「温州蜜柑」は日本のミカンの代表的な種類で、多くの場合「ミカン」といえばこれを指します。 この名前にはちょっとした誤解があります。 名前の「温州」は中国浙江省の温州市に由来していますが、実はこのミカンの原産地は中国の温州...
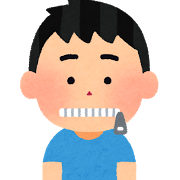 う行
う行「うんともすんとも」という表現は、声や返事がまったく出ない状態を指す日本語の俗語です。 この表現の「うん」という部分は、一般的に承諾や肯定の意を表す言葉であり、また、いきんだり苦しみの際に発する声をも意味します。 一方で...
 う行
う行「雲梯」(うんてい)という言葉は、文字通り「雲に届くほどの長いはしご」を意味します。 この言葉は中国の歴史に起源を持ち、古くは城攻めに用いられた長いはしごを指していました。 古典「墨子」によれば、この長いはしごの考案者は...
 う行
う行「うんちく」という言葉は、もともとは「蘊蓄し」という形で「物をたくわえる」という意味で用いられていました。 この言葉に含まれる「蘊」(または「薀」)と「蓄」という二つの漢字は、いずれも「たくわえる」という意味を持っていま...
 う行
う行「上前を撥ねる」という表現は、代金や賃金などの支払いを仲介した人が手数料を取る行為、または他人の利益の一部分を勝手に自分のものにする行為を指します。 この表現は、「上前」という言葉と「撥ねる」という動詞が組み合わさってい...
 う行
う行「胡乱(うろん)」という言葉は、非常に歴史的な背景を持っています。 この語の「胡」は、古代中国で西方や北方に住んでいた異民族、特に「匈奴」を指しています。 古代中国の人々は、異民族や異国のものに「胡」を冠する習慣がありま...
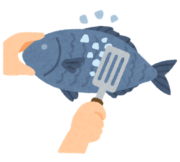 う行
う行「うろこ」(鱗)という言葉の語源は非常に興味深いものです。 この言葉は古くは「いろこ」と呼ばれており、「いろくず」とも称されていました。 この「いろこ」や「いろくず」は、魚の体表面を覆っている小さな固い薄片を指すだけでな...
 う行
う行「嬉しい」という言葉の語源は、日本語の「心(うら)」に由来しています。 この「うら」は、人の感情や心情を表す基本的な言葉であり、それに関連する他の言葉には、「うれい(憂い・愁い)」、「うらめしい(恨めしい)」、「うらやま...
 う行
う行ウルメイワシという名前は、この魚の特徴的な目に由来しています。 ウルメイワシの目は「脂瞼(しけん)」と呼ばれる透明な厚い膜で覆われており、そのために目が潤んでいるように見えます。 この「潤んでいるように見える」特性が名前...
 う行
う行「うるさい」という言葉は多様な状況で使われますが、その基本的な意味は、何かが繁重または不快な程度に存在していると感じられる状態を表します。 この言葉の語源にはいくつかの考え方がありますが、一つは「うら(心)」に「せし(狭...
 う行
う行「閏年」は特定の暦日や暦月が追加される年を指します。 この言葉の日本語での読み方「うるうどし」は、実は漢字「閏」の誤読からきています。 本来、「閏」は「じゅん」と読むのですが、日本では「潤(うるう)」と書き誤ったことから...
 う行
う行「売る」という言葉は日常生活で頻繁に使われる動詞で、主に商品やサービスを代金と引き換えに渡す行為を指します。 この言葉の語源としてはいくつかの説がありますが、一つの考え方は、「うる(得る)」または「うある(得有)」から派...
 う行
う行「羨ましい」という言葉は、人々が他者の様子や持ち物、境遇などを見て、自分もそのような状態や状況であれば良いと強く願う気持ちや、自分よりも良い境遇や資質を持つ他者を見て感じるねたみの気持ちを表現するのに用いられます。 この...
 う行
う行「占い」の語源には、「うら」という部分がキーとなっています。 この「うら」は、一般的に「心」と解釈され、表面には見えない内面や心の状態を指す言葉です。 この点から、「占い」とは表面的にはわからない心の状態や未来、運命など...
 う行
う行「裏付け」という言葉は、元々室町時代において、証文や契約などの文書に押される裏判(保証の印)を指していました。 この裏判は、文書の内容が正確であり、担保されていることを示すために用いられたものです。 このような具体的な行...
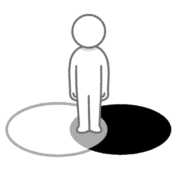 う行
う行「有耶無耶」(うやむや)という表現は、物事を明確にしない、あいまいな状態を指す言葉です。 語源については、「う」と「む」がキーポイントです。 「う」は「有る(ある)」、すなわち「存在する」という意味で、「む」は「無い」、...
 う行
う行梅(うめ)という名前は、その呉音である「メ」に基づいています。 古くは「ムメ」とも呼ばれ、中国では「ムエイ」と発音されていました。 梅は元々中国原産であり、薬用のために日本にもたらされました。 しかし、日本でのその評価は...
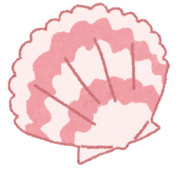 う行
う行「ウミオウギ」は、帆立貝の異称であり、この名前は貝の形が扇に似ているからとされています。 一般的には「ホタテ」と呼ばれるこの貝は、その名前の由来が「帆を立てる」という意味に関連しているとされています。 実際に、ホタテは襲...
 う行
う行「うみ」という言葉は、腫物や傷が化膿した際に出る黄白色の不透明な粘液を指します。 この言葉の語源には確固たる説がないものの、一つの考え方として「う(薄)み(見)」から来ているとする説があります。 この説によれば、「うみ」...
 う行
う行「うみ」という言葉は、日本語で海を指すための古くからの表現です。 この言葉の語源についてはいくつかの説がありますが、一般的な考え方の一つは、「う」が「大きい」という意味からきていて、「み」が「水」を意味するとされています...
 う行
う行「うまのほね」という表現は、素性や背景が不明である人物を指して使われる言葉です。 この語は、もともと中国の言い回しから来ています。 中国では、「一に鶏肋(けいろく)、二に馬骨」という表現があり、これはそれぞれ「小さすぎて...
 う行
う行「ウマノアシガタ」は、キンポウゲの別称で、この名前はその葉の形状に由来しています。 具体的には、葉を遠くから見た場合、その形が馬の足に似ているとされているためにこの名前がつけられました。 しかし、語源には別の説もあります...
 う行
う行「うまい」は非常に多義的な日本語の言葉で、その意味は味が良い、技術が優れている、得になるなど様々です。 この語の語源にはいくつかの説がありますが、一つの考え方としては、果実が熟すと甘さが増すことから、動詞「うむ(熟む)」...
 う行
う行「午・午年」は、十二支の中で第7番目に当たる言葉ですが、その語源となったのは「杵」であり、当初は「ご」と読まれていました。 この字が示すのは、草木が成長してその極限を過ぎ、衰えが見え始めるという状態です。 このような意味...
 う行
う行「馬」は、哺乳類であり、乗用、競技、農耕、運送など多くの用途で人々に利用されています。 この言葉の語源については、漢字「馬」の音読み「マ」が変化して「うま」となったとされています。 特に、平安時代以降は「むま」とも表記さ...
 う行
う行「うぶ」という言葉は、純真で世慣れていない状態や性質を表す日本語の形容詞です。 この語の起源には複数の説がありますが、一般的には「産」または「初(うい)」から派生したとされています。 「産」から派生したとする説では、この...
 う行
う行「うなだれる」は、気持ちが沈んで頭やうなじを垂れる、つまりうつむく行動や状態を指す言葉です。 この語は室町時代末期まで「うなたれる」という形で使われていました。 その語源には「うな(項)」と「たる(垂る)」が組み合わさっ...
 う行
う行「うなずく」は、首を下に動かす行為や諒解・承諾の意を示すときの頷きを指す言葉です。 この言葉の語源は、「項(うなじ)を前に突く」という意味からきているとされています。 ここでの「項」とは「うなじ」や「首すじ」、「えりくび...
 う行
う行「うなじ」は、首の後ろ部分を指す言葉です。 この言葉の語源は完全には明らかでないものの、いくつかの仮説が存在します。 例えば、「うな」という部分は「首」または「首の後ろ」を意味するとされ、複合語を作る際に「うなずく」や「...
 う行
う行「うどん」は日本で広く親しまれている麺類の一つですが、その語源にはいくつかの説があります。 一つの説では、この麺が奈良時代に中国から渡来したとされる「混沌(こんとん)」という唐菓子に由来していると言われています。 混沌は...