さんりんぼう【三隣亡】の語源・由来
「三隣亡」という言葉は、現代では建築をすると火災を起こして、近隣の3軒までをも亡ぼすとされる忌日を意味します。 しかしこの言葉の背景を振り返ると、その由来は意外な事実が隠されています。 もともと、この言葉は「三輪宝」とし...
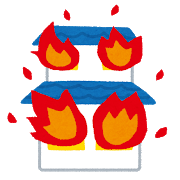 さ行
さ行「三隣亡」という言葉は、現代では建築をすると火災を起こして、近隣の3軒までをも亡ぼすとされる忌日を意味します。 しかしこの言葉の背景を振り返ると、その由来は意外な事実が隠されています。 もともと、この言葉は「三輪宝」とし...
 さ行
さ行「三拍子揃う」という表現は、3種の楽器、すなわち小鼓、太鼓、大鼓における拍子が一致し、調和の取れた演奏ができることを基にしています。 三つの楽器が同時に演奏されることで、その音楽は最も豊かで調和がとれると考えられていまし...
 さ行
さ行三度笠(さんどがさ)は、菅笠の一種で、特に顔面を覆うように深く造られたものを指します。 この特徴的な笠は、貞享の時代(1684年から1688年)頃から使用されるようになりました。 その名前「三度笠」は、江戸時代の特定の飛...
 さ行
さ行サンダルは、足のつま先やかかとを露出させながら、甲部分を紐やバンドで固定する履物の一種を指します。 この名称「サンダル」は、古代ギリシャの言葉で「板」を意味する「sandalion」と、それがラテン語化された「sanda...
 さ行
さ行サンタクロースは、私たちがよく知るクリスマスの前夜に贈り物を配る赤い服と白いひげの親しみやすい老人の姿として世界中で愛されています。 このキャラクターの起源は、アメリカに移住したオランダ人によって持ち込まれた伝説に関連し...
 さ行
さ行「山椒」という名前の由来は、その芳しい香りと独特の辛味に関連しています。 植物の名前の一部としての「椒」には、「芳しい」や「辛味」の意味が込められています。 そのため、山に自生するこの植物が持つ芳しい辛味の実を指して「山...
 さ行
さ行「傘寿」という言葉の起源は、傘の略字「仐」に関連しています。 「仐」という字が「八十」と読めるため、この特徴を基に「80歳」を指す言葉として「傘寿」が使用されるようになりました。 また、80歳のお祝いに関しては、他の節目...
 さ行
さ行「三香子」はフトモモ科の落葉高木から得られる香辛料で、西インド諸島が原産地とされています。 この香辛料の特徴は、クローブ(丁子)、シナモン(肉桂)、ナツメグという三つの主要な香辛料の香気を一つに併せ持つ点にあります。 こ...
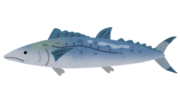 さ行
さ行「サワラ」はサバ科の海産魚で、体型がまぐろを細長くしたような形をしています。 この特徴的な体形から、名前の由来として「狭い腹」を意味する「狭腹」という言葉が関連していると考えられます。 具体的には、その細長い体型が「狭い...
 さ行
さ行「サルビア」はシソ科の植物の一つで、特に観賞用として知られる品種はブラジル原産で、夏から秋にかけて鮮やかな色の唇形花を咲かせます。 この名前「サルビア」は、英語の「salvia」から来ています。 そして、この「salvi...
 さ行
さ行「サルナシ」は、マタタビ科に属する蔓性の落葉低木で、山地に自生して他の樹木に絡みつく性質を持っています。 この植物の名前「サルナシ」は、その実に関する猿の行動から名付けられたとされる2つの説があります。 一つ目の説は、こ...
 さ行
さ行「申」や「申年」という言葉は、十二支のうち第9番目を指し、これは動物の猿を象徴としています。 方角としては、西から南に向かって30度の位置を指します。 また、古い日本の時刻の名称としては、現代の午後4時頃を意味し、一般的...
 さ行
さ行「サル」という言葉の起源は、さまざまな説が存在しますが、一つの注目すべき点は、江戸時代後期の国語辞典「和訓栞」に記載されているとおり、獣の中でも知恵が特に優れているという意味合いを持つことから、「知恵が勝る(まさる)」と...
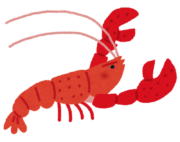 さ行
さ行「ザリガニ」は、その名前の由来に特徴的な歩行や移動の性質が関わっています。 ザリガニは後方へと退く動きをする性質があり、この特徴から「しさり蟹」と呼ばれていました。 「しさり」とは、後ろに退くという意味の動詞「しさる」か...
 さ行
さ行「サラリーマン」という言葉は、日本特有の用語として知られています。 この言葉は英語の「salaried man」が起源とされ、給与を受け取る労働者、特にホワイトカラーの労働者を指します。 しかし、実際の英語圏では「sal...
 さ行
さ行「サラダ」という言葉は、私たちが普段食べる色とりどりの野菜を主材料とした料理を指します。 この言葉の由来は、英語の「salad」やフランス語の「salade」といった言葉から来ています。 さらに、この「salad」や「s...
 さ行
さ行「さもしい」という言葉は、その起源を漢語の「沙門(さもん)」に持ちます。 「沙門」は、サンスクリット語で「努力する人」を意味する「sramana」から来ており、こちらの言葉は僧侶や桑門、出家を意味します。 この「沙門」は...
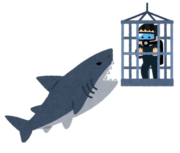 さ行
さ行鮫(サメ)は、その特徴的な外見と生態からさまざまな名前で呼ばれてきました。 その名前「サメ」には興味深い背景があります。 鮫の名前の語源は、その体に対して小さい目を持つことから来ているとされています。 具体的には、「狭目...
 さ行
さ行「侍」という言葉の起源は、貴族などのそばに仕えるという動詞「さぶらう」から来ています。 この「さぶらう」の名詞形である「さぶらひ」が、時代を経て「さむらひ」と音変化しました。 鎌倉時代以降、武士階級の権力が増していく中で...
 さ行
さ行「サミット」という言葉は、英語の「summit」から来ており、頂上や首脳級を意味します。 この英語の「summit」は、最高を意味するラテン語「summus」が起源です。 もともと「summit」には「会談」という意味は...
 さ行
さ行「さみだれ」は、陰暦5月頃に降る途切れがちの長雨を指し、また、その時期自体も指します。 この言葉は、途切れることを表す言葉としても使われます。 名前の由来は、「さ」が「さつき(五月)」の「さ」と同じ意味で、「みだれ」は水...
 さ行
さ行「ザボン」は、アジア南部原産のミカン科の常緑高木で、その果実は15cm余りの扁球形をしており、厚い果皮の中に黄色いやや苦みを持つ果肉が入っています。 特に果肉が紅紫色のものは「うちむらさき」と呼ばれます。 この名前の由来...
 さ行
さ行サポウィルスは急性胃腸炎を引き起こすウイルスの一つで、感染経路としては手指や食品を介した経口感染が主とされています。 このウイルスに関して、その名前の由来は興味深いものがあります。 1968年、アメリカのオハイオ州ノーウ...
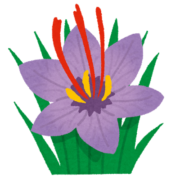 さ行
さ行サフランはアヤメ科の多年草で、その赤色の花柱が古くから香辛料、薬、染料として利用されてきました。 名前の「サフラン」は、オランダ語の「safftaan」に由来し、さらにその根源は、黄色を意味するアラビア語「az-za&#...
 さ行
さ行サファイアという言葉は、青色の美しい宝石を指す言葉として広く知られています。 この名前の起源は、ラテン語の「sapphirus」とギリシア語の「sappheiros」にあり、両方とも青色を意味しています。 サファイアは、...
 さ行
さ行「寂しい・淋しい」という言葉は、物足りなさや欠如、孤独などの感情を表現するときに用いられます。 この言葉の起源は、奈良時代にさかのぼります。 奈良時代には、この言葉は「さぶし」という形で使用されていました。 この「さぶし...
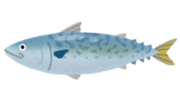 さ行
さ行「サバ」という名前は、その魚の特徴や行動から名づけられたと考えられています。 まず、サバの歯が非常に小さいことから、「小(サ)歯(バ)」や「狭(サ)歯(バ)」といった意味合いで名付けられたという説があります。 また、「狭...
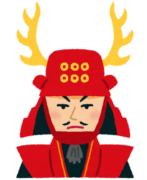 さ行
さ行「真田紐」という言葉は、天正の時代に信州上田の城主であった真田昌幸が、自らの刀の柄にこの紐を巻いたことから生まれたと言われています。 真田昌幸の使用によって紐の名声が高まり、人々はそれを「真田打」と称するようになりました...
 さ行
さ行「さといも」は、熱帯アジアが原産地で、温帯・熱帯地域で広く栽培される一年生の作物です。 この芋は、日本に縄文時代頃に渡来したと考えられ、以来長い間栽培されてきました。 名前の「さといも」は、山で自生していた「やまいも」に...
 さ行
さ行「サツマイモ」は、ヒルガオ科に属する一年生の作物で、中南米が原産地です。 この作物が日本へ伝わったのは、17世紀初頭です。 具体的には、中国と琉球を経由して九州の薩摩地方にやってきました。 この薩摩地方を通った経緯から、...