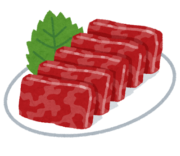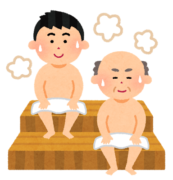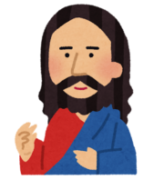「侍」という言葉の起源は、貴族などのそばに仕えるという動詞「さぶらう」から来ています。
この「さぶらう」の名詞形である「さぶらひ」が、時代を経て「さむらひ」と音変化しました。
鎌倉時代以降、武士階級の権力が増していく中で、この言葉は武士を指すようになりました。
特に室町時代には「さむらひ」の形が一般的となりました。
江戸時代には、社会階級の中で特権的な立場にあった「士」、つまり士農工商の士身分を指す言葉として「侍」が使われました。
このように、元々は主君のそばに仕える人を指していた言葉が、時代を経ることで武士や偉大な人物を指す言葉として進化してきました。
さむらい【侍】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「侍」という言葉の起源やその意味の変遷、時代背景などの重要なポイントをカンタンにまとめます。
| キーポイント | 詳細 |
|---|---|
| 語源 | 動詞「さぶらう」から来ている。 |
| 音の変化 | 「さぶらう」の名詞形「さぶらひ」が「さむらひ」と音変化した。 |
| 用途の変化 | 鎌倉時代から武士を指すように、室町時代には一般的な表現として「さむらひ」が用いられた。江戸時代には士身分を指す言葉として使われた。 |
| 元の意味 | 元々は主君のそばに仕える人を指す。 |
| 時代との関連性 | 武士階級の権力や社会階級の変遷とともに、その意味や使われ方も変化してきた。 |