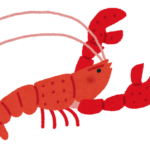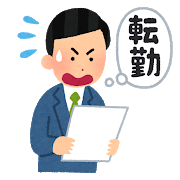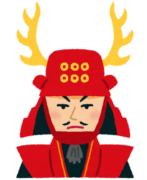「サル」という言葉の起源は、さまざまな説が存在しますが、一つの注目すべき点は、江戸時代後期の国語辞典「和訓栞」に記載されているとおり、獣の中でも知恵が特に優れているという意味合いを持つことから、「知恵が勝る(まさる)」という意味を持つ「サル」という名前がつけられたとされる説があります。
これはサルが他の獣に比べて賢いという観察から来ていると考えられます。
さらに、アイヌ語において「サロ」や「サルウシ」という言葉が存在し、これらが「サル」という言葉の語源であるとする考え方もあります。
「サルウシ」はしっぽを持つものを指す言葉であり、これが「サル」に関連しているとの説が存在します。
また、古くからサルは神聖視されていて、特に午の守護神としての役割も担っていました。
この背景から、「マル(馬留)」という言葉が「サル」に変化したという説もあります。
以上のように、「サル」の名前の由来に関しては複数の説が存在し、その正確な起源は一つに絞りきれないものとなっています。
サル【猿】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「サル」の名前の由来に関する複数の説をカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 「知恵が勝る」説 | 「和訓栞」に記載されている。サルは知恵が他の獣に比べて優れているため、「知恵が勝る(まさる)」という意味から名前がつけられたとの説。 |
| アイヌ語語源説 | アイヌ語の「サロ」や「サルウシ」という言葉が存在し、「サルウシ」はしっぽを持つものを指す。これが「サル」の語源であるとする説。 |
| 「マル(馬留)」変化説 | サルは古くから神聖視され、午の守護神としての役割も担っていた。この背景から、「マル(馬留)」という言葉が「サル」に変化したという説。 |