キンモクセイ【金木犀】の語源・由来
「キンモクセイ」は、中国原産の常緑小高木で、特に秋に橙黄色の芳香の強い小花を多数開きます。 この植物の名前「キンモクセイ」は、その親戚である「ギンモクセイ」と対比されます。 ギンモクセイは白い花をつけるのに対して、キンモ...
 き行
き行「キンモクセイ」は、中国原産の常緑小高木で、特に秋に橙黄色の芳香の強い小花を多数開きます。 この植物の名前「キンモクセイ」は、その親戚である「ギンモクセイ」と対比されます。 ギンモクセイは白い花をつけるのに対して、キンモ...
 き行
き行「銀幕」という言葉は、元々は英語の「silver screen」を日本語に訳したものです。 この「silver screen」は、過去に映画館で用いられた映写幕がアルミや他の銀色の金属膜で覆われていたことに由来します。 ...
 き行
き行「キンボール」という名前は、英語の「kin-ball」から来ており、特に「キン」の部分は英語の「キネスシス(kinesthesis)」から派生しています。 「キネスシス」という言葉は、「運動感性」を意味する用語で、人々が...
 き行
き行「キンポウゲ」という名前は、その漢名「金鳳花」から来ています。 この名前は、花の特徴的な黄色を「金色」とし、豪華で美しい八重咲きの形状を神秘的な鳥「鳳凰(ほうおう)」に例えています。 つまり、その黄金色に輝く花がまるで「...
 き行
き行「金平(きんぴら)」という名前は、複数の意味と用途を持っていますが、料理としての「きんぴら」は、ゴボウを主成分とした日本の伝統的な料理です。 この料理名の由来は、江戸時代にさかのぼります。 当時、ゴボウは体に良く、特に「...
 き行
き行「巾着」(きんちゃく)という言葉は、元々は「巾」が布切れを意味し、「身につける布切れ」つまり袋が「巾着」と称されました。 この語源には、布で作られた小さな袋が縁の部分にひもがついており、そのひもで口を締めて物を収納する、...
 き行
き行「金盞花」(キンセンカ)という名前は、この花の特徴的な色と形状に由来しています。 具体的には、花の色が黄金色(きん)に近く、その形状が日本の伝統的な酒器である「盞(さかずき)」に似ていることから、この名前がつけられました...
 き行
き行「銀シャリ」または「銀舎利」という言葉は、日本で一般的に白いご飯を指す言葉ですが、その語源や由来は少々複雑で興味深いものがあります。 まず、「シャリ」という部分は白米の飯を意味します。 この言葉は、日本の食糧不足が厳しか...
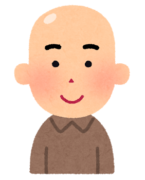 き行
き行「金柑頭」という表現は、人の頭が頭髪が少なく、金柑(きんかん)という丸くて黄色い柑橘類に似ている様子を指しています。 この比喩は、金柑の黄色くつやのある皮が光っているように、頭髪が少ない頭も皮膚が光って見えることから来て...
 き行
き行「キリン」あるいは「麒麟」には二つの主な意味があります。 一つは中国の伝説や神話に登場する想像上の動物で、もう一つは実在する長頸の草食性動物です。 伝説の麒麟は、中国で聖人が出現する前に姿を現すとされています。 この動物...
 き行
き行「切妻」は建築において特定の種類の屋根やその端部を指す言葉です。 この名前の「妻」は、実際には「つま(端)」に由来しており、端を意味します。 したがって、名前に含まれる「切」は、その端部が切り落とされたような形状の屋根を...
 き行
き行「キリシタン」という言葉は、1549年にイエズス会士フランシスコ・ザビエルらによって日本にカトリック教が伝えられた時に生まれた用語です。 この言葉の語源は、ポルトガル語でキリスト教を意味する「christao」に由来しま...
 き行
き行「義理」という言葉は、複数の意味を持つ多面的な概念ですが、その根底には「物事の正しい筋道」または「道理」という基本的な意味があります。 この基本的な意味が進化し、時間とともに「わけ」や「意味」を表すようにもなりました。 ...
 き行
き行「漁夫の利」という言葉は、双方が争っている隙に第三者が利益を得る状況を指します。 この表現の語源は、中国の古典「戦国策」に由来しています。 故事によれば、シギとハマグリが争っているところに通りかかった漁師が、その機会を利...
 き行
き行「夾竹桃(きょうちくとう)」という名称は、その植物の特性を色々な角度から表しています。 この名称は中国名「夾竹桃」の音読みとして日本に採用されました。 この名前にはいくつかの要素が組み合わさっています。 まず、「竹」に関...
 き行
き行「行水(ぎょうずい)」という言葉は、もともと仏教用語から来ています。 パーリ語で「鉢から手を離して」を意味する言葉が、日本語で「食訖りて行水す」と訳されました。 この表現では「行水」は主に「食事の後に手を洗う」行為を指し...
 き行
き行「狂言(きょうげん)」という言葉は、もともと仏教用語の「狂言綺語」から派生しています。 この「狂言綺語」は「道理に合わない言葉」を意味しました。 時代が進むと「狂言」は「ざれごと」や「うそのことを仕組んで人をだます行為」...
 き行
き行「行儀(ぎょうぎ)」という言葉は、元々は仏教語であり、修行や実践に関する規則、または仏教の儀式を指す用語でした。 この「行」は、サンスクリット語で歩み行くことを意味する「gamana」が漢訳されたものであり、仏教における...
 き行
き行「今日(きょう)」という言葉は、もともと旧仮名遣いで「けふ」と表記されていました。 この「けふ」は、時間が経つにつれて「きょう」という発音に変わりました。 この変化の背景には、「けふ」の二つの要素、「け」と「ふ」がそれぞ...
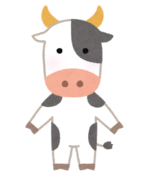 き行
き行「牛耳る」という表現は、首領となって何らかの組織や集団を操縦する、つまり支配する意味で使われます。 この言葉は、もともと「牛耳」が動詞化された形で、その「牛耳」自体が古代中国の春秋戦国時代の習慣に由来しています。 この習...
 き行
き行「キャンドル」という言葉は、英語の「candle」から来ていますが、その更なる語源はラテン語の「candere」とされています。 「candere」は「光り輝く」という意味を持ちます。 このラテン語の「cand」は「輝く...
 き行
き行「キャンディー」という言葉は英語の「candy」から来ていますが、その語源にはいくつかの異なる説があります。 一つの説としては、アラビア語の「qand」から来ているとされています。 この「qand」は砂糖を意味し、アラビ...
 き行
き行「ギャング」という言葉は、元々英語の「gang」という言葉から来ています。 この英語の「gang」は、もともと「一味」や「組」といった意味で、特に犯罪組織を指すわけではありませんでした。 しかし、アメリカの禁酒法時代(1...
 き行
き行「キャロット」という言葉は、英語でニンジンを指す「carrot」という言葉から来ています。 その他のヨーロッパ言語でも似た名称が存在し、フランス語では「calotte」、ドイツ語では「Karotte」、イタリア語では「c...
 き行
き行「キャラクター」という言葉は、多くの文脈で用いられますが、その根源は英語の「character」であり、さらに遡るとギリシア語の「kharakter」に由来します。 ギリシア語で「kharakter」は「刻み込まれたもの...
 き行
き行「キャラウェイ」とは、ヨーロッパ東部から西アジアに自生するセリ科の植物であり、特にその種子が香辛料や薬用として用いられます。 この名前は英語の「caraway」から来ていますが、その更なる起源はアラビア語の「karāwi...
 き行
き行「キャベツ」の名前は、英語の「cabbage」から来ています。 この英語の単語自体は、ラテン語の「caput」に由来しており、もともと「頭」を意味していました。 このラテン語の「caput」がフランス語になると「cabo...
 き行
き行「ギャフン」という言葉は、感動詞「ぎゃ」(驚きや衝撃を表す)と「ふん」(承諾や受け入れを示す)を組み合わせた形です。 この組み合わせが、負けて抗弁ができない、あるいは言い返せない状態を非常にうまく表しています。 明治時代...
 き行
き行「キャビア」の名前は、トルコ語の「khaviar」に起源を持ちます。 このトルコ語は魚卵、特に筋子や腹子を意味します。 この言葉はイタリア語に取り入れられ「caviaro」や「caviale」となりました。 さらにスペイ...
 き行
き行「キャタピラー」という名前は、もともとはアメリカ最大の土木機器メーカー「キャタピラー」社の社名であり、その商標名でもあります。 この名称は、英語で「毛虫」を意味する「caterpillar」から来ています。 なぜこの名前...