「しんどい」の語源・由来
「しんどい」という言葉は、関西地方を中心とした方言で、「疲れた」や「くたびれた」という意味を持ちます。 また、まどろっこしいやじれったいという意味で使われることもあります。 この言葉の語源については、「辛労」すなわち辛い...
 し行
し行「しんどい」という言葉は、関西地方を中心とした方言で、「疲れた」や「くたびれた」という意味を持ちます。 また、まどろっこしいやじれったいという意味で使われることもあります。 この言葉の語源については、「辛労」すなわち辛い...
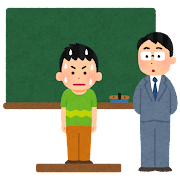 し行
し行「しゃちほこばる」という言葉は、体が緊張して固まる様子を表す表現です。 この言葉の語源や由来は、日本のお城の天守閣に飾られている「しゃちほこ」という装飾から来ています。 しゃちほこの形状が硬直していてこわばった形に見える...
 し行
し行「甚六」という言葉は、ぼんやりと育った長男やお人よし、おろかな人を指す表現として使われます。 この言葉の起源は、「順禄(じゅんろく)」という言葉が変化したものとされています。 元々「順禄」は、家族の世襲制度の中で、家の禄...
 し行
し行「蕁麻疹」という言葉は、突然の皮膚の痒みや腫れ、発疹を伴う急性皮膚炎を指します。 この名前の由来は、植物「イラクサ」の中国名である「蕁麻(じんま)」からきています。 イラクサは、その特有のトゲに触れると皮膚に痒みや腫れを...
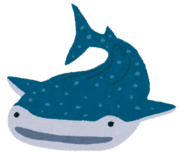 し行
し行「ジンベエザメ」という名前の由来は、この魚の体の模様が、日本の伝統的な衣類「甚兵衛」の模様に似ているためです。 具体的には、ジンベエザメの体には灰黒色の地に白い斑点が散らばっており、これが甚兵衛(またはその別称である甚平...
 し行
し行「甚平」という言葉は、もともと「甚兵衛」として書かれていました。 この「甚兵衛」は「甚兵衛羽織」から来ています。 この「甚兵衛羽織」とは、下級武士や庶民が着用していた、袖のない、膝を覆う程度の長さの綿入れ羽織を指します。...
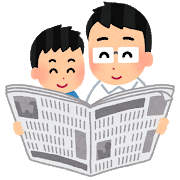 し行
し行「新聞」という言葉は、英語の「newspaper」の訳語として生まれました。 この「新聞」という言葉は、新しい知らせやニュースを意味するものとして使われていました。 実は、古代中国の唐の時代には、地方の出来事を記録した「...
 し行
し行「心配」は、心に何かをかけて思い悩むことや、気配りや配慮をすることを意味します。 この言葉の由来は、江戸時代に使われていた「心配り」を基にしています。 そして、「心配り」の音読みとして「心配」という和製漢語が生まれました...
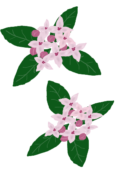 し行
し行沈丁花は、ジンチョウゲ科の常緑低木で、原産地は中国です。 この植物は、小さな花を春分の頃に多数、球状に密集して咲かせます。 特徴的なのはその強い香りで、この香りは沈香や丁字(クローブ)に似ていることから、「ジンチョウゲ」...
 し行
し行「進退谷まる」という言葉は、前に進むことや後ろに退くことができず、困難な状況に陥ることを意味します。 この言葉の由来は、古典文学である「詩経」の中の「大雅・桑柔」に出てくる「進退これ谷まる」という言葉に関連しています。 ...
 し行
し行「親切」という言葉には二つの意味があります。 一つ目は「深切」と書き、深く切なることや痛切なことを指します。 二つ目は、人情が厚く、親しく思いやりがあり配慮が行き届いている様子を指すものです。 この言葉の成り立ちを見ると...
 し行
し行「シンセサイザー」という言葉は、電子音合成装置を指すもので、楽器としての役割を持ちながらも、電子回路を組み合わせて音を制御・合成する機能を有しています。 この装置の起源は1950年代にさかのぼりますが、1960年代にその...
 し行
し行「神髄」や「真髄」という言葉は、ある物事や技術の核心や本質、その最も深いところにある奥義や要点を指す言葉として使用されます。 この言葉の由来は「精神」と「骨髄」の組み合わせからきています。 「精神」は、物質や肉体とは対立...
 し行
し行「人種の坩堝」という言葉は、アメリカ合衆国の多様な人種や民族の混在とその融合を表現するための概念です。 アメリカ合衆国には、ネイティブアメリカン、ヨーロッパ系、アフリカ系、アジア系など、様々な人種や民族が集まっており、こ...
 し行
し行「ジンジャー」という言葉は、主に生姜を指し、またショウガ科の多年草も指すことがあります。 この名前の由来は英語の「ginger」から来ており、さらにその背後にはさらなる起源が存在します。 具体的には、「ginger」は古...
 し行
し行「ジンクス」という言葉は、縁起が悪い物や事柄を指す言葉として使われます。 この言葉の起源は英語の「jinx」にあります。 その「jinx」自体が、キツツキの一種を指すギリシア語「Iynx」から派生したと考えられていますが...
 し行
し行「蜃気楼」とは、気温の局部的な変動によって光の屈折が起きる現象で、その結果、遠くの物体が近くに見えたり、地上の物体が空中に浮かんで見えたりする光学的現象を指します。 砂漠や海上など、気温の差が生じやすい場所でよく観察され...
 し行
し行「ジンギスカン」は、羊肉の薄切りを特有の兜型の鉄鍋で焼き、食する日本の料理です。 この名前は、モンゴル帝国の皇帝、チンギス・カンに由来していると一般的には考えられています。 伝説によれば、チンギス・カンが遠征中にこのよう...
 し行
し行「仁義」という言葉は、多様な意味を持つものの、その語源は儒教の理念に端を発しています。 「仁」と「義」は、儒教の核心的な価値として重視されており、「仁」は愛情や慈しみの心を、「義」は正しさや道理にかなった行いをそれぞれ指...
 し行
し行「人間万事塞翁が馬」という言葉は、人生の幸や不幸は予測できないという意味を持ちます。 この言葉の背景には、中国の古典「淮南子・人間訓」に記されている故事があります。 昔、中国の北部の塞(要塞)の近くに、占いが得意な老人、...
 し行
し行「人間」という言葉の背景は、実は仏教の言葉から来ています。 サンスクリット語、古代インドの言語に「mamusya」という語があり、これが仏教を通じて中国に伝わり、そこで「人間」として漢訳されました。 初めてこの言葉が使わ...
 し行
し行「辰」は十二支の中で第5位を示す言葉で、この言葉は「たつ」とも読みます。 この漢字の原型は「蜃」という字で、これは伝説上の生物を指し、具体的には竜の一種として考えられていました。 一方で、「漢書」の律暦の中では、「辰」は...
 し行
し行「申」は、十二支の中で第9位を占める言葉であり、猿を指します。 この漢字自体の形は、稲光が走る様子を象徴しており、この意味から「電」や「神」の原字となったと言われています。 さらに、この字は草木が直立して伸び、果実が成熟...
 し行
し行「師走」という言葉は、陰暦や太陽暦の12月を指す異称です。 この言葉の由来には、いくつかの説があります。 まず、一つ目の説は、12月に入ると、多くの家庭が僧侶を迎えて読経や仏事を執り行うため、「師走」と名付けられたという...
 し行
し行「しわ」は、物の表面に現れる細かい筋目や縮みを指します。 この言葉の語源は、「しわむ」という言葉に関連していると考えられます。 「しわむ」は、しわが寄る、もしくはしなびるという意味を持っています。 さらに、「しわ」の語源...
 し行
し行「四六時中」という言葉は、日常的に「二十四時間中」という意味で、つまり「一日中」として用いられます。 この言葉の背景には、昔の時刻の呼び方が関連しています。 江戸時代には、一日の時間を干支の十二刻で表現していました。 こ...
 し行
し行「素人」という言葉は、元々平安時代に「白人(しろひと)」と呼ばれていました。 この「白人」は、特定の芸や技術がない、つまり芸のない芸人を指していました。 その後、時代が進むにつれてこの言葉は「しらうと」と変化し、さらに江...
 し行
し行「白」という言葉は、形容詞「白し(しろし)」の語幹から来ています。 もともと「白い」という言葉は、光の顕著さや明るさを表すものでした。 実際に、古典文学の中にも「春はあけぼの やうやうしろくなり行く」という表現が見られ、...
 し行
し行「ジレンマ」という言葉は、英語の「dilemma」を由来としています。 この英語の言葉はさらに、ギリシャ語の要素から成り立っています。 「di」という部分は「2つの」という意味を持ち、「lemma」は「仮説」や「提案」と...
 し行
し行シリヤケイカという名前の由来は、このイカの特徴的な体の部分と、その挙動から来ています。 コウイカ科の一種であるシリヤケイカは、背面が灰褐色で白い斑点が点在しています。 とくに注目すべき特徴として、このイカの胴の腹面後端、...