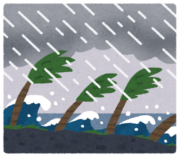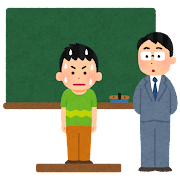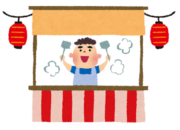「仁義」という言葉は、多様な意味を持つものの、その語源は儒教の理念に端を発しています。
「仁」と「義」は、儒教の核心的な価値として重視されており、「仁」は愛情や慈しみの心を、「義」は正しさや道理にかなった行いをそれぞれ指します。
この2つの言葉が組み合わさった「仁義」は、人々が持つべき優れた心と行動、つまり愛情深く、道理にかなった方法を指すようになりました。
ところが、時代とともに「仁義」の用いられる文脈は多様化しました。
特に、江戸時代になると、博徒や職人、香具師の間で「仁義」という言葉は親分と子分の間の道徳や初対面の挨拶を指すようになりました。
こうした背景の中で、「仁義」という言葉がやくざや博徒の文化で頻繁に使われるようになったのは、あいさつを意味する「辞儀」が時とともに「じんぎ」という読みに変わり、それが「仁義」と混同されるようになったためと言われています。
この点で、博徒ややくざの間での「仁義」という言葉の使用は、本来の儒教の理念とは直接関係がないものとなっています。
じんぎ【仁義】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「仁義」の言葉の意味の起源から変遷に至るまでの主要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 詳細・変遷 |
|---|---|
| 基本の意味 |
|
| 起源 | 儒教の理念 |
| 初期の使用 | 優れた心と道理にかなった行動を指す |
| 江戸時代の文脈 | 博徒や職人間での親分子分の道徳、挨拶 |
| 「仁義」の多様化 | やくざや博徒の文化での頻繁な使用 |
| 語源の変遷・混同 | 「辞儀」が「じんぎ」へと変わり、「仁義」と混同 |
| 儒教理念との関係 | 現代の用法は本来の儒教の理念と直接関係なし |