かんれき【還暦】の語源・由来
「還暦(かんれき)」は、数え年で61歳を指す日本の言葉です。 この言葉の語源は、60年周期で再び生まれた年の干支に戻る、つまり「還る」ことからきています。 この「暦」は干支の意味であり、干支自体は十干と十二支という二つの...
 か行
か行「還暦(かんれき)」は、数え年で61歳を指す日本の言葉です。 この言葉の語源は、60年周期で再び生まれた年の干支に戻る、つまり「還る」ことからきています。 この「暦」は干支の意味であり、干支自体は十干と十二支という二つの...
 か行
か行“頑張る(がんばる)”という言葉は、日本語でよく「努力する」や「忍耐する」といった意味で使われますが、その語源は「我に張る」という表現に由来しています。 この元々の意味は「自分の意志を押し通す」と...
 か行
か行“カンパニー”という言葉は、日本で「会社」や「商社」を意味する際によく使用されますが、その語源は英語の”company”から来ています。 英語の”company...
 か行
か行「カンニング」という言葉は、試験などでの不正行為を指す日本独自の用語です。 この語は、英語の「cunning」という単語が日本で特定の形で用いられるようになったものです。 「cunning」は、元々「ずるい」や「狡猾」と...
 か行
か行「神無月(かんなづき)」は、陰暦の十月を指す日本独特の月名です。 元々は「かみなづき」と呼ばれていたものが、音便によって「かんなづき」と変化しました。 この名前にはいくつかの解釈があり、その中でも特に有名なのは、この月に...
 か行
か行「カンナ」、または漢字での表記「鉋」は、材木の表面を削って滑らかにするための道具を指します。 これには多くの種類があり、一般的には「台鉋」を指すことが多いですが、他にも「槍鉋」などが存在します。 また、「轆轤鉋」のことを...
 か行
か行「勘当」という言葉は、もともと「法に当てはめて処罰すること」を意味していました。 ここでの「勘」は「考える」という意味で、罪や問題行動を評価し、それに適切な処罰を当てはめるという概念を指していたのです。 この基本的な意味...
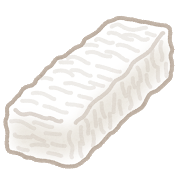 か行
か行寒天とは、主にテングサという海草から作られる弾力のある食品や工業用材料です。 その名前は日本の江戸時代前期に由来しています。 当時、京都市伏見にいた旅館の主人、美濃太郎左衛門が心太(ところてん)を寒い屋外に置いておいたと...
 か行
か行「カンツォーネ」という言葉は、イタリア語で歌謡曲を意味する「canzone」から来ています。 この「canzone」は、フランス語の「シャンソン」とも同源で、どちらも「歌」を意味します。 古くは、この形式はイタリアの詩人...
 か行
か行「肝胆相照らす(かんたんあいてらす)」という表現は、人々がお互いに心の底まで打ち明けて親しく交わる様子を描写するものです。 この表現において、「肝胆」はそれぞれ肝臓と胆嚢を指します。 これらの器官は生命を支える非常に重要...
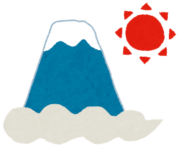 か行
か行「元旦(がんたん)」という言葉は、「元」と「旦」の二つの漢字から成り立っています。 ここで、「元」は「はじめ」や「最初」といった意味を持ち、一方で「旦」は「夜明け」や「早朝」を意味しています。 この二つの漢字を組み合わせ...
 か行
か行「頑丈(がんじょう)」という言葉は、堅固で丈夫な状態を指す日常語としてよく用いられますが、その語源は実は馬に関する表現から来ています。 元々、丈夫な馬を指して「四調者(ガンジョウ)」と呼んでいました。 ここでの「四調」と...
 か行
か行「勘定(かんじょう)」という言葉は、複数の意味を持ちますが、その核となる部分は「考え定めること」です。 この点が、言葉の語源・由来にも繋がっています。 言葉に含まれる漢字、「勘」は「考える」ことを、「定」は「決める」こと...
 か行
か行「元日(がんじつ)」という言葉は、その名の通り年の最初の日、すなわち1月1日を指します。 この言葉における「元」という字は、「はじめ」や「始まり」といった意味を持っています。 一方で、「日」は日付や日を指す文字です。 こ...
 か行
か行漢字(かんじ)という言葉は、文字体系として古代中国で生まれ、中国の漢民族によって使用されていたことからこの名前がつけられました。 具体的には、「漢」は漢民族または漢朝(古代中国の王朝)を指し、「字」は文字を意味します。 ...
 か行
か行「観光」という言葉は、もともと古典中国の文献『易経』に「観光」という形で登場しています。 この文献においては、「国の光を観る」という形で使われ、主に「国の威光や状態を観察する」という意味合いで用いられていました。 この点...
 か行
か行「管弦楽」という言葉は、もともと日本の雅楽、すなわち宮廷音楽で用いられていた言葉です。 この場合、「管」は管楽器、すなわち笛や角笛などの吹き楽器を、「弦」は弦楽器、すなわち琴や筝などの弦を引く楽器を指します。 この二つの...
 か行
か行カンカン帽は、麦わらを密に編み込んで作られた帽子で、糊で強化されているため非常に固い構造を持っています。 この帽子の名前については複数の説がありますが、一つは「かんかんと照りつける夏の日射しを避ける」という意味があるとさ...
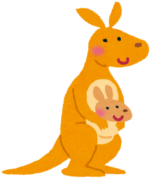 か行
か行「カンガルー」という名前は、オーストラリアの原住民の言葉で「跳ぶもの」を意味する「gangurru」から来ています。 この名前が広まったきっかけとされるのは、ジェームズ・クック船長が率いる探検隊がオーストラリアに上陸した...
 か行
か行日本語の「考える」は、物事を理解し解決するといった一連の思考過程を指します。 しかし、この言葉がどのように形成されたかについては、古い表現「かむがふ」が一つの手がかりとなっています。 「かむがふ」は二つの部分、「か」と「...
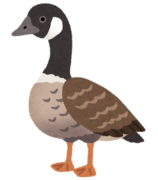 か行
か行「雁(がん)」と呼ばれる鳥は、カモ目カモ科に属する比較的大型の水鳥で、日本では古くから親しまれています。 この鳥の名前については、いくつかの興味深い変遷と説があります。 最も古い呼称としては「カリ」という名があります。 ...
 か行
か行「癌(がん)」という言葉は、悪性腫瘍を指す医学用語であり、その語源は多層的です。 まず、英語の「cancer」が該当する医学用語として広く認知されています。 この「cancer」は、ギリシャ語の「karkinos」に由来...
 か行
か行「代わり番こ」という言葉は、交替で何かをする、特に子供がよく使うやや親しみやすい表現です。 この言葉の語源にはいくつかの考え方がありますが、一つはたたら製鉄に由来するというものです。 たたら製鉄とは、鉄を作る古い方法の一...
 か行
か行「川柳(かわやなぎ)」は主に三つの意味で用いられますが、その中でも最も基本的なのは、川辺に生える柳の木を指す意味です。 この名称は非常に直訳的で、川の近くに自生する柳の木であることから「川柳」と呼ばれています。 また、ヤ...
 か行
か行「厠(かわや)」は、大小便をする場所、すなわち便所を指す日本語の古い語です。 古事記にも「朝署(あさけ)に厠に入りし時」との記述があり、その歴史は古いものとされています。 この名前にはいくつかの説がありますが、一つの説は...
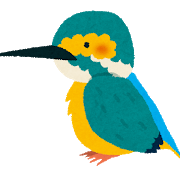 か行
か行「カワセミ」は、特に日本で親しまれている美しい鳥であり、その名前は「川に棲むセミ」という意味があるとされています。 ここでの「セミ」は、古名である「ソニ」から変化した形で、この「ソニ」には土を意味する「ニ」が含まれていま...
 か行
か行「革(かわ)」と「皮(かわ)」は同源であり、基本的に動植物の外表を覆う膜や獣類の皮を特に加工したものを指します。 語源に関しては複数の説がありますが、共通するのは「覆う」や「包む」という概念です。 一つの説は、「かわ」が...
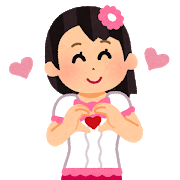 か行
か行「かわいい」という言葉は、実はその歴史と語源において多様な意味変化を経ています。 元々は「カホハユシ(顔映)」という表現から転じた「カハユシ」が起源であり、この「ハユシ」部分は、目にまぶしいような、体に変調をきたすような...
 か行
か行「辛うじて」という表現は、語源としては「辛い」に由来しています。 この「辛い」は、元々は「からし」という形容詞から来ており、塩からい、もしくはしょっぱいという意味で使われていました。 しかし、時が経つにつれて、この「から...
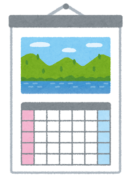 か行
か行「カレンダー」という言葉は、英語の「calendar」から来ていますが、その更なる起源はラテン語にあります。 ラテン語で「帳簿」を意味する「calendarium」が元とされ、この「calendarium」はさらに「朔日...