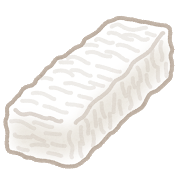寒天とは、主にテングサという海草から作られる弾力のある食品や工業用材料です。
その名前は日本の江戸時代前期に由来しています。
当時、京都市伏見にいた旅館の主人、美濃太郎左衛門が心太(ところてん)を寒い屋外に置いておいたところ、それが自然に凍結・乾燥して寒天が偶然に発見されました。
その後、美濃太郎左衛門はこの新たに発見されたものを万福寺の隠元禅師に試食してもらい、絶賛を受けたそうです。
この出来事がきっかけで、新しい食品は「寒空(寒い日の空)」に由来して「寒天」と命名されました。
このように、寒天はある種の偶然と、それに対する評価や命名のプロセスを経て、今日知られる形になっています。
かんてん【寒天】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「寒天」が何であるか、どのような経緯と評価を経て広まったのかについてカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 基本の意味 | テングサという海草から作られる弾力のある食品や工業用材料。 |
| 起源 | 日本の江戸時代前期、京都市伏見に由来。 |
| 発見者 | 旅館の主人、美濃太郎左衛門。 |
| 発見の経緯 | 心太(ところてん)を寒い屋外に置いたところ、自然に凍結・乾燥して偶然に発見された。 |
| 評価 | 万福寺の隠元禅師に試食してもらい、絶賛を受けた。 |
| 命名 | 「寒空(寒い日の空)」に由来して「寒天」と命名された。 |
| 現代での知名度 | 偶然と評価・命名のプロセスを経て、今日知られる形になっている。 |