あんま【按摩】の語源・由来
「按摩」(あんま)という言葉は、主にマッサージやそのような療法を施す人を指す言葉として広く知られています。 この言葉は、二つの漢字「按」と「摩」から構成されています。 それぞれの漢字が示す意味が、この言葉が指す療法の本質...
 あ行
あ行「按摩」(あんま)という言葉は、主にマッサージやそのような療法を施す人を指す言葉として広く知られています。 この言葉は、二つの漢字「按」と「摩」から構成されています。 それぞれの漢字が示す意味が、この言葉が指す療法の本質...
 あ行
あ行「アンブレラ」という言葉は、英語の「umbrella」がその起源です。 さらに深く掘り下げると、「umbrella」はラテン語の「umbra」という言葉に由来しています。 この「umbra」は「影」という意味を持ちます。...
 あ行
あ行「案の定」という表現は、予想や計画が実際にその通りになった場合に使われる日本語の成句です。 この成句は二つの漢字「案」と「定」から成り立っています。 「案」には「計画」「着想」「推量」といった意味があります。 これは何ら...
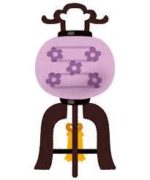 あ行
あ行「あんどん」という言葉は、主な用途が照明具であることから、日本の文化や歴史にも深く関わっています。 この言葉の語源は、漢字で「行灯」と書きますが、その読み方「あんどん」は唐音に由来しています。 唐音とは、中国の唐代に成立...
 あ行
あ行「暗中模索」という言葉の語源は、中国の文献「隋唐佳話」に登場する故事に由来します。 この故事には、古代中国の唐の時代に宰相を務めた許敬宗という政治家が登場します。 許敬宗は非常に優れた文才を持っていたものの、物忘れが非常...
 あ行
あ行「アンジェリカ」という名前は、ラテン語の「Angelicus」に由来しており、これは「天使」を意味します。 この名前の背景には、ヨーロッパで疫病が蔓延していた時期に関する美しい伝説があります。 この伝説によれば、疫病が流...
 あ行
あ行「あんころ餅」の名前は、外側に餡(あん)がついている餅の形状から来ているとされています。 具体的には、餡が餅を覆うような「衣」の役割を果たしていることから、この餅は元々「餡衣餅(あんころももち)」と呼ばれていたと言われて...
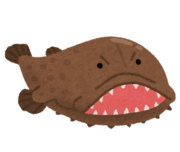 あ行
あ行「アンコウ」の名前の由来にはいくつかの説があり、一つの明確な答えがないのが現状です。 そのいくつかの説を挙げると、一つは「あんぐり」という言葉が変化したものであり、これはアンコウの大きな口に由来すると言われています。 ま...
 あ行
あ行「アンケート」という言葉は、フランス語の「enquête」に由来しています。 このフランス語の言葉は、もともと「調査」や「質問」を意味しており、英語ではそれに相当する「survey」や「questionnaire」が用い...
 あ行
あ行「アンカー」という言葉は多様な意味を持ちますが、その語源は主に英語の「anchor」から来ています。 この英語の言葉は元々船の錨(いかり)を指すもので、船を一か所に固定する役割を果たします。 この概念がスポーツにおいても...
 あ行
あ行「あわよくば」という言葉は、日本語の古語「あわ」と接続助詞「ば」が組み合わさって作られました。 「あわ」は「間」や「隙間」、「合間」といった意味で用いられていた古語です。 この言葉は元々、「都合がよければ」や「機会があれ...
 あ行
あ行アロマテラピーという言葉は、”aroma”(芳香)と”therapy”(療法)という二つの英語の単語を組み合わせた造語です。 この療法では、植物から抽出された精油やその他の...
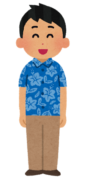 あ行
あ行アロハシャツは、その名前が示す通り、ハワイで生まれたファッションアイテムです。 “アロハ”という単語はハワイ語で、挨拶に使われる言葉です。 これが「ようこそ」「さよなら」などの意味を含むとともに、...
 あ行
あ行「アレルギー」という言葉は、1906年にオーストリアの小児科医ピルケによって命名されました。 この名前はドイツ語の「allergie」からきており、さらにその根底にはギリシア語の「allos」(変わる)と「ergon」(...
 あ行
あ行「アルマジロ」という名前は、この動物が特有の堅い甲羅によって保護されている特性を表しています。 この名前はスペイン語の「armado」に由来しており、それは「鎧を着た小さなもの」という意味を持っています。 実際にアルマジ...
 あ行
あ行「アルファベット」という言葉は、文字が音素を表現するような文字体系の一般名として使われます。 この言葉は、特にローマ字や英語で用いられる26文字を指すこともあります。 この言葉の語源は、ギリシア文字の最初の二文字、すなわ...
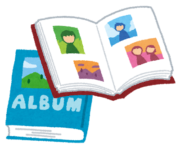 あ行
あ行「アルバム」という言葉は、様々なコレクションを保存する帳面や、音楽の複数の曲をまとめたメディアに使われています。 この言葉の語源はラテン語の「albus」にあります。 このラテン語は「白い」という意味を持っています。 古...
 あ行
あ行「ありきたり」という言葉は、室町時代頃に登場したとされる動詞「有り(在り)来たる」の連用形から派生したものです。 この「有り(在り)来たる」という表現は、もともと「存在し続けていたもの」という意味を持っていました。 つま...
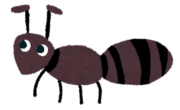 あ行
あ行「アリ」という名前にはいくつかの語源説があります。 一つの説によれば、この名前は動詞「歩く」が変化した「アリク」からさらに短縮されて「アリ」になったと言われています。 この説はアリの特徴的な歩き方、すなわち地面を進む姿を...
 あ行
あ行「あらまし」という言葉は、元々「あり」という動詞に助動詞「まし」が付いた形から派生しています。 この「あり」は「ある(存在する、起こる)」という意味で、助動詞「まし」が加わることで、「ありたいと願う」や「ありそうなことを...
 あ行
あ行「嵐(あらし)」という言葉は、もともとは山間に吹く風を指していました。 古くからの文献、例えば『万葉集』や『古今和歌集』にもこのような用例が見られます。 語源とされるのは「荒風(あらし)」で、初めは特に山で感じる強い風を...
 あ行
あ行「洗い」という言葉には主に二つの意味があります。 一つ目は単純に「洗うこと」、または「洗濯」という行為を指します。 二つ目は、特定の魚の肉を冷水で洗って縮ませる料理方法、特にさしみの一種です。 この語の由来については非常...
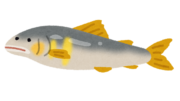 あ行
あ行鮎(アユ)はキュウリウオ科アユ亜科に属する硬骨魚で、特に日本で人気のある食用魚です。 この魚の名前、「アユ」は古語の「落ゆ」から来ているとされています。 この「落ゆ」は「落ちる」または「こぼれ落ちる」といった意味がありま...
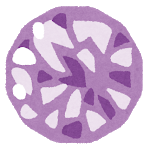 あ行
あ行アメジストという名前は、ギリシア語の「amethustos」に由来しています。 このギリシア語の語源「amethustos」は「酔わせない」という意味があります。 古代ギリシャでは、アメジストで作られた杯で酒を飲むと、そ...
 あ行
あ行「雨(あめ)」という言葉には、主に二つの語源に関する説があります。 一つは「天(あめ)」が同語であるとする説で、もう一つは「天水(あまみづ)」からの約転であるとする説です。 日本の気候は湿潤で雨が多く、水田農耕や山林など...
 あ行
あ行「飴(アメ)」という言葉は、甘いものに関連する言葉「あま味」や「あま水」が転じて生まれたとされています。 その語源には古い文献も参照されており、日本書紀の神武紀には飴を「たがね」と表記して言及されています。 古い記録によ...
 あ行
あ行「天の川」という名前は、川が夜空を横切るような見た目に似ていることから来ています。 実際には、これは銀河系の円盤部の恒星が天球に投影された姿で、数億以上の恒星から成っています。 この名称は中国の文化とも関連があり、古代中...
 あ行
あ行「あまねく」という日本語の表現は、形容詞「あまねし」の連用形から派生したものです。 この「あまねし」は、物事が広く行き渡っている、つまり広範にわたるという意味を持ちます。 それが連用形として「あまねく」と変化し、この形が...
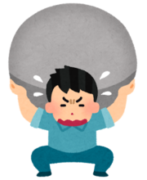 あ行
あ行「あまつさえ」という表現は、「あまり(余り)」と助詞の「さえ」が組み合わさって形成された語です。 ここでの「あまり」とは、一定の量や程度を超えた余分なもの、またはその状態を指す言葉です。 助詞の「さえ」は、何かが特に重要...
 あ行
あ行「アマダイ」または「甘鯛」には、名前の語源や由来について複数の説があります。 一つ目の説は、この魚が特に美味で「甘み」があるために「アマダイ」あるいは「甘鯛」と呼ばれた、というものです。 これに関連して、徳川家康がこの魚...