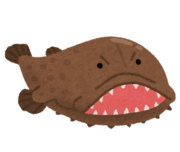「アンコウ」の名前の由来にはいくつかの説があり、一つの明確な答えがないのが現状です。
そのいくつかの説を挙げると、一つは「あんぐり」という言葉が変化したものであり、これはアンコウの大きな口に由来すると言われています。
また、アンコウの体色から「赤魚」が転じたという説もあります。
さらに、アンコウが岩穴でじっとしている様子を「安居(あんご)」と表現したことが名前の由来であるとも指摘されています。
この他にも、「顎」や「暗愚」が名前の由来となったという説も存在します。
古い文献にも「アンコウ」の記載があり、例えば「日葡辞書」には「アンカウ、また、アンガウ」と書かれており、これは現代でも「あんこう」「あんごう」として読まれています。
また、「文明本節用集」という文献に「鮟鱇、アンカウ、有足魚也 心気良薬」とあることから、元々は山椒尾(さんしょうお)を指す名前だった可能性もあります。
総じて、アンコウの名前の由来は複数の説があり、時代や地域、さらにはその特性によって名付けられた可能性が高いです。
アンコウ【鮟鱇】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「アンコウ」名前の由来と説をカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・内容 |
|---|---|
| 複数の説存在 | アンコウの名前の由来には明確な答えがなく、複数の説が存在する。 |
| 「あんぐり」説 | アンコウの大きな口に由来するとされ、言葉「あんぐり」が変化したものと言われている。 |
| 「赤魚」説 | アンコウの体色から「赤魚」が転じたという説がある。 |
| 「安居(あんご)」説 | アンコウが岩穴でじっとしている様子が「安居」として名前の由来であるとも指摘されている。 |
| その他の説 | 「顎」や「暗愚」が名前の由来とされる説も存在する。 |
| 古い文献 | 「日葡辞書」や「文明本節用集」などの古い文献にもアンコウの記載があり、元々は山椒尾(さんしょうお)を指す名前だった可能性も。 |