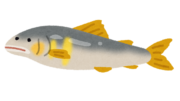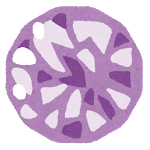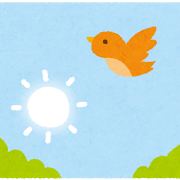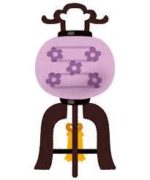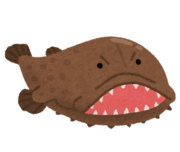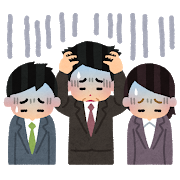鮎(アユ)はキュウリウオ科アユ亜科に属する硬骨魚で、特に日本で人気のある食用魚です。
この魚の名前、「アユ」は古語の「落ゆ」から来ているとされています。
この「落ゆ」は「落ちる」または「こぼれ落ちる」といった意味があります。
この名前は、アユが川で成長し、産卵を控えてその川を下る姿に由来すると考えられています。
さらに、鮎の漢字表記についても興味深い点があります。
現在でよく使われる「鮎」の字は、奈良時代頃から用いられていますが、元々この字は「ナマズ」という全く異なる魚を指していたとされます。
漢字の「鮎」において、右側にある「占」の部分には二つの説があります。
一つは、アユが縄張りを持つ性質から「占める」と関連付けられたという説です。
もう一つは、日本書紀に記されている神功皇后が占いのために釣りをした際にアユが釣れたことに由来するという説です。
以上のように、「アユ」やその漢字表記「鮎」には複数の意味や由来が組み合わさっており、その名前は生態や歴史、文化と深く関わっているわけです。
アユ【鮎】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、アユの名前の由来や漢字表記についてカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・特徴 |
|---|---|
| 分類 | キュウリウオ科アユ亜科に属する硬骨魚。 |
| 名前「アユ」の由来 | 古語の「落ゆ」から来ている。この言葉は「落ちる」または「こぼれ落ちる」という意味があり、アユが川で成長してその後下る姿に由来する。 |
| 漢字「鮎」の由来 | 元々は「ナマズ」を指していた。奈良時代から使われ始めた。 |
| 漢字「鮎」の右側の「占」 |
|