「つまずく」の語源・由来
「つまずく」という動詞は、文字通り足の爪が何かに突き当たって躓く様子を表すものとして、元々「爪突つまつく」という言葉から派生したものです。 具体的には、歩行中に足の爪が障害物などにぶつかり、その結果として体のバランスを失...
 つ行
つ行「つまずく」という動詞は、文字通り足の爪が何かに突き当たって躓く様子を表すものとして、元々「爪突つまつく」という言葉から派生したものです。 具体的には、歩行中に足の爪が障害物などにぶつかり、その結果として体のバランスを失...
 つ行
つ行「鶴瓶鮨」は、奈良県の吉野川で取れるアユを使った馴鮨の一種で、特に下市町で製造されます。 この名前の由来は、酢で締めたアユの腹部にすし飯を詰める工程と、製造されたすしを保存するための特有の容器に関連しています。 この鮨は...
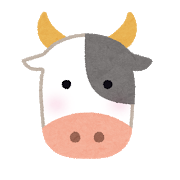 つ行
つ行「ツラミ」は、牛の頬肉を指す言葉です。 この名前の由来は、「ツラ」が「面」や「頬」を意味することから、「ツラの身」という意味で命名されました。 つまり、牛の頬の部分の肉を指す言葉として「ツラミ」が使われるようになったので...
 つ行
つ行「露払い」という言葉は、もともと蹴鞠(けまり)の用語として使用されていました。 蹴鞠の際、鞠庭で鞠を最初に蹴ることで、その周囲の樹木についた露を払い落とす行為、あるいは、その行為を担当する人を指して「露払い」と称していま...
 つ行
つ行「梅雨」は、6月頃に見られる長雨やその雨期を指す言葉として知られています。 この言葉は、もともと中国から日本へと伝わってきました。 当初は「ばいう」として読まれていましたが、江戸時代に入ると「つゆ」という読み方が一般的に...
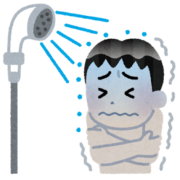 つ行
つ行「冷たい」という言葉は、私たちが日常的に使う形容詞で、主に低い温度を持つものや感情的な冷淡さを指す際に用いられます。 この言葉の起源は、寒さにより指先や足先の爪が痛く感じる状態を指す「爪痛し(つめいたし)」に由来していま...
 つ行
つ行「つめ」という言葉は、私たちの指や足の先端に生じる角質の突起を指します。 この言葉の由来にはいくつかの考え方があります。 まず、「つめ」は「端(つま)」という言葉から派生したとされています。 ここでの「端」は物の端や先端...
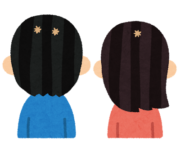 つ行
つ行「つむじ」という言葉は、主に人の頭頂に見られる渦巻き状の毛を指します。 この言葉の名前の由来は、渦巻きの特徴と「旋風(つむじかぜ)」、すなわち渦のように巻き上がる風の特徴を結びつけたことに始まります。 言葉「つむじ」の中...
 つ行
つ行「つみれ」という料理は、魚のすり身に卵、小麦粉、塩などを加えてすり合わせたものを、少しずつすくい取ってゆでることで作られます。 この料理の名前の由来は、作り方に関連しています。 魚のすり身などの混合物を手で摘み取り、汁や...
 つ行
つ行「つまらない」という言葉は、多様な意味を持ちます。 それは、「道理に合わない」や「おもしろくない」といった感じのものから、「価値がない」といった評価に至るまで、さまざまな状況や感情を表現するのに用いられます。 また、「ば...
 つ行
つ行「爪楊枝」という言葉は、歯の間の食べ残しを取ったり、食べ物を突き刺すための小さな棒を指します。 このアイテムの歴史と名前の由来は、仏教と深く関連しています。 奈良時代、仏教がインドから中国と朝鮮半島を経由して日本に伝わっ...
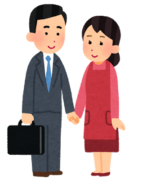 つ行
つ行「つま」、現代で主に「妻」として知られるこの言葉は、元々男女を問わず配偶者の一方を指す言葉として使われていました。 かつては「夫」という漢字を用いて「つま」と読まれていたのです。 この言葉の成り立ちに関しては、語根「つ」...
 つ行
つ行「ツボクサ(壺草)」は、セリ科の多年草で、特徴的な形状の花を持っています。 その名前に関する由来には複数の説が存在します。 一つの説として、この草の花の形が「うつぼ(靫)」という矢を収める筒に似ていることから、元々「ウツ...
 つ行
つ行「ツボ(壺)」という言葉は、さまざまな意味を持ちますが、特に容器の形状に関連するものとしては、口が細くて胴が丸く膨らんだ形を指します。 また、この言葉は「くぼんだ場所」や「特定の部分」など、他の多くの意味でも用いられてい...
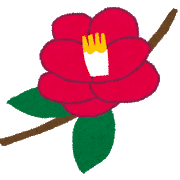 つ行
つ行「ツバキ」という名前は、ツバキの葉の特徴に関連したいくつかの説から派生しています。 ひとつの説によれば、ツバキの葉が艶やかで光沢があるため、「艶葉木(つやばき)」という名前から転化したとされます。 一方、別の説では、ツバ...
 つ行
つ行「つば」や「唾」という言葉の起源は、古くは「つはき(唾吐き)」という形で存在していました。 この「つはき」は、唾を吐き出すという行為を指す動詞でした。 そして平安時代に移ると、この「ツハキ」が唾液を意味する名詞として用い...
 つ行
つ行「角隠し」は、かつて浄土真宗門徒の女性が寺参りの際に用いていた特定のかぶりものを指します。 このかぶりものは、約12センチメートルの幅と約72センチメートルの長さを持つ白絹(内側は紅絹)で作られ、女性はこれを前髪にかぶり...
 つ行
つ行「津波」や「津浪」は、特定の自然現象を指す言葉として知られています。 これは、地震による海底の陥没や隆起、海中の土砂崩れ、または海底火山の噴火といった原因により、水面に大きな波動が生じる現象を指します。 特に海岸近くでは...
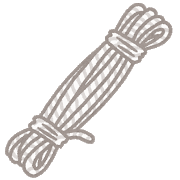 つ行
つ行「綱」という言葉は、植物繊維や針金などを撚り合わせて太く長く作られるものを指します。 これは物を結びつけるためや頼りにするためのものとして使用されるほか、特定の文化や場面、例えば相撲の横綱の力士が締める注連縄としても用い...
 つ行
つ行ツツジは、多くの山地で自生する常緑または落葉の低木で、観賞用としても広く栽培されています。 春から夏にかけて、色とりどりの美しい大型の花を咲かせるのが特徴です。 この「ツツジ」という名前の由来については、いくつかの説が存...
 つ行
つ行「突慳貪」は、人との関わりにおいて不親切や愛想がなく、とげとげしい態度を取ることを指す言葉です。 この表現の語源を深掘りすると、「慳貪」という言葉が核となっており、それ自体が「なさけ心のないこと」や「愛想のないこと」を意...
 つ行
つ行「恙無い」または「つつがない」という言葉は、病気や異常がないこと、つまり無事であることを示す日本語の古典的な表現です。 この言葉の語源を探ると、「つつが」あるいは「恙」とは病気や異常を指す言葉であり、「無い」はその存在が...
 つ行
つ行「土に灸」という言葉は、効果のないことや無駄なことを示すたとえとして使われます。 この表現の起源は、文字通り「土に灸を置く」という行為にあります。 灸はもともと治療の一環として体に直接灸を置くことで効果を得られるものです...
 つ行
つ行「つくばい」、別名「蹲」や「蹲踞」という言葉は、本来「うずくまる」や「つくばう」という動作を意味しています。 特に、茶の湯の文化においては、茶室に入る前に手や口を清めるための手水鉢を指す言葉として使われるようになりました...
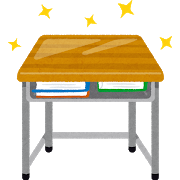 つ行
つ行「つくえ」という言葉は、現代日本語では多くの人にとって、読書や書き物をするための台、すなわち机を指すものとして認識されています。 しかし、この言葉の原初の意味は、そうではありませんでした。 「つくえ」のもともとの意味は、...
 つ行
つ行「つきとすっぽん」、すなわち「月と鼈」という表現は、二つのものの間に極端な差があることを示すたとえとして用いられます。 この表現の背後には、月と鼈という二つのものが、見た目の形状としては丸いという共通点を持ちつつも、その...
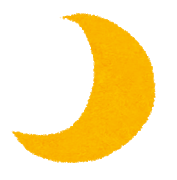 つ行
つ行「つき」という言葉は、我々の惑星、地球の自然衛星であり、夜空でよく目にする明るい天体を指します。 この言葉は日本の文化や言語の中で深い意味を持っており、さまざまな文脈で使用されています。 例えば、自然の美しさや季節の移ろ...
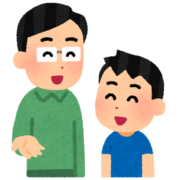 つ行
つ行「つうと言えばかあ」という表現は、お互いに非常に仲が良く、相手の考えや気持ちを少しの言葉で容易に理解することができる関係性を表すものです。 この言葉の背後には、お互いの理解が深い関係性を示す独特なコミュニケーションのやり...
 つ行
つ行「つかぬこと」という表現は、前の話や状況と関係がないこと、またはそれとは異なることを指す言葉として用いられます。 この言葉の背景を理解するためには、日本語の動詞「付く」と、それに付随する打消しの助動詞「ず」を考える必要が...
 つ行
つ行「爪弾き」という言葉は、人を嫌って排斥することを意味します。 この言葉の語源や由来は、仏家の風習である「弾指(だんし)」に関連しています。 「弾指」は、人差し指を曲げて親指の腹部に当て、爪で強く弾いて音を出す行為を指しま...