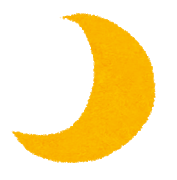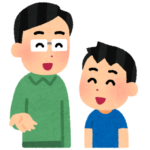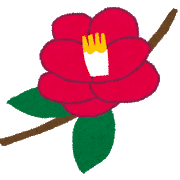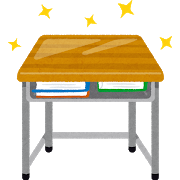「つき」という言葉は、我々の惑星、地球の自然衛星であり、夜空でよく目にする明るい天体を指します。
この言葉は日本の文化や言語の中で深い意味を持っており、さまざまな文脈で使用されています。
例えば、自然の美しさや季節の移ろいを代表するものとして、また、時間の単位や他の衛星、さらには香りや紋所の名前としても使われることがあります。
「つき」の語源については、複数の説が提唱されています。
一つの説は、月が太陽に次いで明るく輝く天体であることから、「次(つぎ)」の意味を持つというものです。
太陽は最も明るい光源であり、月はそれに続く明るさを持つので、この考え方に基づいて「つき」が名付けられた可能性が考えられます。
もう一つの説は、月の満ち欠けの周期を考慮に入れたものです。
月は一定の周期で満ち欠けを繰り返し、欠けの進行によって月の光が「尽きる」ことから、この言葉が名付けられたという解釈です。
どちらの説も、月という天体の特性やその視認性、そして我々の日常生活との関わりを反映していると言えます。
そのため、「つき」という言葉の背後には、天文学的な知識や日常の観察、さらには文化や歴史の中での月の位置づけなど、多様な要素が絡み合っていることが理解できます。
つき【月】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 詳細・内容 |
|---|---|
| 基本意味 | 地球の自然衛星 |
| 文化的な意味 | 日本の文化や言語における深い意味、さまざまな文脈での使用 |
| 使用例 |
|
| 語源の説(1つ目) | 「次(つぎ)」の意味、太陽に次ぐ明るさ |
| 語源の説(2つ目) | 月の満ち欠けの周期、月の光が「尽きる」ことから |
| 重要性 |
|