たんぽぽ【蒲公英】の語源・由来
「たんぽぽ」、または漢字で「蒲公英」と表記されるこの植物は、キク科タンポポ属の多年草を指す総称であり、全世界に広く分布しています。 特に、日本には様々な種類のタンポポが存在しており、カンサイタンポポやエゾタンポポ、シロバ...
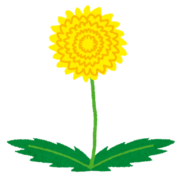 た行
た行「たんぽぽ」、または漢字で「蒲公英」と表記されるこの植物は、キク科タンポポ属の多年草を指す総称であり、全世界に広く分布しています。 特に、日本には様々な種類のタンポポが存在しており、カンサイタンポポやエゾタンポポ、シロバ...
 た行
た行「単刀直入」という言葉は、元々「ただ一人で、一振りの刀を持って敵陣に乗り込む」という意味から来ています。 この具体的なイメージは、文字通り一つの刀で直接的に敵に向かって進む勇敢な行動を描写しています。 この表現の由来は「...
 た行
た行「断腸の思い」という表現は、非常に強い悲しみや苦しみを意味するものです。 この表現の背後には、古代中国の物語が関連しています。 この物語は『世説新語』という書物に収められており、中心となるのは古代中国、晋の桓温です。 彼...
 た行
た行「タンス」や「箪笥」という言葉は、私たちが衣服や小物を整理・保管するための家具として知っているものを指します。 この言葉の起源は、かつて「担子」という形で書かれていたものにあります。 古い時代の中国では「担子」は天秤棒の...
 た行
た行「だんじり」は、関西や西日本の祭りで見られる、太鼓や鉦(かね)といった囃子方が乗る屋台のことを指します。 この屋台は車輪が付いており、人々によって引かれたり、背負われて練行されます。 「だんじり」の名前の由来にはいくつか...
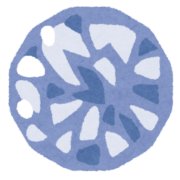 た行
た行タンザナイトは、青紫色の透明な結晶として知られる宝石で、その成分はアルミニウム、カルシウム、鉄の含水ケイ酸塩鉱物であるゾイサイトの一種です。 この宝石の名前「タンザナイト」は、英語の「tanzanite」がその起源となっ...
 た行
た行たんこぶ、またはこぶたんは、瘤を意味する日常的で俗っぽい言い方です。 「たんこぶ」という言葉の由来には、いくつかの説が考えられています。 まず、一つ目の説は、打撲や衝突によってできる瘤の特徴的な音を表現したものと考えられ...
 た行
た行端午の節句は、日本での男子の節句として知られる行事ですが、その名前や由来には深い背景があります。 まず、「端午の節句」の名前の部分「端」は、日本語の「はし」つまり「始め」や「最初」という意味を持ちます。 そして、「午」は...
 た行
た行団子は、日本の伝統的なお菓子の一つで、穀類の粉を水でこねて小さく丸め、蒸したりゆでたりして作ります。 この名前の由来には、いくつかの説が存在します。 まず、最も古いとされる説は、古代中国から日本に伝わった唐菓子「団喜(だ...
 た行
た行タンクトップは、首と腕を大きく露出させた上衣で、ランニングシャツのような形状をしています。 この名前「タンクトップ」は、英語の「tank top」に由来します。 ここでの「タンク」は水泳プールを指し、このデザインは20世...
 た行
た行タングステンは金属元素の一つで、非常に硬く、高い融点を持つ灰白色の金属です。 この名前「タングステン」は英語の「tungsten」に由来しています。 そして、この英語の言葉自体はスウェーデン語で「重い石」という意味を持つ...
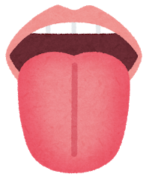 た行
た行「タン」という言葉は、英語の「tongue」から来ており、これは舌を意味します。 この「tongue」は、古い印欧語の「dnghu-」という言葉が起源であり、そこからゲルマン祖語の「tungon」を経て「tongue」と...
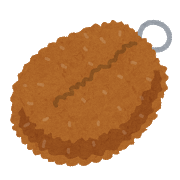 た行
た行「束子」という言葉は、物を「束」にしたものを指す言葉として生まれました。 具体的には、わらや棕梠(しゅろ)の毛などを束ねて作られる、器物をこすり洗うための道具を指します。 その名前は、これらの材料を束ねて作られることから...
 た行
た行「戯け者」の言葉は、ふざけるや愚かなことをするという意味の動詞「戯く」から派生しています。 具体的には「戯く」の連用形が名詞化して「戯け者」となりました。 この名詞は、愚かな行動やふざけた態度をとる人を指す言葉として使わ...
 た行
た行「タレント」という言葉は、英語の「talent」から取り入れられたもので、もともと「才能」や「技能」を意味しています。 この英語の「talent」は、古代ギリシャ語の「talant」に由来し、元々は衡量や貨幣の単位を指す...
 た行
た行「だるま」という言葉は、サンスクリット語の「Bodhidharma」から派生したもので、「菩提達磨」という音写が元となっています。 この中の「dharma」は「法」という意味を持ちます。 達磨大師は、禅宗の始祖とされ、彼...
 た行
た行「だるい」という言葉は、古語の「たるし」が変化してできた言葉です。 この「たるし」は、時が経つにつれて「だるし」という形になり、さらにその後「だるい」という現代の形に変わっていったのです。 この変化の過程で、言葉の頭にあ...
 た行
た行「他力本願」という言葉は仏教の教えに由来しています。 具体的には、阿弥陀如来の本願力に依存して極楽への往生を目指す考え方を指します。 「他力」とは、文字通り他人の力、特に仏教においては自分以外の阿弥陀如来の力を借りること...
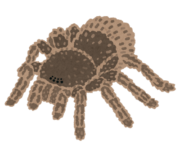 た行
た行「タランチュラ」という名前は、イタリア南部の港町「タラント(Taranto)」に起源を持っています。 過去には、このクモにかまれると「舞踊病」という症状を引き起こすと信じられていました。 この舞踊病とは、激しい発熱を伴っ...
 た行
た行「たらふく」という言葉は、腹一杯に食べたり、何かを十二分に楽しんだりすることを意味します。 この言葉の背後にある「鱈腹」は、実は当て字であり、実際の語源は異なります。 「足らふ」という古い言葉が元になっており、これは「十...
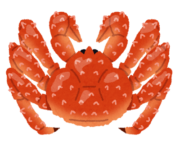 た行
た行「タラバガニ」の名前の由来は、その主要な漁場であるベーリング海やカムチャツカの近海が、タラという魚の漁場とも重複していることから来ています。 そのため、このガニは「タラの場所で獲れるカニ」という意味を持つ「鱈場蟹」と名付...
 た行
た行「タラ」は、タラ科の硬骨魚を指す言葉として知られており、特にマダラを指して「タラ」と言うこともあります。 この名前の由来については複数の説が存在します。 まず、古名「大口魚」のように、タラは大きな口を持ち、多くを捕食する...
 た行
た行「矯めつ眇めつ」という言葉は、物事をいろいろな角度からじっくりと観察する様子を表す言葉です。 言葉の中の「矯め」は、「矯める」という動詞から来ており、目をしっかりと定めてじっと見ることを意味します。 「眇め」は「眇める」...
 た行
た行「ため口」は、相手との対等な関係性や親密さを示す言葉や口調を指します。 この「ため」の部分は、賭博の世界で使われる「ぞろ目」を意味する言葉からきています。 1960年代、不良少年の間でこの言葉が「五分五分」という意味、つ...
 た行
た行「駄目」の言葉は、元々囲碁の用語として使われていました。 囲碁では、盤上に石を配置し、相手の石を取るか、自分の領土を確保することが目的となります。 ところが、盤上には双方の境界線上に位置し、どちらのプレイヤーにとっても領...
 た行
た行「玉の輿」という言葉は、結婚を通じて富や高い社会的地位を手に入れること、特に女性が裕福な家庭に嫁ぐことを指して使われます。 この言葉の背景には、徳川綱吉の生母である桂昌院の物語があります。 桂昌院は、もともと京都西陣の八...
 た行
た行「偶・適」という言葉は、思いがけないさまやまれなこと、または万一という意味を持っています。 この言葉の語源は、「たまたま」の「たま」という部分と、状態や様子を示す接尾語「そか」が組み合わさったものです。 この「そか」は、...
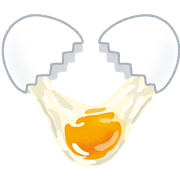 た行
た行「卵」または「玉子」という言葉は、鳥や魚、虫などの雌が産む胚や栄養分を含むものを指しますが、特に私たちが食用とする鶏の卵を指すことが多いです。 さらに、比喩的にはまだ一人前でない人や未熟なものを指すこともあります。 この...
 た行
た行「食べる」という動詞の起源は、「たぶ」という言葉に関連しています。 この「たぶ」は、もともと「タマフ」という言葉が変化したもので、「賜」すなわち「いただく」という意味を持っています。 つまり、もとの意味は飲食物を神や上位...
 た行
た行足袋は、足の形に合わせて作られた袋状の履物で、親指と他の指を分ける特徴的な形状を持っています。 この形状は、小さな鉤(こはぜ)で留めることができる爪形の合せ目によって形成されています。 もともとは草鞋を履くときの下履きや...