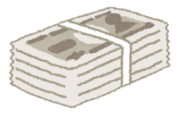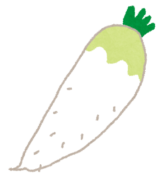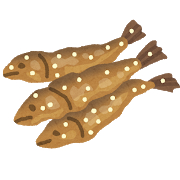足袋は、足の形に合わせて作られた袋状の履物で、親指と他の指を分ける特徴的な形状を持っています。
この形状は、小さな鉤(こはぜ)で留めることができる爪形の合せ目によって形成されています。
もともとは草鞋を履くときの下履きや寒さを防ぐために使われ、後には礼装用としても用いられるようになりました。
歴史を振り返ると、鎌倉時代の終わり頃からは革製の足袋が、そして1643年頃からは木綿製の足袋が作られ始めました。
初期の足袋は筒部分が長く、紐で結ぶタイプでした。
足袋の名称の由来に関しては、元々、鹿や猪の一枚革で作られた「半靴」という履物があり、この「半靴」を「単皮(たんぴ)」と呼んでいたことから、足袋という名前が生まれたと考えられています。
ここでの「足袋」という言葉は、意味を示すための当て字として使われています。
たび【足袋】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、足袋の詳細や背景に関する情報をカンタンにまとめます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基本の特徴 | 袋状の履物で、親指と他の指を分ける形状。鉤(こはぜ)で留める爪形の合せ目を持つ。 |
| 使用目的 |
|
| 歴史的背景 | 鎌倉時代の終わりから革製の足袋、1643年頃から木綿製の足袋。初期は筒部分が長く、紐で結ぶタイプ。 |
| 名称の由来 | 「半靴」を「単皮(たんぴ)」と呼び、これが「足袋」という名前の起源。当て字としての使用。 |