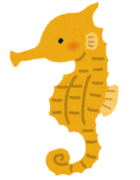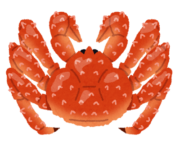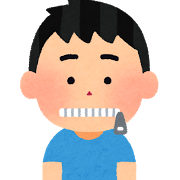端午の節句は、日本での男子の節句として知られる行事ですが、その名前や由来には深い背景があります。
まず、「端午の節句」の名前の部分「端」は、日本語の「はし」つまり「始め」や「最初」という意味を持ちます。
そして、「午」は古い暦の記号で、5月の最初の午の日を指します。
もともと、この日を祝う風習が存在していました。
しかしながら、この「午」が数字の「五」と同じ音を持つため、時間が経つうちに5月5日を端午の節句として祝う日として定着しました。
この風習自体は、元々は中国から伝わったものとされています。
中国では端午の節句は、楚の詩人で政治家でもあった屈原を供養する日として知られていました。
しかし、日本に伝わる過程で、元々日本に存在していた風習と混合しました。
具体的には、日本には、5月、つまり田植えの時期に、稲の神様に豊作を祈って行われる風習がありました。
この風習では、早乙女という若い女性が神社に籠り、田植え前に穢れを祓う「五月忌み」という儀式を行っていました。
この「五月忌み」と中国から伝わった端午の節句が混ざり合って、現在の形になったと言われています。
さらに、江戸時代以降、武家の文化として、幟や甲冑を家の中に飾る風習が生まれました。
この影響により、端午の節句は男子を祝福する節句としての性格を強く持つようになりました。
このように、端午の節句は日本独自の風習と中国の伝統が混ざり合って、現在の形になったと言えます。
【端午の節句】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、端午の節句の背景や由来に関する他の情報や詳細についてカンタンにまとめます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 端午の節句の名前 | 「端」は「始め」や「最初」、「午」は古い暦の記号で5月の最初の午の日を指す |
| 5月5日の由来 | 「午」と数字の「五」が同じ音を持つため、5月5日が祝う日として定着した |
| 風習の起源 | 中国の端午の節句は、詩人・政治家の屈原を供養する日。日本に伝わり、日本独自の風習と混合した |
| 日本独自の風習「五月忌み」 | 5月の田植えの時期に、早乙女が神社に籠り、穢れを祓う儀式を行う風習 |
| 江戸時代の影響 | 幟や甲冑を飾る風習が生まれ、端午の節句は男子を祝福する性格を強く持つようになった |
| 総評 | 端午の節句は、中国の伝統と日本の風習が混ざり合って、現在の形になった |