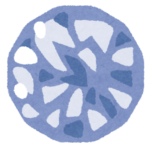「だんじり」は、関西や西日本の祭りで見られる、太鼓や鉦(かね)といった囃子方が乗る屋台のことを指します。
この屋台は車輪が付いており、人々によって引かれたり、背負われて練行されます。
「だんじり」の名前の由来にはいくつかの説があります。
ひとつの説は、「台摺り(だいずり)」が時と共に言葉が変化し、「だんじり」になったというものです。
この説は、屋台が地面を引き摺ることから来ているとされています。
また、祭壇の奥の部分、すなわち「祭壇の尻」を意味することから名付けられたとする説もあります。
さらに、屋台がじりじりとゆっくりと進む様子から、「台じり」と名付けられ、それが「だんじり」になったという説も存在します。
さらに、歴史的な出来事を背景にした説として、良王親王が家臣に命じて親の敵「台尻大隅守」を討ち取った際、その喜びの声として「台尻討った」と叫ばれ、それが祭りの名として受け継がれ、「だんじり」となったという話も伝えられています。
ただし、正確な由来は不明で、これらの諸説の真偽は定かではありません。
また、この「だんじり」に関連する祭りとしては、有名なものとして「岸和田だんじり祭り」があります。
この祭りの起源は、1703年に岸和田藩主の岡部長奏公が京都伏見稲荷を岸和田城内の三の丸に奉納し、五穀豊穣を祈った稲荷祭りから始まったとされています。
【檀尻・(楽車)・(地車)】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「だんじり」に関する重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本概念 |
|
| 名前の由来(諸説) |
|
| 有名な祭り | 岸和田だんじり祭り |
| 岸和田だんじり祭りの起源 | 1703年、岸和田藩主の岡部長奏公が京都伏見稲荷を岸和田城内に奉納 |