「ずぼら」の語源・由来
「ずぼら」という言葉は、怠け者やだらしない様子を表す言葉として使われます。 この言葉の起源は、昔の寺を指す言葉「坊」と、寺の主、すなわち僧侶を指す言葉「坊主ぼうず」に関連しています。 寺や僧侶には尊重されるものも多かった...
 す行
す行「ずぼら」という言葉は、怠け者やだらしない様子を表す言葉として使われます。 この言葉の起源は、昔の寺を指す言葉「坊」と、寺の主、すなわち僧侶を指す言葉「坊主ぼうず」に関連しています。 寺や僧侶には尊重されるものも多かった...
 す行
す行「ズバリ」という言葉は、物事の核心や急所を直接的に、または確実に捉える様子を表す言葉として現代ではよく使われます。 この言葉の起源は、実は鎌倉時代にさかのぼります。 その当時、この言葉は刀や包丁で物を勢いよく切る際の擬態...
 す行
す行「素晴らしい」という言葉は、現代では非常にすぐれたものや事柄を称賛する際に使われる言葉として知られていますが、その起源は意外にも否定的な意味を持っていました。 古くは、この言葉は良くない事態や状態を表す際に用いられ、具体...
 す行
す行「スパム」という言葉は、今日でいうと迷惑メールや大量の不要な情報を指すようになりましたが、元々はアメリカのHomel Foods Corp.が製造する豚肉のハムの缶詰の商標でした。 この名前が迷惑メールと結びつくきっかけ...
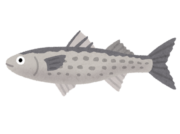 す行
す行「スバシリ」はボラの幼魚を指す名称です。 この名前は、ボラの幼魚が海水魚であるにもかかわらず、幼魚の頃にはよく淡水域に遡上する習性があることに関連しています。 「洲走」という言葉から名付けられたとされ、これは幼魚が淡水と...
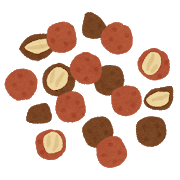 す行
す行「スパイス」という言葉は、英語の「spice」に由来しています。 そして、「spice」の語源は、ラテン語の「species」です。 もともと「species」は「見ること」や「種類」、「商品」などの意味を持っていました...
 す行
す行「スパイ」という言葉は、英語の「spy」から来ています。 この「spy」の語源は、古期フランス語の「espion」で、これは「見張るもの」や「監視するもの」を意味します。 「espion」自体は、印欧語の「見る」という意...
 す行
す行「すね」という言葉の由来については複数の説がありますが、確定的なものはないようです。 一つの説としては、それが「足茎骨(あしぐきほね)」、つまり足の骨の部分を指すという意味から来ているというものがあります。 また、別の説...
 す行
す行「スニーカー」という言葉は、英語の「sneakers」から来ています。 この名前の背景には、靴の特性が関わっています。 具体的には、スニーカーのゴム製の底のおかげで歩く際の足音が小さく、静かに歩けることから、「sneak...
 す行
す行「スナネズミ」という名前は、この動物が好んで生息する環境やその行動特性に関連しています。 具体的には、スナネズミはモンゴルや中国東北部などの気温の日変化が大きい半砂漠地帯に生息しています。 そして、砂を与えると、その中で...
 す行
す行「ストロンチウム」という名前は、英語の「strontium」から来ています。 この名前の由来は、ストロンチウムを含む鉱物が初めて発見された場所、スコットランドの地名「Strontian」に関連しています。 この地域で発見...
 す行
す行「ストロベリー」は英語の「strawberry」から取られた言葉です。 この「strawberry」は、「straw」と「berry」の二つの部分から成り立っています。 ここで、「straw」は「麦わら」を意味し、「be...
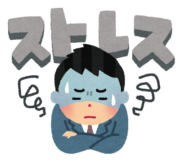 す行
す行「ストレス」という言葉は、英語の「stress」から来ており、もともとは「distress」という言葉に由来します。 この「distress」は、苦痛や苦悩を意味しています。ストレスという概念が現代のように広く知られるよ...
 す行
す行「ストール」という言葉は、もともとギリシャ語の「stole」という言葉やラテン語の「stola」という言葉に由来しています。 これらの語は、丈の長いゆったりとしたローブや外衣を意味していました。 古代ローマの時代には、特...
 す行
す行ステマとは、「ステルスマーケティング詐欺」の略称です。 この言葉は、英語の「stealth marketing」から来ています。 ここで、「stealth」は「隠密」や「こそこそしたやり方」という意味を持っており、この言...
 す行
す行「ステテコ」という言葉の由来は、明治時代の人気のあった「すててこ踊り」からきています。 この踊りは、三遊亭円遊という落語家が創始したもので、特徴的なのは半股引の姿で鼻をつまんで、その後捨てるという真似をしながら踊るという...
 す行
す行「すっぽかす」という言葉は、もともと「ほかす」という動詞があり、これは「放下す」から変化したもので、「捨てる」という意味を持っています。 この「ほかす」に、接頭語の「すっ」(または「素っ」として知られる形)が付加されるこ...
 す行
す行「酸っぱい」という言葉の起源は、名詞「酢」が形容詞化したものです。 これは、塩の味を表す時に使われる「しょっぱい」と似た経緯を持ちます。 つまり、酢のような独特の味を持つものを指すための言葉として始まりました。 この言葉...
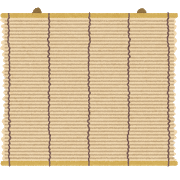 す行
す行「簾」、通称「すだれ」は、細く割った竹や葦を糸で編んで垂らしたもので、部屋の内外を隔てたり、日光を遮るために使用されます。 また、古くは牛車や輿にも取り付けられました。 この言葉「簾」は、「簀」という言葉と「垂れ」という...
 す行
す行「酢橘」、通称「すだち」はミカン科ユズ類の常緑低木で、独特の香気と酸味を持つ小型の果実を持っています。 この果実はその酸味が強いため、かつては酢として珍重されていました。 そのため、「酢」を意味する「酢」と、食用柑橘類の...
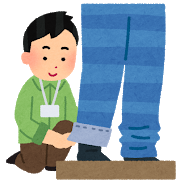 す行
す行「裾分け」という言葉は、もらいものの余分や利益の一部を分配する行為を指します。 この言葉の背景には、「裾」という言葉が重要な役割を果たしています。 「裾」は元々、衣服の下の縁、つまり衣服の最下部を指す言葉として使用されて...
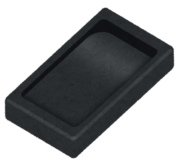 す行
す行「すずり」という言葉は、墨を磨る道具として使われる石や瓦で作られた具を指します。 この言葉の由来は「すみすり」という言葉から来ており、これは「墨磨」という意味です。 平安時代中期には、この「すずり」という言葉は一般的に使...
 す行
す行「雀鮨」は、元々は江鮒という魚を使って作られる料理で、この魚の腹の中にすし飯を詰めて形を作るものでした。 この料理の特徴的な部分は、すし飯を詰めた魚の腹が膨らんで見える点です。 この膨らんでいる姿が、雀のように見えるとさ...
 す行
す行「スズメ」や「雀」という名前は、鳥の特徴やその生態から名づけられたと考えられます。 名前の「スズ」部分は、スズメの鳴き声を表現したものであると考えられます。 平安時代には、スズメの鳴き声は「シウシウ」と表現されていました...
 す行
す行「すずふりばな」または「鈴振り花」は、トウダイグサ科の越年草の一つで、北半球に広く分布しており、特に日本の山地でよく見られます。 この植物は、傷をつけると白い乳液を出す特徴があり、これは有毒です。 この草の成長時、茎の頂...
 す行
す行「すずなり」あるいは「鈴生り」とは、果実や他のものがたくさん房状に集まっている様子を指す表現であり、具体的には、果実が神楽鈴のようにびっしりとむらがって生じるさまを指します。 この言葉の由来は、「神楽鈴」にあります。 神...
 す行
す行「スズナ」とは、春の七草の一つとして知られる青菜やカブの別称です。 この名前「スズナ」の由来については、その根の形状が理由とされます。 具体的には、スズナの根の形が、鈴の形に似ていることからこの名が付けられたと言われてい...
 す行
す行「スズシロ」という名称は、ダイコンの別称として知られており、春の七草の一つにも数えられます。 名前「スズシロ」には、2つの部分「スズ」と「シロ」が含まれています。 ここでの「スズ」は、「涼しい」という意味の「スズ」と関連...
 す行
す行「スズキ」という名前の由来には複数の説が存在します。 1つ目の説は、スズキの鱗が煤けたような色をしていることから、言葉「すすき(煤き)」が変化して「スズキ」になったというものです。 2つ目の説では、スズキの身の色がすすい...
 す行
す行「ススキ」という名前は、「スス」という部分が「ササ(笹)」から派生したものであるとされています。 この「ササ」という言葉は細かさや繊細さを意味する「ささ(細小)」から変化してきたとも考えられています。 そして、「キ」は草...