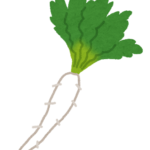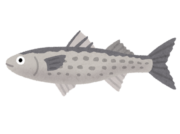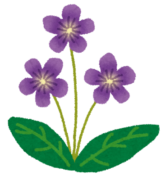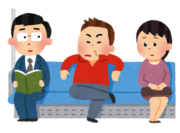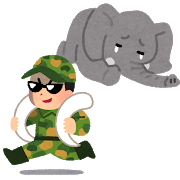「スズキ」という名前の由来には複数の説が存在します。
1つ目の説は、スズキの鱗が煤けたような色をしていることから、言葉「すすき(煤き)」が変化して「スズキ」になったというものです。
2つ目の説では、スズキの身の色がすすいだように白いことから、「すすぎ」が変化して「スズキ」になったと考えられています。
3つ目の説は、スズキがすずしく清らかな身を持っているため、その特徴から名付けられたというものです。
4つ目の説は、「スス」が「小さい」という意味を持つとし、スズキの尾が口の大きさに対して小さすぎることから、この名前が付けられたと考えられています。
5つ目の説は、スズキが勢いよく泳ぎ回る性質や、出世魚であることから「進む」を意味する「すすき(進き)」が名前の由来であるというものです。
6つ目の説では、スズキが磯でよく獲れることから、「イス(磯)」を重ねて「イスイス」とし、その後に長さを示す「キ(寸)」が付いて「イスイスキ」となり、これが「ススキ」に変化したとされています。
これらの諸説の中で、どれが最も正確なのかははっきりしていません。
スズキ【鱸】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「スズキ」の名前の由来に関するさまざまな説をカンタンにまとめます。
| 説の番号 | 説の内容 |
|---|---|
| 1 | スズキの鱗の色が煤けたようであり、「すすき(煤き)」が変化して「スズキ」になったという説。 |
| 2 | スズキの身の色がすすいだように白く、「すすぎ」が変化して「スズキ」になったという説。 |
| 3 | スズキがすずしく清らかな身を持つことから、その特徴を基に名付けられたという説。 |
| 4 | 「スス」が「小さい」という意味を持ち、スズキの尾が小さいことから名前がついたという説。 |
| 5 | スズキが勢いよく泳ぐ性質や出世魚であることから、進行を意味する「すすき(進き)」が名前の由来という説。 |
| 6 | スズキが磯でよく獲れることから、「イス」を重ねて「イスイス」とし、長さを示す「キ」が付き、「イスイスキ」→「ススキ」に変化したという説。 |