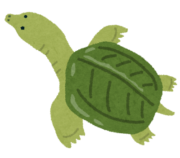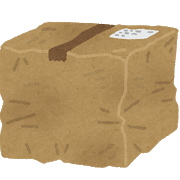「すずなり」あるいは「鈴生り」とは、果実や他のものがたくさん房状に集まっている様子を指す表現であり、具体的には、果実が神楽鈴のようにびっしりとむらがって生じるさまを指します。
この言葉の由来は、「神楽鈴」にあります。
神楽鈴は、里神楽を舞う際に使用される鈴で、15個または12個の鈴を結びつけて柄が付いているものを指します。
この神楽鈴が、びっしりと鈴がついている形状から、多くのものが密集している様子を指す言葉として「鈴なり」という表現が生まれ、時間とともに果実がたくさん房状になる様子や、ものや人が大勢集まっている様子を表現する際に使われるようになりました。
すずなり【鈴生り】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「すずなり」や「鈴生り」という表現に関する主要な情報や由来をカンタンにまとめます。
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 表現 | すずなり / 鈴生り |
| 意味 | 果実や他のものがたくさん房状に集まっている様子。神楽鈴のようにびっしりと密集して生じるさまを指す。 |
| 由来 | 神楽鈴(里神楽を舞う際に使用される鈴。15個または12個の鈴が柄に結びつけられているもの)。 |
| 使用場面 | 果実がたくさん房状になる様子や、ものや人が大勢集まっている様子を表現する際に使用される。 |