げんをかつぐ【験を担ぐ】の語源・由来
「験を担ぐ」という言葉は、ある物事に対して良い前兆か悪い前兆かを気にすることを指します。 この言葉の起源は、「縁起を担ぐ」という表現から変化してきたものだとされています。 「験」という字には、仏教や修験道などの宗教的な背...
 け行
け行「験を担ぐ」という言葉は、ある物事に対して良い前兆か悪い前兆かを気にすることを指します。 この言葉の起源は、「縁起を担ぐ」という表現から変化してきたものだとされています。 「験」という字には、仏教や修験道などの宗教的な背...
 け行
け行「現生」とは、現金を指す俗語です。 この言葉の起源は、江戸時代の上方の商人の間にあります。 彼ら商人は給料のことを「生」と呼んでいました。 なぜ給料を「生」と呼ぶようになったかというと、多くの場合、米や魚などの形で給与が...
 け行
け行「犬兎の争い」という言葉は、争っている二者が共に弱ってしまい、結果的に第三者に利益を持っていかれる状況を指すたとえです。 この言葉の由来は、古典文献「戦国策」の中の斉策に記された寓話からきています。 この寓話において、犬...
 け行
け行「ケンサキイカ」はヤリイカ科に属するイカの一種で、特にヤリイカに似ているものの、腕が太く、幅広い特徴を持っています。 このイカのひれは外套長の3分の2ほどを占めており、三角状に張り出しています。 主に食用として利用され、...
 け行
け行「拳骨」という言葉は、私たちが「にぎりこぶし」として知っているものを指しています。 この言葉の背後には、その形成の過程があります。 まず、元々の「げんこ」という言葉部分は、「こぶし」を意味する「拳」という文字と、接尾語と...
 け行
け行「外連味」は、俗受けを狙ったり、はったりやごまかしのような意味で使われる言葉です。 この言葉の背景を探ると、日本の伝統的な演劇の世界に起源を持ちます。 「けれん」という部分は、もともと江戸末期の歌舞伎の舞台で使われていた...
 け行
け行ゲルマニウムは非金属元素で、特に半導体としての性質を持っており、ダイオードやトランジスター、赤色のケイ光体の製造に使用されています。 この元素の名前「ゲルマニウム」には、発見の背景と特定の地域への敬意が込められています。...
 け行
け行「けりをつける」という表現は、「結末をつける」や「決着をつける」という意味で広く用いられています。 この表現の背後には、日本の伝統的な文学の影響が強く反映されています。 「けり」は、もともと物事の終わりや終結を意味する言...
 け行
け行「ゲテモノ」という言葉は、「下手物」と書かれ、二つの意味を持ちます。 一つ目は、高価で精巧な品物とは対照的な、日常的に用いられる大衆向けの質朴な品物を指します。 二つ目は、一般的に風変わりと捉えられるもの、つまり、通常と...
 け行
け行「けったい」という言葉は、関西地方を中心に使われる表現で、風変わりや奇妙、不思議といった意味を持っています。 この言葉の由来にはいくつかの説があります。 まず、占いの結果として現れる奇妙や不思議な事象を指す「卦体」という...
 け行
け行「けつぜい」または「血税」という言葉は、明治時代の1872年に公布された太政官告諭の中で使われたもので、もともとは身体を用いての奉仕、つまり兵役や徴兵を意味していました。 この「血」は、戦役で流される血を指しており、その...
 け行
け行「けちをつける」という言葉は、欠点や瑕疵を指摘する、または無理やり欠点や問題を見つけ出す行為を指します。 このフレーズの背後にある「けち」という言葉は、もともと「怪事(けじ)」という言葉から派生しています。 「怪事」は不...
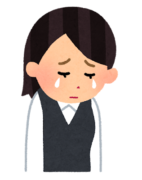 け行
け行「けちょんけちょん」という言葉は、何かを徹底的に批判したり、完全に打ち負かされたりした状態を指す言葉です。 この言葉の語源には複数の説が存在します。 一つの説としては、「けちょん」の部分が「掲焉(けちえん)」という言葉か...
 け行
け行ケチャップは、私たちがよく知る西洋料理の調味料で、通常はトマトを裏ごしし、調味した上で煮詰めた「トマトケチャップ」を指します。 しかし、このケチャップの起源はイギリスにあり、その名前の由来は、東南アジアや中国南部から輸入...
 け行
け行「ケチ」という言葉は、もともと「怪事(けじ)」という言葉から派生したものです。 「怪事」は、縁起の悪い事象や不吉な出来事を指す言葉でした。 しかし、時が経つにつれて、「怪事」が言いにくいものとして訛り、「けち」という形に...
 け行
け行「下駄を預ける」という言葉は、物事の処置や取り決めなどを他者に任せる、つまり相手に全てを託すという意味で使われます。 このフレーズの起源は、かつての日本の風習に基づいています。 来客が家を訪れる際、入室する前に玄関で下駄...
 け行
け行「下駄(げた)」は、特徴的な2枚の歯の付いた台木に、三つの穴を開けて鼻緒を取り付けたはきものを指します。 このはきものには、差歯や連歯(れんし)、さらには一本歯や三枚歯といったバリエーションがあります。 また、印刷業界で...
 け行
け行「げそ」という言葉は、イカの足を指す言葉として、特に鮨屋などで使われます。 この言葉の由来は、「下足(げそく)」という言葉から来ています。 もともと「下足」は、集会場などで靴や履物を脱ぎ取ったものを指す言葉でした。 これ...
 け行
け行化粧柳(けしょうやなぎ)は、ヤナギ科の落葉高木で、特に水辺に生息するものです。 この植物は、磔質の水辺に生え、時には20m以上の高さまで成長します。 春から初夏にかけて、新緑の葉と一緒に、長い花穂を垂れ下がらせるのが特徴...
 け行
け行「けじめ」という言葉は、現代日本語で「区別」や「道徳や慣習としての区別」、さらには「隔たり」や「境界」を指す際に使用されます。 しかし、その語源と由来にはいくつかの説が存在します。 もともと「けじめ」の言葉は、他との比較...
 け行
け行「毛嫌い」という言葉は、日常的に「何という理由もなく、ただ感情的に嫌うこと」として使われます。 この言葉の語源や由来には、いくつかの考え方が存在します。 まず、鳥や獣が他の生き物の毛の様子、つまりその質や色、模様などによ...
 け行
け行「怪我」という言葉は、もともと思いがけない過ちや、不測の結果を指す意味で使われていました。 この考えから、身体を思いがけず傷つける、つまり「負傷」するという意味に発展していきました。 語源としては確定的なものはありません...
 け行
け行「ケーキ」という言葉は、英語の「cake」からきています。 元々、「cake」という語は13世紀ごろに出現し、当初は平らに焼いた固いパンのようなものを指していました。 この言葉の起源は古ノルド語の「kaka」にさかのぼり...
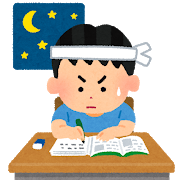 け行
け行「蛍雪の功」という言葉は、厳しい環境の中での勉強や努力の結果として得られる成果や功績を指します。 この表現の背景には、中国の歴史に残る二つの感動的な故事があります。 まず、『晋書』の「車胤伝」には、車胤という学者の話が記...
 け行
け行「謦咳に接する」という言葉は、「目上の方と直接会う」という意味で使われます。 この表現の背景には、実際にその人と会わないと、彼の咳払いの音すら聞けない、という意味が含まれています。 言葉の中の「謦咳」は、実際に咳払いを指...
 け行
け行「毛」という言葉は、動植物の体の一部や物の表面に生じる細くて糸状のものを指す言葉として使われています。 この言葉の語源には、いくつかの説が存在します。 一つの説によれば、「毛」は「生えてくるもの」を意味する「生(き・け)...
 け行
け行「気配」という言葉の背後には、日本語の歴史的な変遷と表記が関わっています。 もともと、この言葉は「けわい」として知られていました。 時間が経つにつれ、この言葉の歴史的仮名づかいは「けはひ」となりました。 仮名づかいとは、...
 け行
け行「景色」という言葉は、我々が自然の風景や見渡す光景を指して使う言葉ですが、その語源はもともとの意味とは少し異なっていました。 実は、「景色」の語源は漢語の「気色」にあります。 この「気色」を呉音で読むと「けしき」となりま...
 け行
け行「けしからん」という表現は、現代日本語で「無礼で許し難い」という意味で使われますが、その語源は古典的な日本語の形容詞とその変遷に起因しています。 この言葉の原形は、「異(怪)し」という形容詞で、これは「普通と異なっている...
 け行
け行「げろ」という言葉は、現在「自白すること」という意味で用いられることがありますが、その起源は泥棒の隠語にあります。 人が食事や飲み物を摂取した後、その内容物を吐き出す行為を指して「げろ」という言葉が使われることが一般的で...