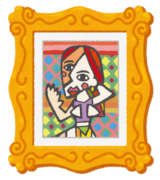「下駄(げた)」は、特徴的な2枚の歯の付いた台木に、三つの穴を開けて鼻緒を取り付けたはきものを指します。
このはきものには、差歯や連歯(れんし)、さらには一本歯や三枚歯といったバリエーションがあります。
また、印刷業界では「下駄」という言葉は、活版印刷の際に必要な活字がない時に、活字を裏返して組んだものを指し、これが印刷されると下駄の歯の形「〓」のマークとして現れます。
現代では、コンピューター組版においても伏せ字を示す記号として使われています。
「下駄」の名前の由来については、この言葉は戦国時代から使われているとされています。
その前は、はきもの全般を指す言葉として「アシダ」という言葉が使われていました。
この「アシダ」という言葉は、上履きも下履きも両方を含む意味合いを持っていました。
しかし、時代が進むにつれて、外で履く「下履き」だけを指す言葉として「下駄」という名前が使われるようになったのです。
「駄」という部分は、元々の「アシダ」という言葉の意味を保持しています。
げた【下駄】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「下駄」の定義、用途、名前の由来などの主要な情報をカンタンにまとめます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 物の定義 | 2枚の歯の付いた台木に、三つの穴を開けて鼻緒を取り付けたはきもの |
| バリエーション |
|
| 印刷業界での意味 | 活版印刷時に活字がない時に、活字を裏返して組んだもの。印刷されると下駄の歯の形「〓」のマークとして現れる |
| 現代的な使用 | コンピューター組版における伏せ字を示す記号として使用 |
| 名前の由来 | 戦国時代から使われ始め、その前は「アシダ」という言葉がはきもの全般を指していた。外で履く「下履き」の意味として使われるようになった |