ぐんかんまき【軍艦巻き】の語源・由来
「軍艦巻き」というすしは、すし飯を握ってその側面を海苔で巻き、上にウニやイクラなどの具材をトッピングしたものを指します。 この名前の由来は、軍艦巻きの形が横から見ると戦艦の形状に似ているためにそう名付けられたと言われてい...
 く行
く行「軍艦巻き」というすしは、すし飯を握ってその側面を海苔で巻き、上にウニやイクラなどの具材をトッピングしたものを指します。 この名前の由来は、軍艦巻きの形が横から見ると戦艦の形状に似ているためにそう名付けられたと言われてい...
 く行
く行「グロテスク」という言葉は、日本語において「怪奇的」や「奇怪」、さらには「無気味」などといった意味で使われますが、その語源には装飾様式の背景が隠されています。 この言葉はフランス語の「grotesque」から来ており、さ...
 く行
く行「グロッキー」という言葉は、元々英語の「groggy」から来ており、その形が少し変わって日本語に取り入れられました。 「groggy」という言葉の由来は、水割りのラム酒「grog」という言葉に関連しています。 グロッグ酒...
 く行
く行「玄人跣」は、素人がその技芸や技術で玄人、すなわちプロフェッショナルや熟練者さえ驚かせるほどに優れている状態を表現する言葉です。 この言葉の背景には、素人の高い技術や実力に驚いた玄人が、あたかも裸足(はだし)で逃げ出すか...
 く行
く行「玄人」は、技芸や特定の分野において熟達した人や専門家を指す言葉として使われます。 また、特定の文脈では芸妓や娼妓の称としても使用されます。 この言葉の起源は、江戸時代に「素人(しろうと)」という言葉の対義語として生まれ...
 く行
く行「黒」という言葉は、墨のような色を指す色の名として、古くから日本語に存在しています。 具体的な語源については明確ではありませんが、光のない状態、すなわち闇や暗さを指す言葉として「黒」が使われることから、この言葉が「暗い」...
 く行
く行「クレヨン」という言葉は、我々にとって子供時代の楽しい思い出やアートの世界と深く結びついているものです。 この名前は、フランス語「crayon」から来ており、実際には「鉛筆」を意味します。 さらに、この「crayon」は...
 く行
く行「クレマチス」とは、キンポウゲ科に属する観賞用の蔓性の多年草で、その美しい大きな車輪型の花が特徴的です。 この花には多くの園芸品種があり、特に初夏から夏にかけて、白や紫、桃色などの鮮やかな色彩で花を咲かせます。 そのため...
 く行
く行「クレパス」という名前の画材は、多くの人にとっておなじみのものでしょう。 これは、1926年に株式会社サクラクレパスが開発し、その後多くの人々に広く愛用されるようになった画材です。 「クレパス」という名前の由来は、実は非...
 く行
く行「紅」は、日本語で「くれない」と読み、色や染料、また特定の香りを指す言葉として使用されます。 「くれない」は、「ベニバナ」という植物の別称としても知られています。 ベニバナは、その名の通り赤い花を持つ植物で、古くから美し...
 く行
く行クレープは、多くの人にとって薄く焼かれた甘いデザートや軽食としてのイメージが強いでしょう。 しかし、この言葉の起源や背景を知ると、クレープへの視点が少し変わるかもしれません。 クレープの語源はフランス語の「crepe」と...
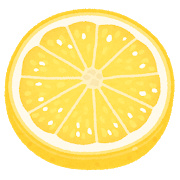 く行
く行グレープフルーツは、ミカン科ザボン類に属する大型の柑橘類で、多くの人々にとってはジューシーで爽やかな味わいの果実として親しまれています。 この名前を聞くと、ぶどうと何か関係があるのではないかと思われるかもしれませんが、実...
 く行
く行グルメという言葉は、多くの日本人にとって美食家やおいしい食べ物を指す言葉として親しみがあります。 この言葉の背後には、フランス語からの影響が深く、実際、グルメの語源はフランス語の「gourmet」という言葉から来ています...
 く行
く行「くるま」という言葉は、我々が普段よく耳にする車を指す名詞ですが、その背景には回転という動きの概念が深く結びついています。 その名前は、車輪が回転することで移動する特性から来ています。 言葉の成り立ちを詳しく見ると、「く...
 く行
く行「くるぶし」、すなわち踝は、足首の部分に位置し、脛とつながる部分の内外両側の突起を指します。 具体的には、内側の突起は脛骨の末端であり「内果」と呼ばれ、外側の突起は腓骨の末端で「外果」と呼ばれます。 この「くるぶし」とい...
 く行
く行「狂う」という言葉は、多様な意味を持ちます。 それは正常な心や考え方を失うこと、神霊や物の怪が取り憑くこと、舞や芸事での激しい動きや、それに熱中するさま、または通常の調子や状態を逸脱することなど、さまざまな状況や行動を示...
 く行
く行「くり」または「栗」は、ブナ科の落葉高木で、果実は食用や菓子作りに用いられるだけでなく、木材も耐久性や耐湿性が強いため、さまざまな用途で利用されます。 この名前の由来に関しては、いくつかの説が存在します。 一つの説は、果...
 く行
く行クラリネットは、円筒形の木管楽器で、1枚のリードを使用して音を出します。 この楽器は1700年頃にドイツで、J.C.デンナーによってシャリュモーという楽器の欠点を改良して創製されました。 シャリュモーはクラリネットの前身...
 く行
く行クラリセージは、シソ科アキギリ属に属する2年草で、特にその花や葉から抽出される精油が知られています。 また、この植物は「オニサルビア」とも呼ばれています。 この名前「クラリセージ」の背後には、英語の「clary sage...
 く行
く行「クラシック」という言葉は、多くの人々にとって古典的な名作や西洋の古典音楽、さらには古典的で格式のある様子を指す言葉として認識されています。 この言葉の背景には興味深い由来があります。 「クラシック」は、英語の「clas...
 く行
く行「グラジオラス」は、アヤメ科の球根植物で、剣のような形をした葉と、長い花序軸につく多彩な色の花で知られています。 この植物の名前は、英語の「gladiolus」に由来しています。 この「gladiolus」という名前の根...
 く行
く行「鞍替え」という言葉は、現在では主に職や立場などを変えることを意味しますが、その起源や過去の用法を知ると、さらに興味深い言葉となります。 元々の「鞍替え」は、文字通り馬の鞍を変える行為や、別の馬に乗り換えることを指してい...
 く行
く行クミンは多くの料理や製品で使用される香辛料の一種で、セリ科の一年草の種子から作られます。 この香辛料の名前の起源には、長い歴史と多くの言語が絡んでいます。 「クミン」という名前は英語の「cumin」から来ています。 しか...
 く行
く行「隈取り(くまどり)」という言葉は、美術や舞台などで使われる技法を表す名詞ですが、その語源は「隈」にあります。 「隈」とは、もともと「奥まって隠れた場所」や「影のあるところ」を意味していました。 この概念が拡大して、「隈...
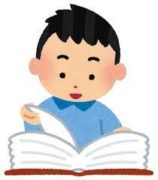 く行
く行「首っ引き(くびっぴき)」という表現は、主に「ある物を絶えず参照すること」や「書物を手に参照しながら作業をすること」を意味しますが、その語源は「クビヒキ」という子供の遊びに由来します。 この遊びでは、向かい合った二人が輪...
 く行
く行「首っ丈(くびったけ)」という言葉は、現代では「異性に強く引かれているさま」や「何かに夢中である状態」を指すようになっていますが、その語源は「首丈(くびだけ)」という表現に遡ります。 この「首丈」は、元々「足元から首まで...
 く行
く行「苦肉の策」という表現は、一般に「考えあぐねた末の策」や「苦し紛れの手段」といった意味で用いられます。 この言葉の語源は、元々「敵を欺くために自分自身や味方を苦しめる」といった状況を指していました。 人々は普段、自分や味...
 く行
く行「口説く」という言葉は、複数の意味で用いられますが、その語源と由来は「くどくど」という言葉に関連しています。 具体的には、「くどくど」という形で繰り返し何かを言う、またはしきりに意中を訴える様子を表現しています。 この言...
 く行
く行「グッドバイ」という言葉は、英語の「good-bye」から来ていますが、そのルーツはさらに古く、別れの挨拶として用いられた「God be with you」または「God be with ye」にさかのぼります。 このフ...
 く行
く行「ぐっすり」という言葉は、もともと「完全に」や「すっかり」といった意味で使われる擬態語です。 この言葉が江戸時代にはすでに使われていたことが、古い文献にも見られます。 例えば、「黄表紙・即席耳学問」という江戸時代の文献に...