インフルエンザの語源・由来
インフルエンザという名前は、イタリア語の「influenza」に由来しています。 このイタリア語の単語は「影響」という意味を持っており、16世紀のイタリアでこの病気に名前がつけられた背景があります。 当時、感染症が伝染性...
 い行
い行インフルエンザという名前は、イタリア語の「influenza」に由来しています。 このイタリア語の単語は「影響」という意味を持っており、16世紀のイタリアでこの病気に名前がつけられた背景があります。 当時、感染症が伝染性...
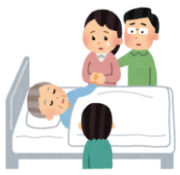 い行
い行「引導を渡す」という表現は、仏教の儀式である「引導」から派生した言葉です。 元々、この儀式は死者の魂を浄土へ導く目的で行われ、僧侶が棺の前で法語を唱えることで、死者が悟りに至るよう導いていました。 この儀式が、死者がこの...
 い行
い行「インディーズ」という言葉は、主に映画や音楽などのクリエイティブな産業において用いられます。 この語は、英語の「independent(独立した)」から派生したもので、大手の制作会社やレコード会社に属していない、小規模な...
 い行
い行「インタビュー」という言葉は、英語の「interview」から来ており、日本語で広く使われています。 この言葉は二つの部分に分解できます。 「インター(inter)」という接頭語は「中・間・相互・以内」などの意味を持ちま...
 い行
い行「インスタント」という言葉は、英語の「instant」から来ています。 この「instant」という語は、フランス語の「stare」に由来し、その意味は「立つ」という行動を示しています。 具体的には、「stant」という...
 い行
い行「寅」という字は、十二支の第3番目に位置するものとして一般によく知られています。 また、「寅」は方角としては東北東、時間としては今の午前4時前後の2時間、さらには陰暦1月の異称としても用いられます。 この字の本来の読みは...
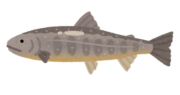 い行
い行「岩魚」(いわな)という名前は、この魚が主に渓谷の岩陰や岩のある淵に生息する特性から来ています。 語尾の「ナ」は他の魚の名前、例えば「フナ」といった場合にも見られるように、魚を意味する古語です。 そのため、「岩魚」とは文...
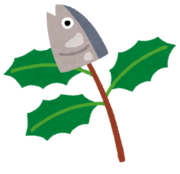 い行
い行「鰯の頭も信心から」ということわざは、日本の民間信仰と風習に由来しています。 特に、節分の夜に鰯の頭を柊の枝に刺して門口に置くという習慣が関係しています。 この風習では、鰯の頭の臭気が悪霊や悪鬼を追い払うと信じられていま...
 い行
い行「祝い」の語源は、動詞「祝う」の名詞形であり、この「祝う」は古くは「いはふ」と言われていました。 この古い表現「いはふ」は、清浄を保ち、吉事を祈るとともに、特定の禁忌を守るという、厳かな態度や行為を指していました。 ここ...
 い行
い行「色男」の語源は歌舞伎の世界から来ています。 元々は歌舞伎で濡れ場を演じる役者、すなわち濡事師を指していたのです。 濡事師は、男女の愛情を描く場面で重要な役割を果たし、そのために顔を白く塗って美男子に見せる演技を行ってい...
 い行
い行「色」は非常に多面的な意味を持つ日本語の単語で、視覚的な色彩から社会的な意味、さらには愛情や情事まで、多くの異なる概念を包括しています。 その語源は、もともと血縁関係を意味する「いろ」から派生しています。 この「いろ」は...
 い行
い行「入れ墨」と「刺青」は、肌に針や刃状の道具で模様や文字を彫り、色料を注入して作るアートフォームを指します。 これは先史時代から行われ、日本でも近世に特に流行しました。 言葉の由来や背景にはいくつかの面白いポイントがありま...
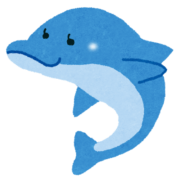 い行
い行「イルカ」、または漢字で書くと「海豚」は、ハクジラ類の小型種を指す日本語の名称です。 この名前の語源や由来については、さまざまな説が存在します。 一つの説は、イルカがしばしば群れを成して遊泳し、さらに船舶に並行して走るこ...
 い行
い行「イランイラン」という名前は、エキゾチックで甘い香りが特徴の植物で、アロマテラピーや香水に使われる精油を提供します。 この植物は、レユニオン島、コモール、インドネシアなどで自生しており、その名前の由来は実は言語的にも地理...
 い行
い行「嫌み」または「厭み」は、主に相手に不快感を与えるような言葉や態度を指します。 この言葉の語源は、日本語の動詞「否む(いやむ)」から派生しています。 「否む」は「いやがる」や「きらう」といった意味で使われる動詞です。 こ...
 い行
い行「イモリ」は日本でよく見られる小さな両生類で、アカハライモリをはじめとして、世界に約110種類が存在するとされています。 日本語での呼び名「井守(いもり)」は、この生き物がよく水のある場所、特に池や井戸などに生息する特性...
 い行
い行「妹(いもうと)」という言葉は、日本語において一般に年下の女性のきょうだいを指すものとして広く用いられています。 しかし、その語源は多少複雑です。 もともとこの言葉は、「いもひと(妹人)」が転じて「いもうと」となりました...
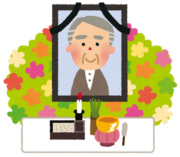 い行
い行「諱(いみな)」という言葉は、もともと死後に使う生前の実名を指していましたが、後には貴人の実名を敬う意味や、死後に尊んで付けられた称号、すなわち諡(おくりな)という意味でも用いられるようになりました。 この言葉の語源は「...
 い行
い行「忌々しい」(いまいましい)という言葉は、日本語において様々な意味で使われますが、その根底にあるのは「忌む(いむ)」という動詞です。 この「忌む」は、何かを避ける、または敬うべきものと考えるという意味があります。 特に、...
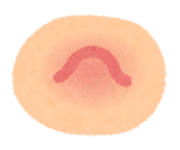 い行
い行「疣」の語源は、古語で飯粒を意味する「いひぼ」に由来します。 この古語が時代と共に略され、「いぼ」となりました。 この飯粒に喩える表現は、いぼが皮膚にできる小さな突起、すなわち米粒のような形状をしていることに基づいていま...
 い行
い行「いびる」という言葉の語源は、もともと「いぶす」という言葉から派生したものです。 この「いぶす」は煙を発生させる行為を指していました。 特に、煙を使って穴倉に隠れている狐や狸などを外に追い出す、つまり燻し出す行為を指して...
 い行
い行「いびき」または「鼾」は、人が睡眠中に上気道が狭くなることで発生する呼吸に伴う雑音を指します。 この語の語源にはいくつかの説がありますが、一つは平安時代の漢和字書『新撰字鏡』に記載されている「息吹」という語に関連するもの...
 い行
い行「イノンド」は、主に西アジアや地中海地方で見られるセリ科の草です。 この植物は料理に幅広く使われ、特にその種子は強い芳香があります。 語源については、スペイン語の「eneldo」が転訛して「イノンド」になったとされていま...
 い行
い行「いのち」、すなわち命の語源にはいくつかの異なる解釈や説があります。 一つの説では、「いのち」の「い」は「いく(生)」や「いき(息)」と共通であり、これらの語は生命や生きること、呼吸といった概念に関連しています。 一方で...
 い行
い行「猪(いのしし)」の語源には二つの主要な成分があります。 一つ目は「い」という音素で、これは猪の鳴き声を模倣した擬声語であるとされています。 猪は特定の鳴き声でコミュニケーションをとる動物であり、その鳴き声から名前がつけ...
 い行
い行「稲」の語源や由来については、複数の説が存在しています。 一つ目の説として、「いひね(飯根・飯米)」からきたとされています。 この説では、稲が食料として極めて重要な存在であることが強調されています。 日本での主食はお米で...
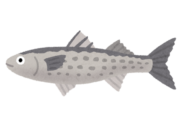 い行
い行「イナ」または「鯔」は、ボラの幼魚を指す言葉で、その語源や由来には複数の説が存在します。 一つ目の説は、稲の茎が腐ったものがこの魚に変わるという俗伝に基づいています。 この説によれば、”稲魚” と...
 い行
い行「糸を引く」という表現は、元々は操り人形を糸で動かす様子から来ています。 この概念を広げて、人や事を裏で操る、あるいは影響を持続させる意味で用いられるようになりました。 この表現にはいくつかの側面があります。 一つ目は、...
 い行
い行「糸柳(イトヤナギ)」は、シダレヤナギの別称であり、ヤナギ科の落葉高木です。 この木の特徴はその細長く垂れ下がる枝であり、この形状がまるで糸のように見えることから「糸柳」と呼ばれています。 糸柳は原産地が中北で、特に湿地...
 い行
い行「営む(いとなむ)」は、元々は「忙しく仕事をする」や「せっせと務める」といった意味で使われていました。 この言葉の語源には、意味で言えば「休むひまがない」や「忙しい」というニュアンスを持つ「暇無(いとな)し」が基になって...