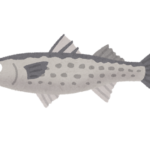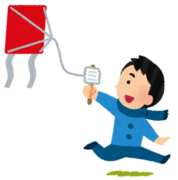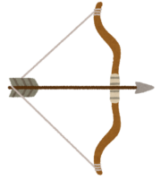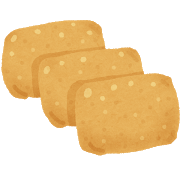「稲」の語源や由来については、複数の説が存在しています。
一つ目の説として、「いひね(飯根・飯米)」からきたとされています。
この説では、稲が食料として極めて重要な存在であることが強調されています。
日本での主食はお米であり、その米を提供する主要な作物が稲であるため、この説は非常に直感的です。
二つ目の説は、「いのちね(命根)」や「いきね(生根・息根)」から派生したというものです。
この説では、稲が単なる食料以上に、生命そのものと深く結びついているという側面を強調しています。
つまり、稲は人々の命を維持する非常に基本的な要素とされています。
三つ目の説は、かつて人々が稲の藁を敷いて寝ていた習慣や、その忌み言葉である「寝ね(いね)」と関連して、「いぬ(寝ぬ)」の連用形が名詞化したというものです。
この説は、稲が単なる食料を提供するだけでなく、生活全般に深く組み込まれていたという事実を示しています。
以上のように、「稲」の語源や由来は多角的であり、その多様な解釈が日本人と稲との深い関係性を表しています。
それぞれの説は、稲が日本文化や生活において果たしてきた多様な役割と深いつながりを象徴していると言えるでしょう。
イネ【稲】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「稲」の語源や由来、日本人と稲との深い関係性をカンタンにまとめます。
| 語源・由来説 | 強調する側面 | 影響・意義 |
|---|---|---|
| いひね(飯根・飯米) | 食料としての重要性 | 日本での主食はお米であり、その供給源が稲。直感的な解釈。 |
| いのちね(命根)/いきね(生根・息根) | 生命との深い結びつき | 稲は食料以上に人々の命を維持する基本的な要素。 |
| いぬ(寝ぬ)の連用形 | 生活全般との関連 | 稲の藁が寝床としても使われ、生活に深く組み込まれていた。 |