らくがん【落雁】の語源・由来
【意味】 米・麦・大豆などの粉に砂糖と水飴を加え型に入れて固めた干菓子のこと。 【語源・由来】 中国の唐菓子である軟落甘(なんらくかん)を略したものといわれている。また、古くは、黒ゴマを加えたといわれており、白い菓子に散...
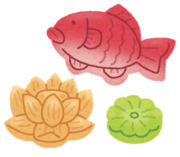 ら行
ら行【意味】 米・麦・大豆などの粉に砂糖と水飴を加え型に入れて固めた干菓子のこと。 【語源・由来】 中国の唐菓子である軟落甘(なんらくかん)を略したものといわれている。また、古くは、黒ゴマを加えたといわれており、白い菓子に散...
 よ行
よ行【意味】 餡と羊羹をまぜ、固めた菓子。 【語源・由来】 元は中国の食べ物で、羊肉の羹(あつもの)のことで、羊の肉を入れたお吸い物を意味する。禅宗を通して日本に伝わったもの。当初は、羊の肝に似せた、小豆と砂糖で作る蒸し餅で...
 ゆ行
ゆ行【意味】 煮立てた豆乳の表面にできた薄いたんぱく質の膜をすくい上げたもの。 【語源・由来】 湯葉を「豆腐皮(ゆば)」と当て字で書くことがある。もとは「うば」。干し湯葉のしわがある黄色い様子が、老婆の顔に見立て「姥(うば)...
 や行
や行【意味】 牛肉などを、醤油・砂糖・生姜で甘辛く煮たもの。多く、缶詰用。 【語源・由来】 明治時代に作られるようになったもの。「大和」は日本国の異称。「日本風の味付け」の意で用いられたものと考えられている。また、缶詰は、日...
 や行
や行【意味】 開いた泥鰌とささがきごぼうを鍋で煮込み、卵でとじた料理。 【語源・由来】 江戸時代、日本橋横山町の柳川という屋号の店で創案されたから。また、使われていた土鍋が、柳川(福岡県)産の土鍋だったからともいわれている。
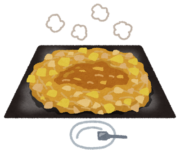 も行
も行【意味】 ゆるくといた小麦粉に種々の具をまぜ、焼きながら食べるもの。 【語源・由来】 江戸時代末期から明治にかけて、子供たちが出汁で溶いた生地で鉄板に文字を書いて覚えながら食べていたことから、「文字焼き」が転じたものとい...
 も行
も行【意味】 もち米の粉をこねて焼いた薄い皮を二枚重ね合わせて、間に餡をつめた和菓子。 【語源・由来】 江戸吉原の菓子屋「竹村伊勢」が、満月をかたどった「最中の月(もなかのつき)」という煎餅のようなものを作り、それが省略され...
 も行
も行【意味】 食料としての鶏・豚・牛などの内臓。 【語源・由来】 「臓物」の上を略したもの。肝臓・腎臓・心臓・胃・腸などのほか、舌なども含んでいう。
 も行
も行【意味】 もち米を蒸し、粘り気が出るまで臼でついたもの。 【語源・由来】 「餅飯」の略である。「もちい」がさらに略されたものという。「もち」については「保つ」「持つ」の意のほか、望月(もちづき)の「望(もち)」、もち(糯...
 め行
め行【意味】 竹串やわらを鰯などの目に刺し通し、数尾ずつ連ねて干したもの。 【語源・由来】 魚の目を刺し通すことから。
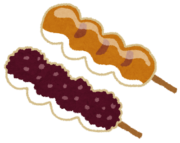 み行
み行【意味】 米の粉で作った団子を竹串に刺し、醤油餡を絡めたもの。 【語源・由来】 京都市左京区下鴨の下鴨神社が行う「御手洗会(みたらしえ)」とされる。みたらし川に足をつけて無病息災を祈る神事の際、境内で売られたのが始まりと...
 ま行
ま行【意味】 小麦粉をねった皮で餡を包み、蒸した菓子。 【語源・由来】 起源は中国にあり、諸葛孔明(しょかつこうめい)が南征した際、川の神に人身御供として人の頭を捧げれば鎮まるという風習を改めるため、羊や豚の肉を小麦粉で作っ...
 ま行
ま行【意味】 昆布・するめ・人参などに数の子を加え、みりんを合わせて醤油に漬けた食品。 【語源・由来】 北海道南西部の松前地方は昆布の名産地であったことから、昆布のことを俗に松前と呼び、昆布を使った料理には「松前」がつけられ...
 ほ行
ほ行【意味】 猪の肉を使った味噌仕立ての鍋。猪鍋。(ししなべ)。 【語源・由来】 いのししの肉を煮こむと脂身がちぢれて、牡丹の花のようになるという説、また、いのししの肉を大皿に並べると、鮮やかな肉のいろどりが、牡丹の花のよう...
 ふ行
ふ行【意味】 柔らかく煮た大根や蕪に味噌をかけて食べる料理。 【語源・由来】 名前の由来には諸説ある。「風呂吹き」とは蒸し風呂で垢をこすり取る役目の者のことで、その風呂吹きが息を吹きかけながら垢をこすり取るさまが、熱い大根に...
 ふ行
ふ行【意味】 大根・茄子・鉈豆・蓮根などの野菜を細かく刻み、みりん醤油に漬け込んだ漬物。 【語源・由来】 福神漬けは、酒悦の主人 野田清右衛門が江戸末期から明治の始めにかけて考案し商品化したもの。店が上野にあったことから不忍...
 ひ行
ひ行【意味】 冷やした豆腐を四角に切り、醤油と湯葉で食べる料理。 【語源・由来】 冷奴の「奴(やっこ)」は、大名行列の先頭で槍や挟み箱をもつ役の「槍持奴(やりもちやっこ)」のこと。奴が着ていた半纏には、「釘抜紋」と呼ばれる四...
 ひ行
ひ行【意味】 鰻のかば焼きを飯櫃に入れたご飯にのせたもの。 【語源・由来】 細かく刻んだうなぎの蒲焼をお櫃のご飯にまぶすことから。「ひつ」は「櫃」。「まぶし」は「まぶす」の連用形の名詞化。名古屋の名物で、最後はお茶漬けにする...
 は行
は行【意味】 魚のすり身に山芋・でんぷんを加えて蒸したもの。 【語源・由来】 魚のすり身をお椀のふたで半円形にかたどって作られたことから「はんぺん」と言われるようになったという説、蒲鉾(現在で言う竹輪)を縦半分に割って板につ...
 に行
に行「煮凝り」は、特定の魚や肉の煮汁に含まれるゼラチン質が冷えることで固まる性質を基にした料理を指します。 この料理名の由来は、「凝る」という動詞からきています。 「凝る」とは、水分を多く含むものが冷やされることによって固ま...
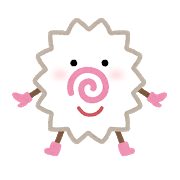 な行
な行「鳴門巻き」とは、日本の伝統的な食品で、かまぼこの一種です。 特徴的なのは、その見た目にあります。 赤く染められた魚肉のすり身を、白いすり身で渦状に巻いて蒸したもので、断面を見ると美しい渦巻き模様が現れます。 この渦巻き...
 な行
な行「奈良漬け」という名前の背景には、奈良という地域の歴史的な背景が関係しています。 奈良は古代から酒の名産地として知られていました。 そのため、この地域では質の良い酒粕が豊富に生産されていました。 7世紀頃から、酒粕を使用...
 な行
な行納豆は、発酵させた大豆から作られる日本の伝統的な食品です。 この名前の由来は、かつて寺院の出納事務を担当する「納所(なっしょ)」という場所で製造されていたことにちなんでいます。 納豆の中でも、蒸した大豆に麹菌を加え、その...
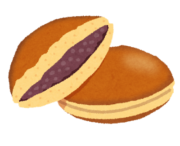 と行
と行「どら焼き」とは、小麦粉、卵、砂糖を混ぜ合わせて丸く焼き上げた二枚の皮の間に餡を挟んだ和菓子のことを指します。 この名前の由来は、どら焼きの形状が銅製の打楽器「銅鑼」に似ていることからきています。 実際、漢字で「どら焼き...
 と行
と行「ところてん」、別名「心太」は、天草を煮溶かして作り、冷やし固めた後に線状に押し出して食べる日本の伝統的な食品です。 この名称の由来は、もともと天草や、天草から作られた食品を「心太(こころぶと)」と呼んでいたことから始ま...
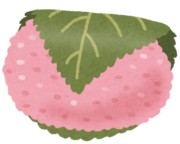 と行
と行道明寺とは、関西地方での桜餅の呼び名です。 この名前の由来は、「道明寺粉」というものに関連しています。 道明寺粉とは、もち米を蒸してから乾燥させ、その後粗挽きにしたものを指します。 この道明寺粉を「道明寺糒」とも称し、糒...
 て行
て行「天麩羅」という言葉は、魚、貝、野菜などに小麦粉と卵、水を混ぜた衣をつけて油で揚げた料理を指します。 この料理名の由来については、複数の説が存在します。 一つの説は、ポルトガル語の「tempero」という言葉から来ている...
 て行
て行「田麩」は、蒸して柔らかくした魚の身をほぐし、みりんや醤油で下味をつけて煎った料理を指します。 この料理名の語源としては、元々「田夫(でんぶ)」という言葉が使われていました。 「田夫」は、農夫や田舎者を意味する言葉でした...
 て行
て行「てっちり」は、河豚を主材料とするちり鍋のことを指します。 この名前の由来は、「鉄のちり鍋」からきています。 具体的には、この「鉄」という部分は、ふぐの毒に触れると非常に危険で、死に至ることがあるため、ふぐを「鉄砲」と例...
 つ行
つ行「つくね」という言葉は、鶏肉や魚肉に卵や片栗粉を加えて、手でたたき、よくこねて丸めた食品を指します。 この名称の由来は、手で混ぜてまとめるという意味の動詞「つくねる(捏ねる)」からきています。 具体的には、「つくねる」の...