けいえん【敬遠】の語源・由来
「敬遠」という言葉は、現在では「うわべでは敬意を示しながらも、実際には避けて接する」という意味で使われています。 この言葉の由来は、中国の古典『論語』にさかのぼります。 『論語』には「敬鬼神而遠之」という表現があります。...
 け行
け行「敬遠」という言葉は、現在では「うわべでは敬意を示しながらも、実際には避けて接する」という意味で使われています。 この言葉の由来は、中国の古典『論語』にさかのぼります。 『論語』には「敬鬼神而遠之」という表現があります。...
 わ行
わ行【意味】 演劇・映画などで、主役を助けて副次的な役割をつとめる役。転じて、一般に表面に出ない補佐役。 【語源・由来】 「脇」は側面・横・そばなどの意を表すが、転じて、中心となるものの次の位置するものをさす。能楽では、主役...
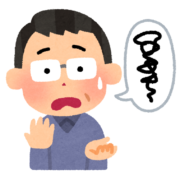 ろ行
ろ行【意味】 舌がうまく動かず、発音が不明瞭であること。 【語源・由来】 「呂律」は雅楽の旋法である「呂旋」と「律旋」を表す「呂律(りょりつ)」が変化したもの。雅楽を合奉する際にうまく合わないことを「呂律が回らない」といった...
 め行
め行【意味】 物事の強弱。調子。 【語源・由来】 「減り張り」と書いて、ゆるむことと張ることの意。もとは、邦楽用語の「減り上り」から。低い音を「減り(めり)」、高い音を「上り」と呼んでいた。音の抑揚や歌舞伎などの演出の強弱を...
 み行
み行【意味】 ことさらに自分を誇示するような態度をとる。 【語源・由来】 「見得」は「見え」で、見えること。つまり外観をいう。歌舞伎で、役者が感情の高まりを示すために、一瞬動きを止めて目立った姿勢や表情をすること。その所作を...
 ま行
ま行【意味】 ゴマをかけた俵形の握り飯とおかずとを詰め合わせた弁当。 【語源・由来】 芝居で舞台の幕が下り、次の場面で幕が上がるまでのことを「幕の内」や「幕間(まくあい)」と言い、その間に食べる弁当という意味で名付けられた。
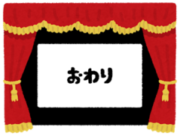 ま行
ま行【意味】 物事の終わり。 【語源・由来】 芝居で一幕が終わって幕が下りること。これが転じて物事の終わりを指すようになった。同類の言葉で、物事を終わりにすることを「幕引き」というが、これは幕を引いて芝居を終えることからいう...
 ひ行
ひ行【意味】 他の者の存在が薄くなるほど、ある一人が目立った活躍をすること。また、一人だけが思うままに振る舞うこと。 【語源・由来】 ただ一人の役者が舞台で演技をすること。独演。一人芝居。他にも共演者がいるのに一人だけ際立っ...
 ひ行
ひ行【意味】 自分の手腕を披露する晴れの舞台。 【語源・由来】 かつて、檜(ひのき)の板で床を張ったのは、大劇場の舞台のみだった。そこから、格の高い舞台で大芝居に出演することを「檜舞台を踏む」と呼ぶようになり、自分の力量を広...
 は行
は行【意味】 他人の言動に非難やからかいの言葉をかける。 【語源・由来】 半畳は、江戸時代の芝居小屋で敷く畳半分ほどのござのこと。現在の座席指定料のようなもので、観客が入場料として半畳を買い、これを敷いて見物していた。役者が...
 は行
は行【意味】 はかりごとを言葉や行為に出さず、腹の中で企むこと。また、直接言葉で指示するのではなく度胸や迫力で物事を処理すること。また、そういうやり方。 【語源・由来】 芝居で、役者がせりふや動作に出さず、感情を内面的におさ...
 は行
は行【意味】 人生で最も華々しい状況。また、人生の最後の花。 【語源・由来】 歌舞伎の劇場で、舞台の下手から観客席を縦に貫く通路のこと。役者が登場したり、退出したりするときに用いる。六方をふんだり見得を切ったりと、見せ場があ...
 は行
は行【意味】 色合いや性格が華美なこと。人目を引くこと。 【語源・由来】 「映え手(はえて)の変化した語とする説や三味線で、従来の演奏方法を破った新様式の曲風を「破手(はで)」といい、非常ににぎやかなもので、それが転じたとい...
 は行
は行【意味】 隠していた正体や、悪事がバレることのたとえ。 【語源・由来】 「馬脚」は、芝居で馬の脚を演じる役者のこと。馬の脚を演じる役者が芝居中にうっかり姿を現すことから、隠しておいたことが明らかになることを言うようになっ...
 の行
の行「のべつ幕なし」という言葉は、芝居の舞台の文化からきています。 この表現は、芝居で途中で幕を引くことなく、絶えず演技を続ける様子を指しています。 「のべつ」とは「延べつ」とも書かれ、絶えずやひっきりなしにという意味を持っ...
 ぬ行
ぬ行「濡れ場」という言葉は、現代では映画やドラマなどのエンターテインメントにおけるラブシーンや情事の場面を指す言葉として一般的に認識されています。 この言葉の起源は、日本の伝統的な舞台芸術である歌舞伎に遡ります。 歌舞伎にお...
 に行
に行「二枚目」という言葉は、美男子や色男を指す際に使われる言葉として知られています。 この表現の起源は、上方歌舞伎の伝統に根ざしています。 上方歌舞伎の劇場では、公演の際に八枚の看板を劇場の前に掲示していました。 これらの看...
 に行
に行「二の舞」という言葉は、雅楽の中の特定の舞、特に「安摩(あま)」という舞に由来しています。 舞楽の中で、「安摩」というのは蔵面をつけて舞われる一つの雅楽です。 この舞には答舞、つまり返しの舞が存在しています。 この答舞が...
 に行
に行「二の句が継げない」という言葉は、雅楽の朗詠の特定の部分、特に詠むのが難しい部分に由来します。 雅楽の朗詠では、詩句を三段階に分けて詠むことが伝統となっています。 その中の「二の句」は、この三段階の中の二段目の句を指しま...
 な行
な行「鳴り物入り」という表現は、歌舞伎という日本の伝統的な舞台芸能に由来します。 歌舞伎の舞台では、太鼓や笛などの楽器が使用されることが多く、これらの楽器を総称して「鳴り物」と呼びます。 特に、三味線を除く鉦、太鼓、笛の組み...
 な行
な行「並び大名」という言葉の背景は、日本の伝統的な演劇である歌舞伎に由来しています。 歌舞伎には様々な役どころが存在しますが、中には大名の姿で舞台に並ぶだけの役があります。 この役は、主要な登場人物やストーリーに直接関与する...
 な行
な行「奈落」という言葉は、物事のどん底や最終のところを意味します。 この言葉の起源は、梵語の「naraka(ナラカ)」にあります。 この梵語は地獄を意味しており、それを漢字で音写した際に「奈落迦」と表現されました。 時が経過...
 と行
と行「どんでん返し」とは、立場や情勢が急激に変わることを指します。 この言葉の起源は、歌舞伎の舞台に遡ります。 近世の歌舞伎の舞台では、大道具を使用して場面の変化を表現するための技術がありました。 その中で、大道具を90度後...
 と行
と行「どんちゃん騒ぎ」という言葉は、酒宴などでの大騒ぎや、そういったにぎやかな騒ぎを指します。 この言葉の「どんちゃん」は、鉦と太鼓が同時に打たれる時の音を表現したものです。 歌舞伎のような舞台での合戦の場面では、鉦や太鼓が...
 と行
と行「どろん」という言葉は、姿を消して姿を見せないことを指します。 この言葉の由来は歌舞伎の舞台に関連しています。 歌舞伎で、幽霊や霊的な存在が舞台から消えるとき、大太鼓を打って「どろんどろん」という効果音が鳴らされます。 ...
 と行
と行「突拍子もない」という表現は、我々が思いがけない、予期しない、あるいは通常の範疇を超えた事柄や行動を指す際に用いられる言葉です。 この言葉の背景には、太鼓の奏法としての「突拍子」というものが関連しています。 「突拍子」と...
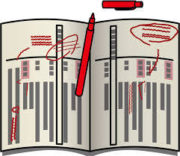 と行
と行「ト書き」という言葉は、演劇の脚本における台詞の間に書かれる、舞台の演出や俳優の動きに関する説明文を指します。 この言葉の起源は、江戸時代の歌舞伎にさかのぼります。 当時、現代でいう脚本に該当するものは「台帳」と称されて...
 と行
と行「頭取」という言葉は、現在では主に銀行の代表者を指す言葉として知られていますが、その語源は雅楽、伝統的な日本の音楽に由来します。 雅楽での合奏時に、首席で演奏する役割を持つ人を「音頭取り」と呼んでいました。 ここでの「音...
 て行
て行「てんてこ舞い」という言葉は、祭りなどで演奏される祭囃子や里神楽において使用される小太鼓「てんてこ」の音にちなんでいます。 この「てんてこ」という小太鼓の音に合わせて、人々が慌しく舞う様子がこの言葉の起源です。 つまり、...
 ち行
ち行「ちゃんぽん」という言葉は、もともと二種類以上のものを混ぜ合わせることやその状態を指す言葉として使われています。 その由来は、日本の伝統的な楽器である鉦(かね)と鼓(つづみ)を合奏する様子に関連しています。 「ちゃん」と...