ねみみにみず【寝耳に水】の語源・由来
「寝耳に水」という表現は、突然の出来事や予期しない出来事に対する驚きを意味する言葉として使われます。 この言葉の由来は、「寝耳に水の入るが如し」という表現から来ています。 もともとは、眠っている間に耳に水の音が聞こえるこ...
 ね行
ね行「寝耳に水」という表現は、突然の出来事や予期しない出来事に対する驚きを意味する言葉として使われます。 この言葉の由来は、「寝耳に水の入るが如し」という表現から来ています。 もともとは、眠っている間に耳に水の音が聞こえるこ...
 ね行
ね行「ねぶた」という言葉と、それに関連するお祭りは、東北地方において非常に有名で、特に青森市や弘前市で行われるものがよく知られています。 お祭りでは、竹や木を基盤とした大きな紙貼りの武者人形や悪鬼、鳥獣などが作られ、その内部...
 ね行
ね行「捏造」という言葉は、「捏」という字が「捏ねる」という動詞から来ており、これは粉や土などを水で練り合わせて一つの固まりにする行為を指します。 「造」は物を作るという意味を持っています。 したがって、「捏造」の語源的な意味...
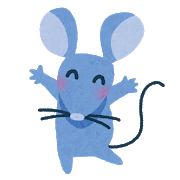 ね行
ね行「ネズミ」は、多くの小型哺乳類の総称として使用されます。 具体的には、ネズミ目(齧歯類)の中の多くの種、リス亜目のホリネズミ、さらにはモグラ目のトガリネズミなどを指します。 ネズミ亜目ネズミ科には、カヤネズミやクマネズミ...
 ね行
ね行「ねじる」の動詞は、物を互いに逆方向に回すような動作や、スイッチや栓を回す動作を指します。 この言葉の起源は、古い上二段動詞「ねづ」からきており、近世以降、四段活用の「ねじる」へと変化しました。 さらに深く語源を探ると、...
 ね行
ね行「ネジ」という言葉は、物を「ねじる」動作やその形状から来ています。 元々の言葉は「ねづ」という上二段動詞で、その連用形から「ネジ」という言葉が派生しました。 このネジが螺旋の形をしていることから、漢字では「螺子」と表記さ...
 ね行
ね行「猫も杓子も」という表現は、日本語で「どんな人も」「誰も彼も」という意味を持ち、全ての人を包括的に示す言葉として使われます。 この言葉の語源や由来には複数の説が存在します。 一つの説は、「禰宜(ねぎ)も釈子(しゃくし)も...
 ね行
ね行「猫に小判」という言い回しは、貴重なものを持っていてもそれが価値を理解できない者には役立たないという意味で使われることが多い表現です。 これは、猫が鰹節のような食べ物には興味を示すものの、人間にとって価値のあるもの、たと...
 ね行
ね行「猫」という言葉は、私たちがよく知っている小型の哺乳動物、特に家畜化されたものを指します。 この動物は体がしなやかで、独特の特徴、例えば爪を引っ込めることができること、ざらざらとした舌、鋭い感覚のひげなどがあります。 家...
 ね行
ね行「ネグリジェ」という言葉は、女性のリラックスした部屋着や寝間着を指します。 この言葉の語源はフランス語の「neglige」で、これは「だらしない」という意味を持ちます。 さらに、この「neglige」はラテン語の「neg...
 ね行
ね行ネオンは希ガス元素の一つで、無臭・無色・無味の気体として知られています。 特に放電管に封入すると美麗な赤色を呈するため、ネオンランプや広告用のネオン管として広く利用されています。 この「ネオン」という名前の由来は、ギリシ...
 ね行
ね行「ネーブル」は、ミカン科ダイダイ類のオレンジの一品種を指します。 このオレンジの特徴的な部分は、果実の頂部にある、へたの反対側の臍状のくぼみや突起です。 この特徴から、英語の「Navel Orange」、すなわち「へその...
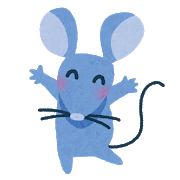 ね行
ね行「子」は、十二支の中で最初の位に位置するものとして認識されており、この象徴として動物の鼠が当てられています。 また、方角としての「子」は北を示し、時刻としては真夜中の12時頃や、大体午後11時から午前1時の間を指します。...
 ね行
ね行「懇ろ」という言葉は、丁寧で心がこもっている様子を表す言葉です。 この言葉の起源は「ねもころ」という古語から来ています。 具体的には、「ねもころ」は「根+も+凝ろ(ころ)」または「根+如(もころ)」の組み合わせとされてい...
 ね行
ね行「閨」は、寝室を意味する言葉です。 この語は「寝屋(ねや)」からきており、文字通り寝るための部屋、すなわち寝室を指すものとして使われています。 簡潔に言うと、「閨」は寝るための場所、つまり寝室を意味する「寝屋」に由来して...
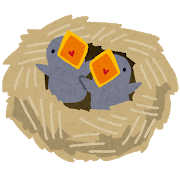 ね行
ね行「塒(ねぐら)」は、寝る場所を指す言葉として使われます。 この言葉の起源は「寝座(ねくら)」で、もともとは鳥が寝る場所、つまり鳥の巣を意味していました。 時が経つにつれて、この言葉は一般的な寝る場所全般を示すようになりま...
 ね行
ね行「禰宜(ねぎ)」は、神職の総称として用いられる言葉です。 この言葉の起源は、神の心を和らげて加護を願うことを意味する動詞「ねぐ(労ぐ)」に関連しています。 具体的には、「ねぐ」の連用形が「ねぎ」として使われるようになった...
 ね行
ね行「ねた」という言葉は、もともと「たね(種)」という言葉の倒語として生まれました。 「たね」は原料や材料、何かを始めるきっかけや元となるものを指す言葉です。 倒語とは、言葉の音節の順番を逆にして新しい言葉を作る手法であり、...
 ね行
ね行「神主(かんぬし)」という言葉は、一般的には神社で神に仕える職業、すなわち神職を指しますが、この文では意外にも「葱」について語っています。 これは、神職の一つである「禰宜(ねぎ)」という呼び名と「葱(ねぎ)」が同音である...
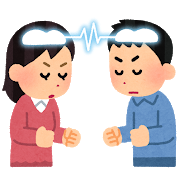 ね行
ね行「拈華微笑」という言葉は、言葉を介さずに心から心へと伝えること、または、そのような非言語的なコミュニケーションを意味します。 この言葉の背景には、釈迦とその弟子たちとの間に起きたある出来事が関連しています。 「拈華」は、...
 ね行
ね行「涅槃」という言葉は、梵語の「nirvāṇa」という言葉が起源であり、それが日本語に取り入れられた際の音写として「涅槃」と書かれるようになりました。 この梵語「nirvāṇa」には、もともと「吹き消す」という意味がありま...
 ね行
ね行「願わくは」という言葉は、願うことやできることならという意味を持つ古典的な表現です。 この言葉の起源は、漢文において願う内容を後に続ける際に使用される「願」を、日本語の訓読みで読むことから派生しました。 具体的には、古語...
 ね行
ね行「合歓の木」とは、マメ科に属する落葉の小高木を指します。 この名称は、「眠りの木」という意味からきています。 その理由は、この木の特徴的な小葉が、夜になると閉じて垂れ下がることから、まるで眠ったかのように見えるためです。...
 ね行
ね行「猫柳」という名前は、ヤナギ科の落葉低木を指します。 この植物は早春に、緑の葉が出るよりも先に、特徴的な大きな花穂を出します。 この白い毛で覆われた花穂が、猫のしっぽのように見えるため、「猫柳」という名前が付けられました...
 ね行
ね行「根掘り葉掘り」という表現は、何から何まで詳しく調べる、または問いただす様子を示す言葉として使われます。 この言葉の由来は、木の根元を丁寧に、そして徹底的に掘り起こす様子からきています。 この行為は、その木や植物のすべて...
 ね行
ね行「猫糞」という言葉は、拾得物を自分のものとしてしまう行為を指します。 この表現の由来は、猫の習性に関連しています。 猫は自らの糞を砂や土で覆い隠すという行動があります。 この隠す行為が、拾ったものをそのまま自分のものとし...
 ね行
ね行「年季を入れる」という言葉は、修練や経験を積むことを意味します。 この表現の起源は、江戸時代に使用人を雇う際に定められた奉公の年限、すなわち「年季」に関連しています。 当時、この奉公の期間を延長する行為を「年季を入れる」...
 ね行
ね行「根回し」という言葉は、事前に関係者との調整や打ち合わせを行うことを意味します。 これは、事がスムーズに進むように、前もって話を整えておくという行為を指します。 この言葉の起源は、木の移植に関連しています。 木を他の場所...
 ね行
ね行「年貢の納め時」という言葉は、物事に終止符を打つ必要がある状況や、あきらめなければならない時を意味します。 この言葉の起源は、かつての日本で行われていた年貢という税の制度に関連しています。 年貢は、農民などが領主や地方の...