やつざき【八つ裂き】の語源・由来
【意味】 ずたずたに裂くこと。 【語源・由来】 「八つ裂き」とは、八つ裂きの刑のこと。罪人の両足または両手両足をそれぞれ二頭ないし四頭の牛の角に繋いで、反対方向に牛を走らせ、四肢を引き裂くという極刑のこと。「牛裂き」とも...
 や行
や行【意味】 ずたずたに裂くこと。 【語源・由来】 「八つ裂き」とは、八つ裂きの刑のこと。罪人の両足または両手両足をそれぞれ二頭ないし四頭の牛の角に繋いで、反対方向に牛を走らせ、四肢を引き裂くという極刑のこと。「牛裂き」とも...
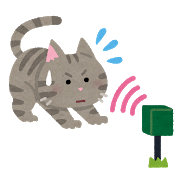 も行
も行【意味】 問題として取り上げないこと。 【語源・由来】 「門前」とは奉行所の門前のこと。 江戸時代の追放刑の中で、罪人を奉行所の門前から追い払うという最も軽い刑を「門前払い」といった。後に、来訪者を追い返すという意味が生...
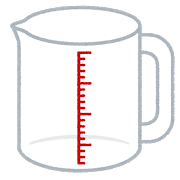 め行
め行【意味】 大体の見当。目あて。 【語源・由来】 目安は、形容詞「めやすし」の語幹が名詞になった語。 「めやすし」の語構成は「目(め)」+「安し(やすし)」で、見ていて安心していられるという意味から、平安時代には「見苦しく...
 む行
む行【意味】 仲間外れにすること。 【語源・由来】 村八分は、江戸時代から行われた習慣。 村八分の「八分」とは、十分ある交際のうち、葬式と火事の際の消火活動の二分以外は付き合わないという意味で、のけ者にすることをいう。
 み行
み行【意味】 離縁すること。または離縁されること。 【語源・由来】 もともとは、江戸時代、離縁の際に夫が妻の家族に出した離別状のことである。この離別状には離婚を決めたという宣言と、妻の再婚許可が三行半にまとめられていたことか...
 ふ行
ふ行【意味】 ある人の思想・主義などを強権的に調べること。また、その手段。 【語源・由来】 江戸時代のキリシタンをあぶりだすために、キリストの絵を踏ませたことから。
 ふ行
ふ行【意味】 配慮・注意が行き届かないこと。不注意なこと。道理や法にそむく行いをすること。不埒なこと。 【語源・由来】 もとは、行き届かないことを意味する言葉で、江戸時代には、裁判の判決文に用いられた。後に、心が法に届かない...
 ひ行
ひ行【意味】 大勢に求められる物や人のこと。 【語源・由来】 タコの干物を作る際、足を四方八方に広げて干された形が磔の刑の様に似ていることから。昔はその形から、磔の刑やその罪人を表す言葉として「ひっぱりだこ」は用いられていた...
 ね行
ね行「年貢の納め時」という言葉は、物事に終止符を打つ必要がある状況や、あきらめなければならない時を意味します。 この言葉の起源は、かつての日本で行われていた年貢という税の制度に関連しています。 年貢は、農民などが領主や地方の...
 な行
な行「名代」という言葉は、元々「名目」や「名義」という意味を持っていました。 つまり、ある物事や人の「名前」や「名称」を指す言葉として使用されていたのです。 しかし、時間が経過するにつれて、その「名前」に付随する「評判」や「...
 と行
と行「問屋」という言葉は、現在では卸売りをする店や人を指す言葉として一般的に知られていますが、その起源は古く、平安時代末期まで遡ることができます。 平安時代末期には、荘園の領主が命じて港や湾に派遣された人々がいました。 彼ら...
 と行
と行「土壇場」という言葉は、現在では「切羽詰まった場面」や「最後の決断を迫られる場面」を指す言葉として使われますが、その語源や由来はその意味とは異なる背景があります。 もともと「土壇場」とは、土を盛り上げて作った壇の場所を指...
 た行
た行大工は、木造家屋を建築する職人を指す言葉として現在では広く用いられています。 その起源は、律令時代に遡ることができます。 この時代には、「大工」は特定の技術官のことを指しており、彼らは「木工寮」という組織や「修理職」とし...
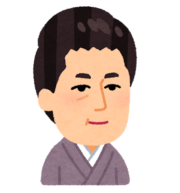 し行
し行「女史」という言葉は、もともと中国や日本における女官を指す言葉として使われていました。 日本の歴史の中で、文書関連の仕事を担当していた勾当内侍という女官がいました。 彼女たちを「女の史」として言及していたことから、その表...
 し行
し行「上戸」という言葉の背景には、古代の日本の令制に起源を持ちます。 令制では、人々の家戸を四等級「大戸・上戸・中戸・下戸」の中でランク付けしていました。 この中で「上戸」は二つ目のランクで、その戸内には六、七人の正丁(成年...
 さ行
さ行「左官」は、壁を塗る職人を指す言葉として現代でも使われていますが、その語源は古代の日本の制度に起源を持ちます。 律令制の時代、官職は四等に分けられており、「かみ」「すけ」「じょう」「さかん」という順序で呼ばれていました。...
 け行
け行「下戸」という言葉は、現代では「酒の飲めない人」を指す言葉として一般的に知られています。 しかしその語源は、日本の古い制度、律令制に起源を持ちます。 律令制の時代、人々は「大戸」「上戸」「中戸」「下戸」という四等戸という...
 き行
き行「極め付き」という言葉の語源は、書画、骨董、刀剣などの鑑定書に付いている「極め書き」から来ています。 この「極め書き」は、専門家や鑑定士がその品物の価値や品質を保証するために書かれる文書であり、これが付いていることでその...
 か行
か行「貫禄(かんろく)」という言葉は、日本の歴史的背景に基づいています。 この言葉は二つの漢字「貫」(かん)と「禄」(ろく)から成り立っています。 「貫」はもともと中世日本で、土地や所領の規模、あるいはその土地から得られる収...
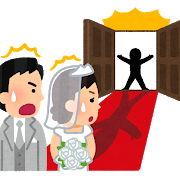 か行
か行「駆け落ち」という言葉は、中世末期から用いられていますが、その起源は戦国時代から江戸時代にかけての「欠落(欠け落ち)」という概念にあります。 当時、欠落とは、戦乱、重税、貧困、悪事などの理由で自分の居住地から逃れる行為を...
 お行
お行「折り紙付き」という言葉は、何かが保証付きで信頼できる状態を表す日本独特の表現です。 この表現は、日本の歴史と文化に深く根ざしています。 元々「折り紙」とは、奉書紙や鳥の子紙といった高級な紙を二つ折りにしたものを指してお...
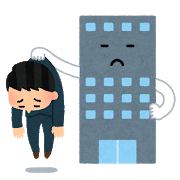 お行
お行「お役御免」という言葉の由来は、元々「役目」を免じられる、つまり仕事や職務などから解放される、あるいは辞めさせられるという状況を指していました。 ここでの「免」は免除の「免」であり、「御免」は許可または免除を意味します。...
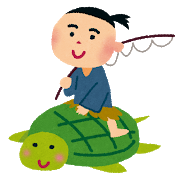 お行
お行「おとぎ話」という言葉は、日本でよく親しまれる形式の童話や昔話を指します。 この言葉の語源には、実は歴史と格式があります。 まず、「とぎ」は、話の相手をして退屈を慰めることを意味します。 ここに接頭語の「お」をつけると「...
 お行
お行「落度」という言葉は、あやまちや過失を指す言葉として現代日本語で用いられますが、この言葉の起源には深い歴史があります。 律令制の時代、日本には関所という場所が設けられ、通行する際の税金などの徴収や人々の行き来をチェックす...
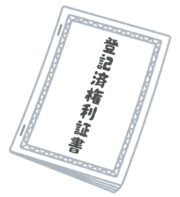 お行
お行「お墨付き」という言葉は、日本語で「権威者からの許可や保証」を指します。 この表現の語源は、室町時代や江戸時代に遡ります。 当時、将軍や大名は、臣下に対して領地を与える際に、その保証として特定の文書を発行していました。 ...
 お行
お行「お仕着せ」という言葉は、もともとはお上(上司や当局)や商家の主人から奉公人などに与えられた衣服を指していました。 この意味から発展して、現代では「上からあてがわれた、形式通りのもの」という広い意味で用いられています。 ...
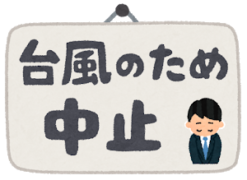 お行
お行「おくら」または「お蔵」という言葉は、もともとは江戸幕府が直轄地から集めた米を保存するための米蔵を指していました。 その後、この言葉は一般的な保管庫や倉庫で保管される品物や家財を意味するようになりました。 この「保管する...
 う行
う行「上前(うわまえ)」という言葉は、本来「人に払うべき賃金や代金の一部」という意味で使われますが、その語源は「上米(うわまい)」という言葉にあります。 元々、「上米」は神仏への奉納や寺社への寄進の形で提供される米を指してい...
 い行
い行「居候」という言葉は、元々江戸時代の公文書において使われていました。 この時代には、家庭内の構成員や関係性を公式に示す場合に「居候」という肩書きが採用されていました。 たとえば、「××方居候 〇〇」という表記があれば、こ...