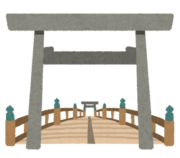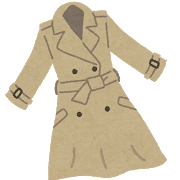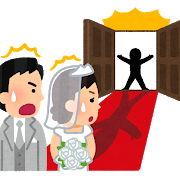「問屋」という言葉は、現在では卸売りをする店や人を指す言葉として一般的に知られていますが、その起源は古く、平安時代末期まで遡ることができます。
平安時代末期には、荘園の領主が命じて港や湾に派遣された人々がいました。
彼らの主な業務は、年貢として徴収される米の輸送、保管、また船の手配などを担当していました。
これらの人々は「問職(といしき)」と呼ばれていました。
時代が流れ、鎌倉・室町時代に入ると、この「問職」の役割は専門化し、さらに具体的な業務が増えました。
特に中継ぎの取引や、船商人向けの宿所の手配なども担当するようになり、この進化した役割を持つ人々は「問丸(といまる)」と呼ばれるようになりました。
彼らは物資の管理、取引の仲介、宿屋の経営といった多岐にわたる業務を行っていました。
そして、さらに時間が経過し、彼らが陸上での輸送も行うようになると、彼らの呼称も変わり「問屋」と呼ばれるようになりました。
江戸時代に入ると、「問屋」という言葉が一般的に使われるようになり、今日に至っています。
この言葉は「といや」とも発音されることもあります。
このような歴史的背景を通じて、「問屋」という言葉がどのように発展してきたのかが理解できます。
とんや【問屋】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「問屋」という言葉の歴史的背景や発展をカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 言葉 | 問屋 |
| 現代での意味 | 卸売りをする店や人 |
| 起源 | 平安時代末期 |
| 初期の役割 | 荘園の領主が命じて港や湾に派遣された人々。年貢の米の輸送、保管、船の手配などを担当。この人々は「問職(といしき)」と呼ばれた。 |
| 鎌倉・室町時代の役割 | 問職の役割が専門化。中継ぎの取引や船商人向けの宿所の手配などを担当。「問丸(といまる)」と呼ばれるようになった。 |
| 陸上輸送の開始と名前の変化 | 陸上での輸送も担当するようになり、「問屋」と呼ばれるようになった。 |
| 江戸時代以降 | 問屋という言葉が一般的に使われるようになった。発音として「といや」とも呼ばれることもある。 |