ろうだん【壟断】の語源・由来
【意味】 利益や権利を独占すること。 【語源・由来】 「壟」は丘。「断」は崖の意。昔、市場で物々交換が行われていたころ、欲深い男が高い所から市場を見下ろして商売に都合のよい場所を見定め、利益を独占したという故事から。「孟...
 ろ行
ろ行【意味】 利益や権利を独占すること。 【語源・由来】 「壟」は丘。「断」は崖の意。昔、市場で物々交換が行われていたころ、欲深い男が高い所から市場を見下ろして商売に都合のよい場所を見定め、利益を独占したという故事から。「孟...
 り行
り行【意味】 人や物がぎっしりつまっていて、少しの隙間もないこと。 【語源・由来】 「立錐」は木に穴をあける道具「錐(きり)」を立てること。「錐を立てるほどの余地もない」の意。「立錐の地なし」ともいう。漢の劉邦の質問を受け、...
 り行
り行【意味】 演劇界。とくに歌舞伎者の社会のこと。 【語源・由来】 芸術を好んだ唐の玄宗皇帝が、唐都長安西北郊の西内苑内で、梨が植えられている宮中の庭園に弟子を集め、自ら歌舞音曲を教えたという故事から。この弟子たちは「皇帝の...
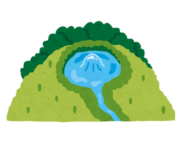 ら行
ら行【意味】 物事の始まり。起源。 【語源・由来】 「濫」は「溢れる」(河川の氾濫等)の意、「觴」は「盃」の意。孔子のことば「その源は以て觴を濫(ひた)すべし」から出た語。中国の長江のような大河でも、源流を遡れば觴(さかずき...
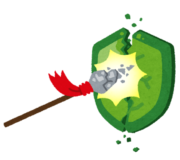 む行
む行【意味】 つじつまが合わないこと。 【語源・由来】 楚の国に矛と盾を売り歩く商人がいた。矛を売る時は「この矛はどんな堅い盾でも突き通す」と言い、盾を売る時は「この盾はどんな矛でも防ぐ」と言った。客の一人が「では、その矛で...
 み行
み行【意味】 夫と死別した婦人。後家。 【語源・由来】 元々は、夫に先立たれた夫人が、「自分は未だに死亡していない」の意で用いる謙遜の自称。かつて中国では、夫が死んだら妻もそれに従うという観念があった。楚の宰相の子元が、亡き...
 ま行
ま行【意味】 背中など手の届かないところをかくのに使う、手の形に作った棒。 【語源・由来】 「麻姑(まこ)の手」が変化した語。「麻姑」は、鳥のように爪が長い、中国の伝説上の仙女のこと。麻姑の爪でかゆい所をかいてもらうと、非常...
 ほ行
ほ行【意味】 後悔する。 【語源・由来】 「臍」はへそ。自分のへそを噛もうとしても口は届かないが、それでも噛もうとするほど残念でいらいらすることから。春秋時代、鄧の祁候(きこう)の三人の甥が、楚の文王を見て、祁候に進言した時...
 ほ行
ほ行【意味】 人びとを教え導く人。指導者。 【語源・由来】 昔、法令などを世に示すときに鳴らした木製の舌を持った金属製の鈴のこと。人民に触れて歩くときに、これを振り鳴らしたことから。転じて、世間に警告を発し、教えを導く人のた...
 ほ行
ほ行【意味】 思っていた通りの結果になって、ひそかに笑う。 【語源・由来】 「ほくそ」を「北叟」の転とする説がある。北叟は、中国の北方の砦に住むとされた老人塞翁(『淮南子』の故事「塞翁が馬」(人生の吉凶や禍福は予想できないも...
 ほ行
ほ行【意味】 意見や態度をかたく守り続けること。 【語源・由来】 「墨」は、博愛・非戦を説く、中国春秋時代の思想家の墨子(ぼくし)のこと。楚の王は、公輸盤(こうしゅばん)が開発した雲梯(長いはしご)を使って、宋を攻めようとし...
 ほ行
ほ行【意味】 他人の目を気にせず、勝手気ままにふるまうこと。 【語源・由来】 中国の『史記(刺客列伝)』にある「旁(=傍)若無人者」という表現から。「傍らに人無き者のごとし」と訓読し、「まわりにひとがいないかのようなふるまい...
 ふ行
ふ行【意味】 夜でも昼のように明るいにぎやかな場所。歓楽街など。 【語源・由来】 漢の時代、中国の東莱郡(現在の山東省)の不夜県にあった城の名からとする説がある。不夜県の名は、夜も太陽が出て明るかったという伝説による。「三斉...
 ふ行
ふ行【意味】 世間の騒がしい議論・評判。とりざた。 【語源・由来】 「酔えば則ち鐸(すず)を執りて挽歌し、物議を屑(いさぎよ)しとせず(酔うと大きな鈴を鳴らしてうたい、世間の評判など気にもしなかった)」から出た言葉。これは、...
 ひ行
ひ行【意味】 酒のこと。 【語源・由来】 「漢書」食貨志の「酒は天の美禄」から。「美禄」は。すばらしい賜り物のこと。「美禄を食む」など、よい給与の意で使われることもある。
 ひ行
ひ行【意味】 行動や態度などが、がらりと変わること。 【語源・由来】 豹の毛が季節によって生え変わり、豹の斑文が美しくなることから。「君子豹変す、小人は面を革 (あらた) む(君子は豹の模様のようにはっきりと過ちを改めるが、...
 ひ行
ひ行【意味】 向こう見ずの勇気。 【語源・由来】 戦国時代の孟子の言葉から。『孟子・梁恵王下』より。「これ匹夫の勇、一人に適する者なり(無分別な男のむやみな強がりで、たった一人を相手にするだけの者だ)」と述べ、もっと大きな勇...
 は行
は行【意味】 すべてのことが終わりである。もはや手の施しようがない。 【語源・由来】 荊南の王従誨(じゅうかい)は、まだ幼い息子の保勗(ほうきょく)を溺愛し甘やかした。それをねたんでいる者がにらみつけても、保勗はにっこり微笑...
 は行
は行【意味】 今まで誰も成し得なかったようなことをすること。 【語源・由来】 「天荒」は未開の地。中国唐代に「荊州(けいしゅう)」からは「科挙(高等官資格試験制度)」で合格者がなかったため、「天荒」と呼ばれたが、「劉蛻(りゅ...
 は行
は行【意味】 止めようとしても止まらない激しい勢い。 【語源・由来】 竹を割る時、最初の一節を割ると、あとは勢いよく割れることから。西晋の武将杜預(どよ)が呉を攻撃する作戦会議を開いた時、将の一人が「今はちょうど暑さに向かう...
 は行
は行【意味】 非常に危険な状況にのぞむことのたとえ。 【語源・由来】 「詩経」にある詩句「戦戦兢兢、如レ臨二深淵一、如レ履二薄氷一(深い淵をのぞきこむ時のように、また薄い氷の上を歩く時のように、こわごわと慎重に行動する)」か...
 は行
は行【意味】 白い眉毛。また、同類の中で最も優れている人や人物のこと。 【語源・由来】 三国時代の蜀の馬氏に優秀な五人兄弟がいた。その兄弟の中でも「馬良」が最も優秀であった。馬良は幼いころから眉毛に白い毛があって「白眉」と呼...
 は行
は行【意味】 優劣がつけにくいこと。 【語源・由来】 「伯」は長兄、「仲」は次兄の意。兄弟の年齢を上から順に「伯」「仲」「叔」「季」という。兄と弟くらいの違いしかない、この二人に大きな差がないということから、力が接近し優劣の...
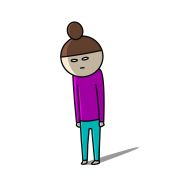 は行
は行【意味】 冷たい目つき。 【語源・由来】 中国・晋時代の「竹林の七賢人」の一人である阮籍が、俗世の礼儀にうるさい人には冷淡な目つき(白眼)で接し、尊敬したり好意を持っている人物は、歓迎の目つき(青眼)で交わったという故事...
 は行
は行【意味】 夫婦が離別すること。 【語源・由来】 やむをえず離れて暮らすことになった夫婦が、鏡を二つに割ってそれぞれの一片を持ち、愛情のあかしとして別れた。のちに、妻が不義を働いたために、その一片がカササギとなって夫の所へ...
 な行
な行「鳴かず飛ばず」という言葉は、将来の活躍の機会を静かに待ち構えているさまや、長い間何も目立った活躍をしないことを指す表現です。 この言葉の起源は、春秋時代の中国にさかのぼります。 当時、楚の国に伍挙という賢者がおり、荘王...
 と行
と行「虎の巻」という言葉は、秘伝の書や参考書を指す表現として使用されます。 この表現の起源は、古代中国の兵法書「六韜(りくとう)」に由来しています。 この「六韜」は、様々な戦略を解説した六つの編から成り立っており、その中の一...
 と行
と行「怒髪天を衝く」という言葉は、極端な怒りを表す表現で、毛髪が天を突くほどの勢いで逆立っているさまを意味します。 この言葉の起源は、中国の戦国時代のエピソードに由来します。 そのエピソードでは、趙の国にあった美しい宝石「和...
 と行
と行「登竜門」という言葉は、現代では立身出世のための難関や厳しい試験を表す隠喩として使われます。 この言葉の背景には、古代中国の伝説や故事が関わっています。 伝説によれば、黄河上流には竜門山という場所があり、その山を切り開い...
 と行
と行「頭角を現す」という言葉は、学識や才能が人よりも優れて顕著になることを意味します。 この表現の中の「頭角」とは文字通り「頭の先」を指し、その先端が他よりも突き出ているというイメージから、特別に優れていることを指すようにな...