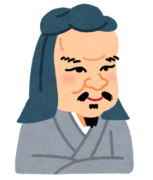「鳴かず飛ばず」という言葉は、将来の活躍の機会を静かに待ち構えているさまや、長い間何も目立った活躍をしないことを指す表現です。
この言葉の起源は、春秋時代の中国にさかのぼります。
当時、楚の国に伍挙という賢者がおり、荘王という王が即位してから三年間、何も大きな政治的な活動をしないで享楽に耽っていました。
伍挙はこの王の行動に懸念を感じ、王を諫めるために言った言葉がこの「鳴かず飛ばず」の起源とされています。
伍挙が王に向かって言ったのは、 「我が国には大鳥がおり、王庭に止まっています。しかし、この大鳥は三年間鳴くことも飛ぶこともしません。この大鳥は一体何の鳥でしょうか?」 という意味の言葉でした。
これは、王が即位してからの三年間、何も行動を起こさなかったことを皮肉って指摘するものでした。
この言葉によって、荘王は自分の行いを省み、その後、真摯に国政に取り組むようになったと言われています。
このエピソードは「史記」という史書に記されており、その中の話から「鳴かず飛ばず」という言葉が生まれ、日本語にも取り入れられることとなったのです。
【鳴かず飛ばず】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「鳴かず飛ばず」という言葉の起源や背景、意味をカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 言葉 | 鳴かず飛ばず |
| 基本的な意味 | 将来の活躍の機会を静かに待ち構えるさまや、長い間何も目立った活躍をしないこと |
| 語源の時代 | 春秋時代の中国 |
| 関連する人物 | 伍挙(楚の国の賢者)と荘王 |
| 伍挙の言葉 | 「我が国には大鳥がおり、王庭に止まっています。しかし、この大鳥は三年間鳴くことも飛ぶこともしません。この大鳥は一体何の鳥でしょうか?」 |
| 言葉の影響 | 荘王はこの言葉によって自らの行動を省み、真摯に国政に取り組むようになった |
| 記録の史書 | 史記 |
| 日本語への影響 | 「史記」からこの言葉が日本語に取り入れられた |