ぴんはね【ピン撥ね】の語源・由来
【意味】 他人の利益のうわまえを先に取ること。 【語源・由来】 「ピン撥ね」の「ピン」は、カルタ・賽の目などの一数を意味する語でポルトガル語の「pinta」から。転じて、一割、一部の意になり、一割をかすめ取る意から、上前...
 ひ行
ひ行【意味】 他人の利益のうわまえを先に取ること。 【語源・由来】 「ピン撥ね」の「ピン」は、カルタ・賽の目などの一数を意味する語でポルトガル語の「pinta」から。転じて、一割、一部の意になり、一割をかすめ取る意から、上前...
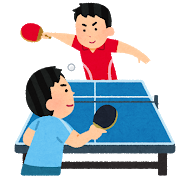 ひ行
ひ行【意味】 球技の一つ。長方形の卓の中央にネットを張り、ラケットでプラスチック製のボールを打ち合って得点を競う。シングルス・ダブルス・混合ダブルスの試合形式がある。テーブル-テニス。 【語源・由来】 「ピンポン」は元々商品...
 ひ行
ひ行【意味】 不快感を与えるようなことをして嫌われ、軽蔑される。 【語源・由来】 「顰蹙」は、不快を感じて眉をひそめること。嫌って軽蔑することを「顰蹙する」といい、「顰蹙される」は「顰蹙を買う」と同じような意味。
 ひ行
ひ行【意味】 ①礼を失すること。不作法。無礼。不敬。 ②きたなく、けがらわしくて、人前で失礼に当たること。 【語源・由来】 愚か、ばかの意の古語「おこ(痴)」の当て字「尾籠」を音読した語。のちに、無礼、不敬の意味になり、礼を...
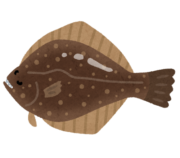 ひ行
ひ行【意味】 ①やや平らなさま。 ②平板なこと。変化に乏しく、趣のないこと。 【語源・由来】 「ひらめ」は、平たい体に、目が二つ並んでいることから名付けられたという説、片平に目が二つ並んでいることから、「比目魚」が語源とする...
 ひ行
ひ行【意味】 平安初期、漢字の草体から作られた草(そう)の仮名をさらにくずして作った音節文字。女性も用いたので女手と呼ばれ、はじめは種々の異体があった。「ひらがな」の称は後世のもの。 【語源・由来】 「ひらがな」は、片仮名と...
 ひ行
ひ行【意味】 ①片目が小さく口のとがった男の滑稽な仮面。潮吹面。また、その仮面をかぶって踊る滑稽な踊り。 ②男子をののしっていう語。 【語源・由来】 「ひょっとこ」は、火を吹くときの顔つきからか、「ヒヲトコ(火男)」が転じた...
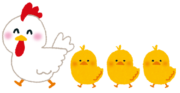 ひ行
ひ行【意味】 ①鳥の子。特にニワトリの子。ひな。 ②転じて、身体・才能・学問・技術などのまだ十分に発達しない者。一人前でない者。ひよっこ。 【語源・由来】 「ヒヨコ」の「ヒヨ」は、「ヒヨヒヨ」なくことからで、「コ」は、小さな...
 ひ行
ひ行【意味】 気軽明朗であって滑稽なこと。おどけ。 【語源・由来】 「剽軽」の「軽(キン)」は唐音。「剽」は、すばやいの意。漢語の「剽軽」はすばやいさまを表す。日本に入ってから、気軽明朗で滑稽なことを意味するようになった。
 ひ行
ひ行【意味】 細打ちにしたうどんをゆでて冷水で冷やし、汁をつけて食べるもの。 【語源・由来】 「ひやむぎは、小麦粉を原料とする乾麺の一種で、室町末期頃に、手で延ばした素麺に対して、切って細くしたものを切麦と呼んだ。さらに、切...
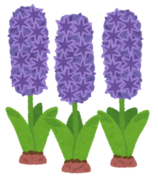 ひ行
ひ行【意味】 クサスギカズラ科(旧ユリ科)の多年草。秋植え球根植物。地中海沿岸の原産。鱗茎から肉質で広線形の葉を叢生。春、青・紫・紅・黄・白色、また一重咲・八重咲の花を総状に付ける。花に芳香があり、園芸品種が多い。江戸末期に...
 ひ行
ひ行【意味】 ①(ヒャクセイとも)一般の人民。公民。 ②(もと荘園農民の呼称)農民。 ③いなか者をののしっていう語。 【語源・由来】 「百姓」は、古くは「ひゃくせい」ともいい、「百」はたくさんの意で、古代中国では、種々の姓を...
 ひ行
ひ行【意味】 ①はにかむ。 ②気おくれする。しりごみする。 【語源・由来】 現在では、気おくれする、しりごみするという意味で多く用いられるが、元々は、「はにかむ」という意味で、江戸時代の川柳の句集「誹風柳多留」に「あいさつに...
 ひ行
ひ行【意味】 スズメ目ヒバリ科の小鳥。スズメよりやや大きく、背面は黄褐色の地に黒褐色の斑がある。腹部は白く、後向きの趾(あしゆび)の爪は非常に長い。日本各地の畑地・草原などに巣を作って、空中高くのぼってさえずる。鳴き声は「一...
 ひ行
ひ行【意味】 ①皮と肉。転じて、からだ。 ②(骨や髄にまで達しない所の意)うわべ。表面。理解の浅いところ。 ③骨身にこたえるような鋭い非難。 ④遠まわしに意地わるく弱点などをつくこと。あてこすり。 ⑤物事が予想や期待に相違し...
 ひ行
ひ行【意味】 雛祭にかざる人形。 【語源・由来】 「雛人形」の「雛」は、ひよこの意から、小さい、愛らしいという意味を表す語。雛人形は、古く平安時代からあり、穢れや災いを人形(ひとがた)に移して流す風習だった。初め立ち雛(紙雛...
 ひ行
ひ行【意味】 才能のあるすぐれた子供のこと。 【語源・由来】 「飛兎」「竜文」はともに、非常によく走るすぐれた馬、駿馬のこと。転じて、才知あふれる子供の意となった。「竜」は「りょう」、「文」は「もん」とも読む。
 ひ行
ひ行【意味】 たったひとりでいること。孤独であること。また、その人。 【語源・由来】 「ひとりぼっち」は、「ヒトリボフシ」の訛。「ヒトリボフシ」は、「独法師」と書き、宗派や教団などに属さない僧侶の境遇を表す語で、あてもなく世...
 ひ行
ひ行【意味】 人が多く集まっていて、体の熱気やにおいが立ち込めること。 【語源・由来】 「人いきれ」の「いきれ」は、蒸し暑くなる、ほてる、いきまく、りきむの意の動詞「いきれる(熱れる)」の名詞形。「草いきれ」の「いきれ」と同...
 ひ行
ひ行【意味】 サル目(霊長類)ヒト科のうち、直立二足歩行を行い著しく発達した脳を有する動物。狭義にはヒト科ヒト属現生種のホモ・サピエンス。人類。また、その一員としての個々人。 【語源・由来】 「人」は万物の霊長から、「霊」が...
 ひ行
ひ行【意味】 ①写字・清書などによって報酬を得ること。また、その人。 ②文筆により生計を立てること。 【語源・由来】 「筆耕硯田」の略。「筆耕」も「硯田」も、いずれも文章で生計を立てることをいう。筆で硯(すずり)を耕す意で、...
 ひ行
ひ行【意味】 通りがかりの自動車に便乗させてもらい、乗り継ぎながら目的地まで行く。 【語源・由来】 「ヒッチハイク」は、英語「hitchhike」から。輪・鉤・索などでひっかける意の「hitch」+歩いていく、徒歩旅行するの...
 ひ行
ひ行【意味】 ①十二支の第8。動物では羊に当てる。 ②南から西へ30度の方角。 ③昔の時刻の名。今の午後2時頃。また、およそ午後1時から3時のあいだの時刻。 【語源・由来】 「未」は、本来は「み」と読み、漢音では「び」。「漢...
 ひ行
ひ行【意味】 ひっこすこと。転居。転宅。 【語源・由来】 「引っ越し」は、転宅する意の動詞「引き越す」が転じて名詞化された語。「越す」だけでも引っ越しの意味がある。「引く」は、今住む場所から退いて越す意味から、「退く越す」と...
 ひ行
ひ行【意味】 ①(当て字で吃驚・喫驚と書く。)不意のできごと、予期せぬ物事に驚くさま。 ②(普通、下に打消しの語を伴った形で)わずかに動くさま。 【語源・由来】 「ぴくり」と同源の「びくり」の強調形。「吃驚」「喫驚」は、近代...
 ひ行
ひ行【意味】 ひききりなしの音便。きれめがないこと。絶え間がないさま。たてつづけ。 【語源・由来】 「ひっきりなし」は、「引切り無し」からで、「引切り」は、手元に引くように切ることから、切れ目をいい、とぎれること、間が切れる...
 ひ行
ひ行【意味】 左手で団扇を使うこと。安楽な暮らしの境遇のたとえ。ひだりおうぎ。 【語源・由来】 「左団扇」は、利き手でない左手でゆうゆうと団扇を使う意から。一般的に右手が利き手の人が多いことからいう。「左団扇を使う」「左扇で...
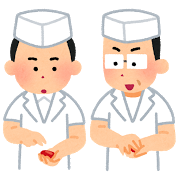 ひ行
ひ行【意味】 無批判に他人の言動の真似をする。一般に、師や先輩の言説を拠りどころにして自説を展開する(行動を手本として同じようにする)ことを謙遜していうのに用いられる。 【語源・由来】 「顰(ひそみ)」は動詞「ひそむ(顰む)...
 ひ行
ひ行【意味】 ①神経症の一型。劣等感・孤独・性的不満・対人関係などの心理的感情的葛藤が運動や知覚の障害などの身体症状に無意識的に転換される反応。歩行不能・四肢の麻痺・痙攣・自律神経失調・皮膚感覚鈍麻・痛覚過敏・失声・嘔吐など...
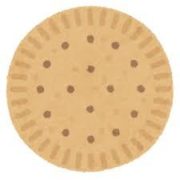 ひ行
ひ行【意味】 小麦粉に砂糖・バター・牛乳・ベーキングパウダーなどを混ぜて焼いた薄く小形の洋菓子。 【語源・由来】 「ビスケット」は、英語「biscuit」から。「biscuit」は、二度焼かれたという意味のラテン語「Bisc...