わたりにふね【渡りに船】の語源・由来
【意味】 必要なものがちょうど都合よく揃うこと。好都合なこと。 【語源・由来】 「法華経」の「薬王品(やくおうぼん)」にある表現で「子の母を得るは、渡りに船を得たるが如し」から出た言葉。子にとっての母の存在を、川の向こう...
 わ行
わ行【意味】 必要なものがちょうど都合よく揃うこと。好都合なこと。 【語源・由来】 「法華経」の「薬王品(やくおうぼん)」にある表現で「子の母を得るは、渡りに船を得たるが如し」から出た言葉。子にとっての母の存在を、川の向こう...
 ろ行
ろ行【意味】 必要以上の親切心。 【語源・由来】 仏教用語の「老婆心切」が語源。年をとった女性が子や孫をかわいがったり、余計な忠告をしたり、世話を焼きがちだったりするように、師が弟子をいつくしみ導くこと。また、そのような心遣...
 る行
る行【意味】 光沢のある青い宝石。 【語源・由来】 仏教の七宝の一つ。梵語vaiḍūryaの音写「吠瑠璃」の略。多く、青い色の宝石を指すとされる。
 る行
る行【意味】 同じ状態にとどまらず、移り変わること。 【語源・由来】 仏教語。六道・四生の迷いの生死を繰り返すこと。生まれ変わり死に変わって迷いの世界をさすらうこと。転じて、変化し続ける意になった。
 り行
り行【意味】 生死を繰り返すこと。 【語源・由来】 回転する車輪が何度も同じ場所に戻ってくるように、衆生が迷いの世界に生まれ変わり死に変わりすること。仏教の基本的な考え方。梵語のsaṃsāraに由来する語。
 り行
り行【意味】 義理がたいこと。実直なこと。 【語源・由来】 仏教では「りつぎ」と読み、悪を抑制するはたらきのあるものを指す。また、悪を防いで善を行うように導く戒律の意。転じて義理をかたく守る意になった。
 ゆ行
ゆ行【意味】 (野や山へ)遊びに行くこと。 【語源・由来】 禅宗では、晴れ晴れとした心境で、山水の景色を楽しみながら暮らすこと。また、遊山の「遊」は自由に歩きまわること、「山」は寺のことで、修行を終えたあと、他山(ほかの寺)...
 ゆ行
ゆ行【意味】 自分だけがすぐれているとうぬぼれること。 【語源・由来】 「天上天下唯我独尊」の略。この世で自分はもっとも尊い存在であるという意。釈迦が生まれた際、七歩歩き、右手で天を左手で地を指していったとされる言葉。この世...
 や行
や行【意味】 古代インドの鬼神。また、俗に恐ろしい女性のたとえ。 【語源・由来】 梵語yakṣaの音写。神聖な霊的存在で元は古代インドの神。仏教では、法を守る八部衆の一つ。毘沙門天の眷属で、北方の守護にあたる。また、外面似菩...
 や行
や行【意味】 ちょっと聞きかじっただけで知っているつもりになっている人。 【語源・由来】 禅宗で、まだ悟りきっていないのに悟ったかのようにふるまう人を野ぎつねにたとえたことば。
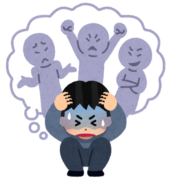 も行
も行【意味】 ありえないことを想像すること。根拠のないことを信じること。 【語源・由来】 心の迷いによって起こる誤った考え。仏教では、不正な考えやみだらな考えは、すべて心の迷いによって生み出されるとされる。古くは「もうぞう」...
 め行
め行【意味】 非常に。むやみに。はなはだしく。 【語源・由来】 因果関係に支配されないもの。絶対に生滅変化しない真如や涅槃といった絶対的真理のこと。それを究極的なものと解したことから、程度のはなはだしい意が生じたと考えられる...
 め行
め行【意味】 とんでもない。 【語源・由来】 仏教語で、物事や生物の移り変わりを四段階に分けた四相(生相・住相・異相・滅相)の一つ。 四相では、事物がこの世に出現することを「生相」、存在・持続することを「住相」、変化すること...
 め行
め行【意味】 あの世。 【語源・由来】 死者の魂がたどって行く道(=途)。また、成仏できない魂の行きつくところ。閻魔王など多数の地獄の役人がいて、生前の罪を裁くといわれる。「冥途」とも書く。
 む行
む行【意味】 世の中が変わりやすく、はかないこと。 【語源・由来】 この世の中の一切のものは常に生滅流転 (しょうめつるてん)して、永遠不変のものはないということ。「無情」と書くと、「情愛のないこと」の意。
 む行
む行【意味】 無限にあること。いくら取ってもなくならないこと。 【語源・由来】 本来は仏教語で、尽きることのない財宝を納めた蔵のこと。仏の無限の功徳のたとえ。もっと世俗の世界になると、庶民のための金融機関、「無尽講(頼母子講...
 む行
む行【意味】 残酷なさま。また、気の毒なさま。 【語源・由来】 本来は仏教語で、「無慙」「無慚」と書く。罪を犯しても恥じないことをいう。羞恥心のないこと。「慙」は恥ずかしく思う意。対義語は「慚」で、自分の犯した罪を恥じること...
 む行
む行【意味】 純粋なさま。けがれないさま。 【語源・由来】 煩悩のないこと。心を汚すもの(=垢)がなく、清浄であること。
 み行
み行【意味】 まだ来ていないとき。将来。 【語源・由来】 仏教では、死後の世界のこと。三世(前世、現世、来世)のひとつ。「未来」は未だ来たらざる世。つまり、次の世のことで来世。
 み行
み行【意味】 ある立場で受ける恩恵。 【語源・由来】 本来は、善業によって受ける利益。これは、仏や菩薩が、知らず知らずの間に与える利益で、「冥加の利益(みょうがのりやく)」といった。転じて、人がおのずと受ける恩恵の意になった...
 み行
み行【意味】 今までにない非常に珍しいこと。 【語源・由来】 もとは、「びっくりした」の意の梵語「adbhuta」が漢訳された仏教語。仏の功徳の尊さや神秘なことを賛嘆した言葉であった。「未だ曾て有らざる(いまだかつてあらざる...
 み行
み行【意味】 細かいちり。また、非常に細かいもの。 【語源・由来】 仏教で、非常に小さいものを表す単位。物質を分割し、これ以上細分できない大きさを極微(ごくみ)といい、一つの極微を中心に、上下四方の六方から極微が結合したもの...
 ま行
ま行【意味】 くまなく。全体に。 【語源・由来】 「満遍」は仏教語で、平均・平等の意。転じて、残るところなく行き渡ることを表すようになった。「満遍なく」の「なく」は否定の活用語尾ではなく、「満遍ない」の連用形。「万遍なく」と...
 ま行
ま行【意味】 この世の諸相を描いたもの。 【語源・由来】 梵語maṇḍalaの音写。本質を有するものの意。本来は悟りを得るための「修行道場」をいった。また、密教では、経典にもとづき、主尊を中心に諸仏諸尊の集会(しゅうえ)する...
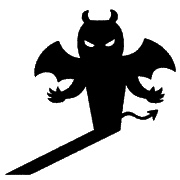 ま行
ま行【意味】 陰茎。男根。 【語源・由来】 梵語māraの音写。人の善事を妨げる悪神、また悟りの妨げとなる煩悩をいう。陰茎の意はここから転じたものとも、排泄する意の「まる」の交替形ともいう。もとは僧の用いた隠語。
 ま行
ま行【意味】 極めて不思議なこと。 【語源・由来】 「摩訶」は、梵語mahaの音写で、大きいこと、すぐれていることの意。他の語について、「摩訶般若波羅蜜多心経(まかはんにゃはらみったしんぎょう)」や「摩訶曼陀羅華(まかまんだ...
 ほ行
ほ行【意味】 心を悩ますもの。 【語源・由来】 「煩悩」とは、本来は仏教語で、何かに心がひどく煩わされて心の平穏が保てないこと。すべての欲望や怒り、執着などを基本とする。
 ほ行
ほ行【意味】 でたらめ。うそ。また、大言を吐くこと。 【語源・由来】 仏教では「ほうら」と読み、仏の説法のさかんなことをいう。もともと、「法螺」は法螺貝の意味で、吹くと大きな音がする巻き貝でつくった笛の一種。山伏が深山でお互...
 ほ行
ほ行【意味】 死後の冥福。 【語源・由来】 菩提は梵語bodhiの音写。「道・智・覚」と訳され、煩悩を断って得た悟りをいう。また、涅槃に至ること。人は死ぬと仏になるという信仰から、死後の冥福という意味を持つようになった。
 ほ行
ほ行【意味】 ある目的を達成するために利用する便宜上の手段。 【語源・由来】 「方便」とはもとは仏教語で、衆生を救い、真の教えへと導くための便宜的な手段のこと。「嘘も方便」という成句は江戸時代から見られ、法華経の「三車火宅(...