ぼんぼり【雪洞】の語源・由来
【意味】 ①(ぼんぼりと書く)ものがうすく透いてぼんやりと見えるさま。はっきりしないさま。ほんのり。 ②(「雪洞」と書く) ア.茶炉などに用いる紙張のおおい。せっとう。 イ紙または絹張りのおおいを付けた手燭・燭台。また、...
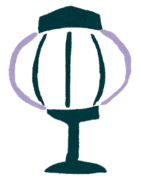 ほ行
ほ行【意味】 ①(ぼんぼりと書く)ものがうすく透いてぼんやりと見えるさま。はっきりしないさま。ほんのり。 ②(「雪洞」と書く) ア.茶炉などに用いる紙張のおおい。せっとう。 イ紙または絹張りのおおいを付けた手燭・燭台。また、...
 ほ行
ほ行【意味】 家畜などを殺すこと。また、古くなった自転車などを叩き壊して解体すること。転じて、老朽したもの。廃品。 【語源・由来】 「ぽんこつ」は、「拳骨(げんこつ)」を聞き間違え「ぽんこつ」になったという説と、拳骨で殴る「...
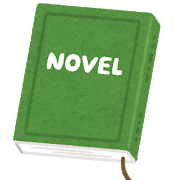 ほ行
ほ行【意味】 ①中心となるもの。また、もととなるもの。主。 ②もととしてみならうべきもの。てほん。かがみ。 ③書籍。書物。 ④まこと。正しい。正式のもの。 ⑤(接頭辞的に用いて)今問題にしているそのものの意。自分の側に属して...
 ほ行
ほ行【意味】 半袖襟付きのシャツ。前あきが短く、頭からかぶって着る。 【語源・由来】 「ポロシャツ」は、ポロ競技の際に着たことに由来。ポロ競技とは、小型の馬(ポニー)に乗ってT字型のスティックで木製のボールを打ち、相手のゴー...
 ほ行
ほ行【意味】 内分泌腺など特定の組織または器官から分泌され、血液とともに体内を循環し、特定の組織の機能に極めて微量で一定の変化を与える物質の総称。甲状腺ホルモン、性ホルモン、昆虫の変態ホルモンなど。 焼肉のホルモン焼きは、豚...
 ほ行
ほ行【意味】 志願者。奉仕者。自ら進んで社会事業などに無償で参加する人。また、その無償の社会活動。 【語源・由来】 「ボランティア」は、義勇兵の意の「volunteer」から。「volunteer」は、自由意志の意のラテン語...
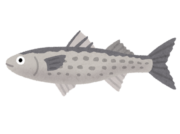 ほ行
ほ行【意味】 ボラ科の硬骨魚。淡・鹹両水域にすむ。体は長くて円みを帯び、頭端は鈍い。胃壁は厚く、俗に臍または臼という。背部灰青色、腹部銀白色。全長約80センチメートルに達する。世界各地に産し、養殖魚ともなる。秋に美味。卵巣を...
 ほ行
ほ行【意味】 ホヤ綱の尾索類の総称。海産、固着性で、単独または群体を作る。単体のものは球形から卵形、群体では板状のものが多い。木質を含む厚い被嚢を被る。出水孔と入水孔があり、水中に浮かぶ微細な食物を水とともに吸入ろ過して食う...
 ほ行
ほ行【意味】 イヌの一品種。ポメラニアン地方原産といわれるが、初期のものはかなり大型、現在の小型犬はイギリスで改良されたもの。毛は豊富で細く、色は多様。愛玩用。 【語源・由来】 「ポメラニアン」は、ドイツ東部とポーランド西部...
 ほ行
ほ行【意味】 ヤナギ科の落葉高木。北欧原産。葉は菱形。高く伸び、樹形が美しいので、街路樹や牧場などに植える。材は細工用。セイヨウハコヤナギ。このほか、北米産のアメリカヤマナラシなどの同属の数種を総称してポプラと呼ぶことがある...
 ほ行
ほ行【意味】 髪を後頭部に高く束ね、ポニーの尻尾のように垂らす髪型。 【語源・由来】 「ポニーテール」は、子馬のしっぽの意の英語「ponytail」から。髪を後頭部に高く束ね、ポニーの尻尾のように垂らす髪型のことをいう。
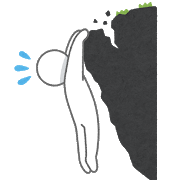 ほ行
ほ行【意味】 ①大方。大略。 ②今少しで。すんでのことで。 【語源・由来】 「ほとんど」は、大体、ほとんどの意味の副詞「ほとほと」が転じた語。室町時代中頃には、「ほとんど」の形で見られる。「ほとほと」は、「ほとり」の語根「ほ...
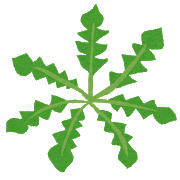 ほ行
ほ行【意味】 ①キク科のタビラコの別称。春の七草の一つ。 ②シソ科の一年草または越年草。原野・路傍に自生。茎は柔軟で高さ25センチメートル前後。春、紫色の唇形花を輪状に付ける。ホトケノツヅレ。三階草。漢名、宝蓋草。 【語源・...
 ほ行
ほ行【意味】 ①ア悟りを得たもの。仏陀。 イ釈迦牟尼仏。 ②仏像。また、仏の名号。 ③仏法。 ④死者またはその霊。 ⑤ほとけのように慈悲心の厚い人。転じて、お人よし。 ⑦大切に思う人。 【語源・由来】 「ほとけ」は、「ぶつ(...
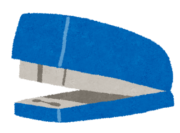 ほ行
ほ行【意味】 ①機関銃の一種。ガス圧を利用した空冷式のもの。 ②紙綴器の一種。「コ」の字型の綴じ針を挿入し内側へ折り曲げることで、紙などを綴り合わせる具。綴込器。ステープラー。ホチキス。 【語源・由来】 アメリカの兵器発明者...
 ほ行
ほ行【意味】 祝儀やお年玉を入れる、小さい熨斗袋。 【語源・由来】 「ポチ袋」の「ポチ」は、京阪の方言で心づけ、祝儀、チップのこと。客が、芸妓や茶屋女に少額の祝儀を渡したことがはじまりで、「これっぽち」という控えめな気持ちが...
 ほ行
ほ行【意味】 ホタルイカモドキ科のイカ。小型で、胴長6センチメートル弱。体の各部に数百個の発光器を備え、刺激を受けると青白い光を発する。水深600メートルくらいにすむが、5~6月の産卵期には夜浮上する。オホーツク海から日本海...
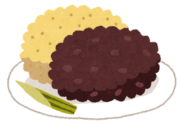 ほ行
ほ行【意味】 ①糯米や粳米などを炊き、軽くついて小さく丸め、餡(あん)・黄粉(きなこ)・胡麻などを付けた餅。おはぎ。はぎのはな。きたまど。隣知らず。 ②女の顔の丸く大きく醜いもの。 ③丸くて大きなもののたとえ。 【語源・由来...
 ほ行
ほ行【意味】 ①束縛される。からみつかれる。 ②特に、人情にひかれて心や行動が束縛される。 【語源・由来】 「絆される」は、綱でつなぎとめる、自由を束縛されるの意の動詞「絆す(ほだす)」に受身の助動詞「れる」が付いた形。束縛...
 ほ行
ほ行【意味】 フランス料理のスープの総称。日本では特に、コンソメに対して、とろみのある濃いスープを指す。 【語源・由来】 「ポタージュ」は、フランス語「Potage」から。「po」は、飲むことの意の古い印欧祖語で、ラテン語の...
 ほ行
ほ行【意味】 ①ア.部署。 イ.職。地位。 ②郵便箱。また、郵便受け。 ③標柱。支柱。 【語源・由来】 「ポスト」は、英語「post」から。「post」は、配置する、立てるの意のラテン語「ponere」の過去分詞男性形が、フ...
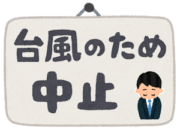 ほ行
ほ行【意味】 つぶれる。駄目になる。 【語源・由来】 「ぽしゃる」の「ぽしゃ」は、降参する意の「シャッポをぬぐ」の「しゃっぽ」の倒語。「シャッポをぬぐ」は「シャッポだ」ともいい、降参する意味と駄目になる意を関連付けた語。
 ほ行
ほ行【意味】 ①こまかな塵(ちり)の飛ぶもの。綿のようなごみ。 ②はした。あまり。のこり。 【語源・由来】 「ほこり」は、「ホオコリ(火起)」「ホケリ(火気)」「ホコゴリ(火凝)」「ホコリ(火残)」「立ち放こる」の意味からと...
 ほ行
ほ行【意味】 皮膚に点在する黒色または暗褐色の小斑で、母斑の一種。毛を生ずることもある。ははくそ。ほくそ。 【語源・由来】 「ほくろ」は、古くは「ははくそ」といい、「くそ」は、「垢」や「かす」のことで、「ほくろ」が、母の胎内...
 ほ行
ほ行【意味】 言葉少なく無愛想な人。また、道理のわからない者。わからずや。 【語源・由来】 「朴念仁」の「ぼくねん」は擬態語、「じん」は人の意。無愛想で(頭が堅くて)話せない人のこと。
 ほ行
ほ行【意味】 小鋼球をペン先に装置し、運筆に応じて回転し軸内の糊状インクを滲出させて書くペン。 【語源・由来】 「ボールペン」は、英語「ballpoint pen」を略した語。小鋼球がペン先にはめこまれていることからの名。1...
 ほ行
ほ行【意味】 ①割増金。株式の特別配当金。 ②賞与。特別手当。期末手当。 【語源・由来】 「ボーナス」は、英語「bonus」から。「bonus」は、良いの意のラテン語「bonus」から。「bonus」は、ローマ神話の成功と収...
 ほ行
ほ行【意味】 スズメ目ホオジロ科の鳥。スズメより少し大きく、背面は大体栗褐色で、胸腹部は淡褐色、顔は黒色で頬が白い。日本では林縁や草原・川原など開けた場所でよく見られる。雄のさえずりは「一筆啓上仕り候」「源平つつじ白つつじ」...
 ほ行
ほ行【意味】 今にも這い出さんばかりの様子。散々な目にあってかろうじて逃げる様子。 【語源・由来】 「這う這うの体」の「這う這う」は、這うようにして、這いながら、かろうじて歩いてという意味。転じて、散々な目にあってかろうじて...
 ほ行
ほ行【意味】 ①頭にかぶって寒暑または塵埃を防ぎ礼容をととのえるもの。 ②烏帽子の略。 ③物の頭部にかぶせるもの。 ④刀剣の切先にある刃文。 ⑤囲碁で、相手の石を攻めるため、二路上からかぶせるように圧迫する手。 【語源・由来...