ふがいない【不甲斐ない】の語源・由来
「ふがいない」という言葉は、古語「言いふ甲斐無かひなし」または「言いふ易無かへなし」から派生したとされています。 この中の「甲斐かい」という部分は、何かをすることで得られる効果や、それによって生じる満足感を意味しています...
 ふ行
ふ行「ふがいない」という言葉は、古語「言いふ甲斐無かひなし」または「言いふ易無かへなし」から派生したとされています。 この中の「甲斐かい」という部分は、何かをすることで得られる効果や、それによって生じる満足感を意味しています...
 ふ行
ふ行【意味】 ①足に力を入れて倒れまいとする。 ②主張して屈しない。譲歩しない。 ③気力を出して苦難に堪える。こらえる。がんばる。 【語源・由来】 「ふんばる」は、「踏み張る(フミハル)」の音便。「踏み張る」は、足を開いて強...
 ふ行
ふ行【意味】 多くあるさま。十分にゆたかなさま。たくさん。 【語源・由来】 絶え間のないことの意の「不断(ふだん)」の転。途切れることなく続く意から多くあるさまをいうようになった。「ふんだん」のほか、「ふんだく」「ふんだ」と...
 ふ行
ふ行【意味】 ふんぎること。決断すること。 【語源・由来】 「ふんぎり」は、思い切ることの意の「踏み切り(フミキリ)」の音便。「踏み」は動詞「踏む」の連用形の名詞形。「ふん」は、「ふん縛る」「ふん捕まえる」のように、思い切る...
 ふ行
ふ行【意味】 くそ。大便。 【語源・由来】 「ふん」は、漢字「糞」を読んだもので、呉音・漢音ともに「ふん」。漢字表記「糞」は、肥料の意味がある。現在では、人間の排せつ物は「くそ」、「大便」といい、動物の排せつ物を主に「ふん」...
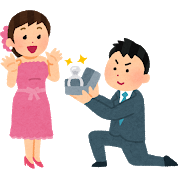 ふ行
ふ行【意味】 申し込むこと。特に、結婚の申し込み。求婚。 【語源・由来】 「プロポーズ」は、結婚を申し込む意の英語「prppose」から。「propose」は前に置く意のラテン語「proponere」(前にの意の「pro-」...
 ふ行
ふ行【意味】 数種のナチュラルチーズを原料にし、それを混合・加熱・溶解して作る加工チーズ。 【語源・由来】 「プロセスチーズ」は、英語「process cheese」から。「process」は加工処理するという意味で、「na...
 ふ行
ふ行【意味】 ①風呂に入る時には衣類を包んでおき、湯から上がった時には足を拭うのに用いた布。 ②物を包むのに用いる方形の布。古くは「ひらづつみ」ともいう。 【語源・由来】 「風呂敷」は、風呂の床に布を敷いたことから。 元々は...
 ふ行
ふ行【意味】 ウェブサイトの一種。個人や数人のグループで運営される日記形式のもので、情報提供や意見交換などのコミュニケーション機能が付加されている。 【語源・由来】 「Web」と「log」の造語、Webに残される記録の意の「...
 ふ行
ふ行【意味】 ①入浴のために設けた場所。湯殿。浴室。また、ゆぶね、古くは戸棚式の蒸風呂、江戸時代、浴槽を設けたものや柘榴口をつけたものが現れ、蒸風呂は次第に廃れた。温湯浴が主流になるとともにそのための浴槽・浴室、また湯そのも...
 ふ行
ふ行【意味】 あらかじめ工場で部材の加工・組立を行い、現場で組み上げる建築構法。また、その建築物。 【語源・由来】 「プレハブ」は、英語「prefab」から。「prefab」は、prefabrication」の略。「pref...
 ふ行
ふ行【意味】 贈り物をすること。また、贈り物。進物。 【語源・由来】 「プレゼント」は、英語「present」から。「present」は、前に持ってくるという意味のラテン語から。「present」は前にの意の「pre」+存在...
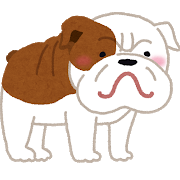 ふ行
ふ行【意味】 イヌの一品種。イギリスで雄牛(ブル)との格闘犬として作出。毛色はふつう茶、腹側は白い。肩高約40センチメートル。頭は大きく、口は幅広く、独特のしゃくれた顔をしている。四肢は筋骨たくましく、耳は小さく尾も短い。現...
 ふ行
ふ行【意味】 ①昔のことである。 ②存在してから長い年月を経ている。以前から伝わっている。 ③長い間使いならして古びている。 ④年老いている。年功を積んでいる。 ⑤陳腐だ。珍しくない。 ⑥新鮮でない。 【語源・由来】 「ふる...
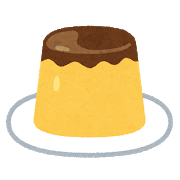 ふ行
ふ行「プリン」は、英語の「pudding」からきた言葉とされています。 この「pudding」の語源には複数の説が存在します。 一つ目の説は、ラテン語の「boutullus」が元になっているとされています。 この「boutu...
 ふ行
ふ行【意味】 ヤナギ科の落葉低木。バッコヤナギとネコヤナギの雑種と推定され、切り花用に植栽される。アカメヤナギ。ピンクネコヤナギ。 【語源・由来】 「フリソデヤナギ」は、1657年、江戸でおこった「明暦の大火(振袖火事)」の...
 ふ行
ふ行【意味】 蚤の市。フリマ。 【語源・由来】 「フリーマーケット」は、英語「flea market」からで、「flea」は蚤の意。「フリーマーケット」は、パリ郊外の「ラ・ポルト・ド・サン・クリニャンクール」で開かれた中古品...
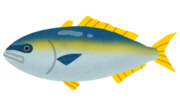 ふ行
ふ行【意味】 アジ科の海産の硬骨魚。体は長い紡錘形。背部は鉄青色、腹部は銀白色で、体側に前後に走る淡黄色の帯がある。全長約1メートル。日本付近に分布し、養殖もされる。寒鰤といい、冬に美味。いわゆる出世魚で、幼魚から順にワカシ...
 ふ行
ふ行【意味】 商標。銘柄。特に、名の通った銘柄。 【語源・由来】 「ブランド」は、英語「brand」から。「brand」は、罪人に押した焼印の意味もあり、焼印を利用して、自社製品の表示を行っていたことから商標、銘柄の意になっ...
 ふ行
ふ行【意味】 ①計画。設計。 ②設計図。平面図。 【語源・由来】 「プラン」は、計画、企画、工夫する、設計するの意の英語「plan」から。「plan」は、平面図の意のラテン語「plaus」から。
 ふ行
ふ行【意味】 ①かきしるしたもの。文字。 ②文書。書物。 ③手紙。書状。恋文。 ④学問。特に、漢学。 ⑤漢詩。漢文。 【語源・由来】 「ふみ」は、「文」の字音「フン」からといわれる。
 ふ行
ふ行【意味】 ①人や物をのせて水上を渡航するもの。 ②水・酒などを入れる箱型の器。湯ぶね・酒槽(さかぶね)・紙漉槽・馬糧桶の類。 ③棺。 ④刺身などを入れて売る底の浅い容器。 「舟」は手でこぐ小型のものに使うことが多い。「槽...
 ふ行
ふ行【意味】 いくじのないこと。まぬけ。こしぬけ。 【語源・由来】 「腑抜け」の「腑」は内蔵、はらわたの意。はたわたをぬきとられている意から、いくじのないことを意味する。似たような言葉に「腑が抜ける」があり、元気がなくなる、...
 ふ行
ふ行【意味】 合点がいかない。納得できない。 【語源・由来】 「腑に落ちない」の「腑」は内蔵。転じて、心の意。そこから、「腑に落ちない」は、人の意見などが心に入ってこない、納得できないという意味になった。本来は、「腑に落ちな...
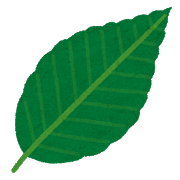 ふ行
ふ行【意味】 ブナ科の落葉高木。やや高い山地に生え、ブナ帯の代表種。特に日本海側山地に多い。幹の高さ約20メートル。葉は広卵形。5月頃、淡緑色の花を開き、単性で雌雄同株。果実は殻斗(かくと)内になって堅く、10月頃成熟し、食...
 ふ行
ふ行【意味】 ①蒲の葉で編み、坐禅などに用いる円座。ほたん。 ②(「布団」は当て字)綿・藁またはパンヤ・羽毛などを布地でくるみ、座りまたは寝る時に敷いたり掛けたりするもの。 【語源・由来】 「ふとん」は、元々は、蒲の葉で編ん...
 ふ行
ふ行【意味】 フトモモ科の常緑高木。インドネシア原産。沖縄では野生化。高さ8メートル。葉は披針形で厚い。花は白色・大形で長い雄しべが多数伸びる。液果は芳香があり、食用。 【語源・由来】 「フトモモ」は、中国名の「蒲桃(プータ...
 ふ行
ふ行【意味】 不満があって人の言うことをきかない。また、不平があって投げやりな振舞をする。ふてくさる。 【語源・由来】 「ふてくされる」は、動詞「ふてる」の強調表現。「不貞腐れる」は当て字。「ふてる」は、捨てばちな行動に出る...
 ふ行
ふ行【意味】 ①仏教で重んずる、仏と法と僧。すなわち三宝。 ②ブッポウソウ目ブッポウソウ科の鳥。全長約30センチメートル。頭・風切羽・尾羽の大部分は黒色、その他は美しい青緑色で、嘴・脚は赤い。風切羽の中央に青白色の大斑があり...
 ふ行
ふ行【意味】 突然起こる。思いがけなく現れる。 【語源・由来】 「降って湧く」は、「天から降る」と「地から湧く」を合わせた語。天から降り地から湧くことが同時に起こることを意味し、そこから、思いがけなく現れる意味になった。