まんをじす【満を持す】の語源・由来
【意味】 ①弓を十分に引いてそのまま構える。 ②準備を十分にして機会を待つ。 【語源・由来】 「史記・李将軍伝」から。 「満を持す」の「満」は、ここでは、弓を十分に引くこと。「持す」は、ある状態・態度を保ち続ける意。弓を...
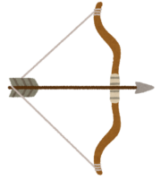 ま行
ま行【意味】 ①弓を十分に引いてそのまま構える。 ②準備を十分にして機会を待つ。 【語源・由来】 「史記・李将軍伝」から。 「満を持す」の「満」は、ここでは、弓を十分に引くこと。「持す」は、ある状態・態度を保ち続ける意。弓を...
 ま行
ま行【意味】 買い物をするふりをして、店頭の商品をかすめとること。また、その人。万買。 【語源・由来】 「まんびき」は、商品を間引いて盗むことから、「間(ま)」に「引(ひき)」の意からとされる。また、運を狙って引き抜くという...
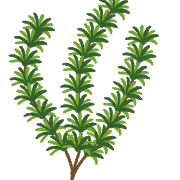 ま行
ま行【意味】 シソ科の常緑低木ローズマリーの和名。食用、薬用などハーブとして多くの用途がある。 【語源・由来】 「マンネンロウ」は香りが強いことから、「常に香りがする」という意味で「万年香」と呼ばれていた。「万年香」が「まん...
 ま行
ま行【意味】 中空の軸にインクを入れ、その先に金または合金のペン先を取り付け、使用するにしたがってインクがペン先に伝わり出るようにしたペン。万年ペン。 【語源・由来】 1809年、イギリスのフレデリック・B・フォルシュがペン...
 ま行
ま行【意味】 マンネリズムの略。 【語源・由来】 「マンネリ」は、英語「mannerism(マンネリズム)」の略で、「mannerism」は、同じ趣向が繰り返されて、新鮮さを失うこと。特に芸術作品などで、手法・様式などが型に...
 ま行
ま行【意味】 中高層の集合住宅。1960年代後半から急速に普及。 【語源・由来】 「マンション」は、大邸宅の意の英語「mansion」から。「mansion」は、とどまる場所の意のラテン語「manera」から。日本でいう「マ...
 ま行
ま行【意味】 二人が掛合いで滑稽な話をかわす演芸。また、その芸人。関西で大正中期、万歳が舞台で演じられたことから始まり、昭和初年掛合い話が中心となる。 【語源・由来】 「まんざい」は、元々は「万歳」で、いつまでも栄えるように...
 ま行
ま行【意味】 アカメヤナギの別名。 【語源・由来】 「マルバヤナギ」の「マルバ」は、葉が丸みを帯びていることからの名。柳の葉は細長いことが多く、丸みを帯びていることは珍しいためこの名が付けられた。
 ま行
ま行【意味】 ①ちょうど。あたかも。さながら。 ②(下に否定的な語を伴って)全く。全然。まるっきり。 【語源・由来】 「まるで」は、「丸で」の意味で、丸は欠けたところがないことから、完全の意になり、完全に似ているさまをいう「...
 ま行
ま行【意味】 イヌの一品種。肩高15センチメートルほど。白の絹糸のような長毛が体や顔を覆う。ローマ時代以来の愛玩犬。 【語源・由来】 「マルチーズ」は、「マルタの」という意味の英語「maltese」から。原産が地中海沿岸のマ...
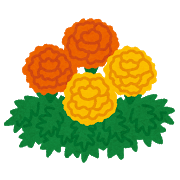 ま行
ま行【意味】 キク科の一年草。メキシコ原産の観賞用植物数種の総称。高さ30~50センチメートル。葉は羽状複葉。夏に球状の頭花を開く。園芸品種が多く、花色は黄・橙赤など。孔雀草。紅黄草。万寿菊。 【語源・由来】 「マリーゴール...
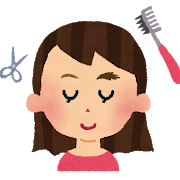 ま行
ま行【意味】 ①目の上に横になって生えた毛。まゆげ。まいげ。まよ。 ②眉墨の略。 ③烏帽子の前面、額の上を押しこんだ所に出る皺の横線。左右両方あるのを諸眉、左右いずれか一方のを左眉・右眉といった。 ④牛車の屋形の前後にある軒...
 ま行
ま行【意味】 1⃣(名) ①マメ科の植物。また、その種子。ふつう食用にする大豆・小豆・隠元などにいう。 ②特に、大豆。 ③手足の皮膚がかたいものとこすれてできる豆のような水ぶくれ。 ④食用にする牛・豚などの腎臓...
 ま行
ま行【意味】 へびの一種。有毒。体長は約60センチメートル。頭は三角形またはスプーン形、頸は細く、全身暗灰色か赤褐色あ(赤蝮と俗称)で黒褐色の銭型斑が多い。目と鼻にあるピット器官で、餌とする小動物の体温を感知する。卵胎生。日...
 ま行
ま行【意味】 瀬戸内海沿岸で、海魚サッパのこと。 【語源・由来】 「ままかり」は、「飯借り」と書き、この魚の酢漬けがおいしいことから、飯が無くなってしまい、隣家から飯を借りて食べたほど食が進むことから「ままかり」になったとい...
 ま行
ま行【意味】 ①襟巻。 ②消音器。 【語源・由来】 「マフラー」は、英語「muffler」から。「maffler」は、包む、覆うの意の「muffle」から。防寒のために包むことから「襟巻」の意になり、音を消したり抑えたりする...
 ま行
ま行【意味】 眼球の表面をおおって開閉する皮膚のひだ。まなぶた。眼瞼(がんけん)。 【語源・由来】 「まぶた」は、目の蓋の意。「ま」は、「目」が複合語の中で用いられるときの形。古くは「まなぶた」といった。 「な」は古形の格助...
 ま行
ま行【意味】 まばたくこと。またたき。 【語源・由来】 「瞬き」は、動詞「瞬く(まばたく)」の連用形の名詞化。「まばたく」の「ま」は目の意で、複合語の中で用いられる際の形。「ばたく」は、叩くの意の動詞「叩く(はたく)」。
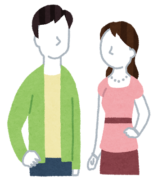 ま行
ま行【意味】 ①衣服を着せて飾る陳列用の等身大の人形。 ②ファッション-モデル。 ③新作の服装や化粧をして宣伝・販売する人。マヌカン。 【語源・由来】 「マネキン」は、フランス語「mannequin」から。「mannequi...
 ま行
ま行【意味】 ①まねること。模倣。 ②動作。ふるまい。しぐさ。 【語源・由来】 「まね」は、動詞「まねぶ(学ぶ)」、「まなぶ(学ぶ)」と同源。「真に似せる」の意から、模倣の意の「まね」や「まねぶ」が生じ、「まなぶ」になったと...
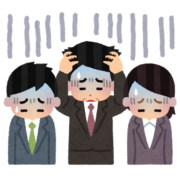 ま行
ま行【意味】 間の抜けたこと。することにぬかりのあること。その人。とんま。 【語源・由来】 「まぬけ」の「ま」は、時間的な感覚の「間」のこと。「間が抜ける」で、テンポが合わないことを意味する。転じて、することにぬかりがあるこ...
 ま行
ま行【意味】 ①宣言。宣言書。 ②特にマルクス・エンゲルスの「共産党宣言」を指す。 ③選挙で、政党・候補者が掲げる具体的な公約。 【語源・由来】 「マニフェスト」は、イタリア語「manifesto」から。「manifesto...
 ま行
ま行【意味】 手の爪の手入れ・化粧。また、それに用いる液。爪をみがき、つや出しし、色付けなどをする。 【語源・由来】 「マニキュア」は、英語「manicure」から。手の意のラテン語「manu」+手当の意の「curare」か...
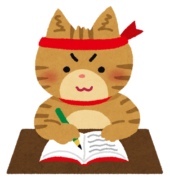 ま行
ま行【意味】 ①まねてする。ならって行う。 ②教えを受けて身につける。習得する。 ③学問をする。勉強する。 ④経験を通して身につける。 【語源・由来】 「まなぶ」は、「まねる(真似る)」と同源で、「まねぶ(学ぶ)」から。「ま...
 ま行
ま行【意味】 目じり。 【語源・由来】 「まなじり」は、「目の後(しり)」の意から。「目」の意の「ま」+古形の格助詞「の」+末端部分の意の「しり」から成る語。平安時代には、「まじり」といわれ、「めじり(目尻)」に変化した。現...
 ま行
ま行【意味】 ①黒眼。 ②めだま。眼球。目。 【語源・由来】 「まなこ」は、目の子の意味から。目の意の「ま」+古形の格助詞「の」+「子(こ)」。「目」の意の「まなこ」が、「目の子」になったのは、元々は、黒眼(瞳)のみを指して...
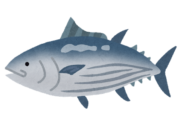 ま行
ま行【意味】 マナガツオ科の海産の硬骨魚。全長約60センチメートル。体は側扁し、輪郭は丸みのある菱形で、蒼銀白色。口は小さい。背びれとしりびれとは鎌型。美味。南日本産。広義にはマナガツオ科魚類の総称。 【語源・由来】 「マナ...
 ま行
ま行【意味】 ①まつること。祭祀。祭礼。俳諧では特に夏祭りをいう。 ②特に、京都加茂神社の祭の称。 ③近世、江戸の二大祭。日吉山王神社の祭と神田明神の祭。 ④記念・祝賀・宣伝などのために催す集団的行事。祭典。 【語源・由来】...
 ま行
ま行【意味】 「まつかさ」の別称。まつぼくり。 【語源・由来】 「まつぼっくり」の「ぼっくり」は、精巣の意の「フグリ」が転じた「ボクリ」の促音化。形が精巣に似ていることからといわれる。「松陰嚢」は当て字。
 ま行
ま行【意味】 ①ことごとく。すべて。 ②じつに。まことに。 ③(下に打消しの語を伴って)決して。全然。 ④まこと。本当に。 【語源・由来】 「まったく」は、欠けたところがない、十分である、安全であるの意の形容詞「まったい(全...