やもり【守宮】の語源・由来
【意味】 トカゲに似た爬虫類の一種。 【語源・由来】 人家に住みつくことから「家を守る」の意。家を守る番人と考えられていることから「家守」とも書く。
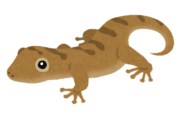 や行
や行【意味】 トカゲに似た爬虫類の一種。 【語源・由来】 人家に住みつくことから「家を守る」の意。家を守る番人と考えられていることから「家守」とも書く。
 や行
や行【意味】 巻貝の殻に住む節足動物。 【語源・由来】 他の貝の殻を借りて住むことから。
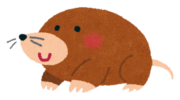 も行
も行【意味】 土中に住む哺乳動物。 【語源・由来】 地下に潜って土を高くもり上げることから、「もぐらもち」「むぐらもち」と呼ばれていたものの転といわれている。漢字表記の「土竜」は漢名ではミミズのこと。モグラがミミズを食べるこ...
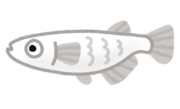 め行
め行【意味】 メダカ科の淡水魚。 【語源・由来】 メダカは目の大きな魚で、その目が体の先の方の高い位置にあることからこの名があるという。
 み行
み行【意味】 フクロウ目フクロウ科の鳥のうち、耳のような羽角をもつ種の総称。 【語源・由来】 「耳付く」もしくは「耳突く」の意味から。「木菟」は、木に住み、ウサギのような耳を持つことからの当て字。
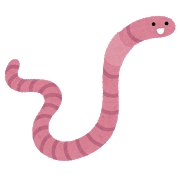 み行
み行【意味】 土の中に住む環形動物。 【語源・由来】 「蚯蚓」は、目が見えないが光を感じる細胞があり暗いほうへ這っていく。目で見ることができない動物の意味から、「目不見(めみず)」と呼ばれ、それが転じたとされる。または、「日...
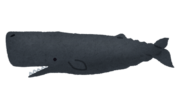 ま行
ま行【意味】 鯨の一種。ハクジラ類で最大。 【語源・由来】 「抹香」とは、沈香(じんこう)やセンダン(栴檀)などを混ぜて作った香料のこと。仏事に用いられる。「抹香鯨」は、腹部にある模様の色が抹香の色に似ていることからつけられ...
 ほ行
ほ行【意味】 ホタル科の昆虫。 【語源・由来】 夜間に光ることから「火照(ほてり)」または、「火垂(ほたり)」とよばれ、それが転じたものといわれている。
 ふ行
ふ行【意味】 フクロウ科の夜行性の鳥。 【語源・由来】 毛が膨れた姿から「膨るる(ふくるる)」の転といわれる。また、鳴き声に由来するともいわれている。他にも、夜行性なので、「昼隠居(ひるかくろう)」の転ともいわれる。別名「五...
 ひ行
ひ行【意味】 海底にすむ棘皮動物。 【語源・由来】 五本の腕を放射線状に出した姿が、人の手に見えることから。「人手」とも書く。「海星」の表記は、形が星に似ていることから。
 は行
は行蛤は海産の二枚貝の一種であり、その名前の由来はその形状からきています。 蛤の形が栗の実に似ていること、そしてこの貝が浜辺に生息していることから、「浜栗」と呼ばれるようになりました。 その後、この名前が時代とともに「はまぐ...
 は行
は行【意味】 鼠の一種。 【語源・由来】 一説によると、噛まれても痛くない「甘口(あまくち)」のネズミというところから「甘口鼠( あまくちねずみ)」と呼ばれたものが、後に「廿日鼠(はつかねずみ)」となったといわれている。江戸...
 と行
と行「蜻蛉」、日常的には「とんぼ」として知られるこの昆虫に関する言葉の語源や由来には複数の説が存在します。 一つの説は、「トン」が「飛ぶ」を意味し、「バウ」が「棒」を意味するという点から、「飛ぶ棒」という意味で「とんぼ」と名...
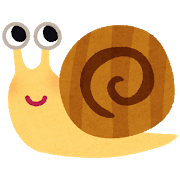 て行
て行「蝸牛(でんでんむし)」は、かたつむりの別名です。 この名前の由来は、「出出虫(ででむし)」からきています。 かつて、子供たちがかたつむりに向かって「出よ、出よ」と、つまり「外に出てこい」と呼びかける様子から「ででむし」...
 つ行
つ行「月輪熊」という名称は、特定の熊の一種を指す名前です。 この名前の由来は、その熊の胸部に見られる特有の模様に関係しています。 この熊の胸には三日月型の白い模様が存在し、この特徴的な模様が「月の輪」と似ていることから、「月...
 ち行
ち行「千鳥」は、チドリ科に属する小型の水鳥を指す名前です。 この名前の由来は、主に二つの説があります。 一つ目の説は、「千」の部分が「数が多い」という意味を持っており、この鳥が群れをなして飛ぶ様子を表現しているというものです...
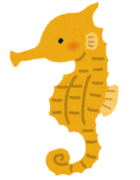 た行
た行「竜の落とし子」という名称は、ヨウジウオ科の海魚の名前として知られていますが、この名前の背景には特有の意味合いが込められています。 「おとしご」という部分は「落とし子」を指し、これは身分の高い人が正妻以外の女性との間にも...
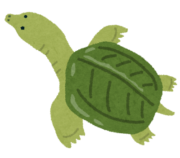 す行
す行「すっぽん」または「鼈」とは、淡水に生息する亀の一種を指します。 この言葉の由来にはいくつかの説があります。 まず、一つの説として「すっぽん」の鳴き声が「スホンスホン」と聞こえることからその名がついたとされています。 こ...
 し行
し行「尺取虫」は、シャクガ科の蛾の幼虫の名前として知られています。 この名前の由来は、その特有の進み方からきています。 尺取虫は、人が親指と人差し指を使って物の長さを測る、つまり「尺を取る」という動作に似た、一歩一歩前に進む...
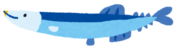 さ行
さ行秋刀魚は、サンマ科に属する海魚で、特に日本で秋の味覚として人気があります。 この魚の名前「秋刀魚」には、魚の体型や漢名の意味が関連しています。 もともと、その細長い体型から「狭真魚(さまな)」と呼ばれていたとされ、この名...
 さ行
さ行「山椒魚」という名前は、この両生類の特徴と「山椒」という植物との関連性から来ています。 山椒魚は、その皮膚から分泌する粘液のにおいが、香りの強いスパイスとして知られる植物「山椒」のにおいに似ているとされるため、この名がつ...
 こ行
こ行「こめつきむし」は、コメツキムシ科に属する昆虫の名前です。 この名前の由来は、その昆虫の特徴的な動作に関連しています。 具体的には、この昆虫の体を押さえると、頭を振る動作を行います。 この動作が、米を搗(つ)くときの様子...
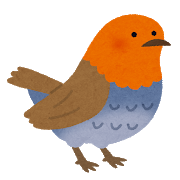 こ行
こ行駒鳥はツグミ科に属する小さな鳥で、その名前の由来には特定の意味が込められています。 具体的には、「駒」という言葉は、馬を指す言葉として知られています。 そして、この鳥の名前が「駒鳥」と呼ばれる理由は、その特有の鳴き声が、...
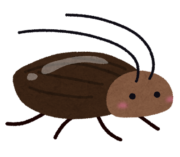 こ行
こ行「蜚蠊」は、ゴキブリ科の昆虫を指す言葉で、一般的には「ごきぶり」として知られています。 この「ごきぶり」という言葉の語源は、「御器噛り(ごきかぶり)」から派生しています。 ここでの「御器」は、食物を盛るための椀や器を指し...
 こ行
こ行五位鷺は小型の鷺を指す言葉として知られています。 この名称の「五位」は、古代日本の位階制度での五番目の位を示すもので、宮中での地位や階級を示すものでした。 この名前の由来には、ある故事が関わっています。 伝承によれば、醍...
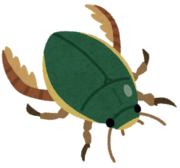 け行
け行「源五郎」という言葉は、ゲンゴロウ科に属する昆虫を指す名称です。 この名前の由来は、その昆虫の特徴的な外見に関連しています。 具体的には、ゲンゴロウの背部は黒っぽい色をしています。 この黒い色の特徴から、「玄い甲」、すな...
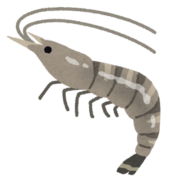 く行
く行「くるまえび」、または車海老は、特定の海老の一種を指す言葉です。 この名前の由来は、車海老の独特な特徴に関連しています。 車海老の身体は、殻の部分に縞模様があります。 さらに、この海老が身体を丸く曲げると、その形が車輪の...
 く行
く行「くらげ」、または「水母」は、海を浮遊する腔腸動物を指す言葉です。 この名前の由来は、実際には確定しているわけではなく、複数の解釈や考察があります。 まず、水母は目がないため、それが「暗い」という意味の「くらい」と関連付...
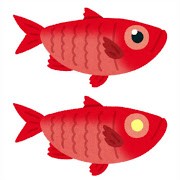 き行
き行「金目鯛」は、この魚が持つ金色の大きな目に由来する名前です。 金色は一般に貴重で美しいとされる色で、その鮮やかな目が特徴的なこの魚にぴったりの名称といえるでしょう。 興味深い点として、名前に「鯛」が含まれているものの、実...
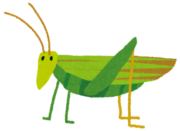 き行
き行「螽斯(きりぎりす)」という名前は、その特有の鳴き声から名付けられたとされています。 この鳴き声は、日本文化においても詩や俳句、文学作品などでしばしば取り上げられ、美しい自然の象徴とされています。 また、その漢字の表記は...