わざわい【災い】の語源・由来
【意味】 不幸をもたらすような出来事。 【語源・由来】 「わざ」は神のしわざ。「わい」は接尾語とされる。悪い結果をもたらすような神のしわざの意。
 わ行
わ行【意味】 不幸をもたらすような出来事。 【語源・由来】 「わざ」は神のしわざ。「わい」は接尾語とされる。悪い結果をもたらすような神のしわざの意。
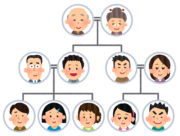 れ行
れ行【意味】 確かで、疑う余地のないようす。明白なさま。 【語源・由来】 身分や家柄の高いさまをいう「歴とした」に促音「っ」の入った形。
 ら行
ら行【意味】 さまざま。 【語源・由来】 「四方八方」の意の「よもやま」の転かといわれる。
 よ行
よ行【意味】 たいそう。ずいぶん。 【語源・由来】 良い程度の意を表す「良き程」が音変化したもの。もとは「ちょうどよい程度」をいった。「かなりの程度」の意になるのは江戸時代以降で、「余程」はそのころからの当て字。
 ゆ行
ゆ行【意味】 睡眠中、現実のように物事を感じる現象。 【語源・由来】 奈良時代は「いめ」。寝て物を見てることから、「寝目(いめ)」の意とされる。「寝(い)」は「睡眠」、「目(め)」は「見えるもの」の意味。
 ゆ行
ゆ行【意味】 婚約成立の印に金銭や品物を取り交わすこと。また、その金銭や品物。 【語源・由来】 申し込みの意の「言ひ入れ(いひいれ)」が変化した語で、動詞「言ふ」が語形の変化で「ゆふ」となったのに伴ない、「言ひ入れ」も「ゆひ...
 や行
や行【意味】 身分が高い。 【語源・由来】 「止む事無し」が一語化したもので、もとは「止むに止まれぬ、捨てておけない」の意。のち、並々でない意、尊い意などが派生した。
 や行
や行【意味】 後先を考えず物事にあたるようす。むやみやたらなさま。 【語源・由来】 「闇の雲」の意を表し、闇の中で雲をつかむように、漠然としてあてがない意から。
 や行
や行【意味】 家来。召使。 【語源・由来】 室町時代ごろまでは「やつこ」といった。「家つ子」の意で、もとは、「人に使われる奴隷」を指した。その「やつこ」が音変化したもの。
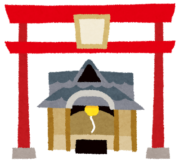 や行
や行【意味】 神をまつった殿舎。神社。 【語源・由来】 「屋(や)代(しろ)」で、「代 (しろ) 」は神を祭るために地を清めた場所のこと。で、元来、祭祀の際に、神がおりてくる仮小屋を設けた土地の意。
 や行
や行【意味】 穏やかで思いやりがある。 【語源・由来】 やせる意の動詞「やす(痩す)」が形容詞化した語。もとは、肩身が狭く身もやせ細るほどに恥ずかしいという意味。万葉の時代から、人や世間に対して気恥ずかしい、肩身が狭いの意味...
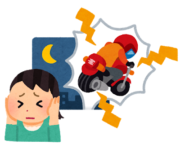 や行
や行【意味】 声や音が大きくてうるさく、不快である。 【語源・由来】 「弥囂(いやかま)しい」の転とする説がある。「いや」はますます、「かまし」はさわがし意。
 や行
や行【意味】 刃のついているもの。 【語源・由来】 「焼き刃」のイ音便形で、もとは「焼き入れをした刀剣の刃」の意。また、焼き入れによって生ずる刃紋のことをいった。
 も行
も行【意味】 秋になり、木の葉の色が赤や黄に変わること。 【語源・由来】 木の葉が色づく意の動詞「もみず」(古くは「もみつ」)の連用形が名詞化したもの。
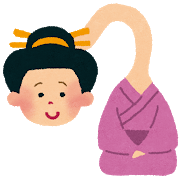 も行
も行【意味】 思いがけないこと。予期せぬこと。 【語源・由来】 人にたたるものの意の「物の怪」の転。古くは、不吉なこと・異変を意味した。
 も行
も行【意味】 使う。役立たせる。 【語源・由来】 「持ち率(い)る」で、もとは、目上が目下の能力を認めて使う意。
 め行
め行【意味】 米を炊いたもの。 【語源・由来】 動詞「食べる」の尊敬語「召す」の連用形「召し」が、名詞化したもの。
 め行
め行【意味】 目つきで知らせること。 【語源・由来】 古くは、「めくわす(目食はす)」の形で、「食はす」は、「合わせる・一体化する」という意味で、目で合図をする意を表した。その名詞化が「めくはせ」。「めくばせ」と濁る形が現れ...
 め行
め行【意味】 おしゃれをする。 【語源・由来】 「冗談めかす」「ほのめかす」などの「そのように見せかける」「~らしくする」意の接尾語「めかす」が独立して動詞化したもの。「危めかす」の略か。もとは外見をとりつくろう意。転じて、...
 め行
め行【意味】 妻をもつ男性と関係をもち、経済的な援助を受ける女性。 【語源・由来】 「目を掛ける」の意からで、古くは「目掛」とも書いた。男が目を掛けて世話をする女の意になった。
 め行
め行【意味】 精一杯。 【語源・由来】 「目」は、はかりの目盛りのことで、「目一杯」は目盛りぎりぎりいっぱいまでという意味。
 む行
む行【意味】 自分の子供。 【語源・由来】 「むす」は生まれる、生じるの意で、「苔生す(こけむす)」の「生す」と同じ。息子は「生す子(産す子)」が変化したもの。娘の「むす」は「生す女(産す女)」が変化したもの。
 む行
む行【意味】 わかりにくい。 【語源・由来】 室町時代ごろまでは「むつかし」。不愉快に思う意の動詞「むずかる(むつかる)」の形容詞形で、うっとうしいなどの感情をいうのが原義。「むつかしい」とも
 み行
み行【意味】 上品で優美なこと。 【語源・由来】 「都人(みやこびと)風をする」「宮廷風をする」意の動詞「みやぶ」の連用形が名詞化したもの。「みや」は「宮」の意。
 み行
み行【意味】 皇居のある土地。 【語源・由来】 もと「宮処(みやこ)」。「みや」は「み(御)+や(屋)」の意で、御殿・宮殿のことをいい、本来は神霊のいるところ、すなわち「宮」をいった。「こ」は「処」で、ここ、そこ、いずこなど...
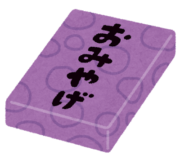 み行
み行【意味】 旅先などから持ち帰る、その土地の品物。 【語源・由来】 古くは「みあげ(見上げ)」といった。よく見て選び、人に差し上げる品物のことをいった。その土地の産物の意の「とさん(土産)」と混同され、室町時代以降、この字...
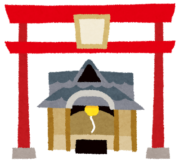 み行
み行【意味】 神をまつったところ。神社。 【語源・由来】 もとは「御屋(みや)」で、神のいる建物の意。
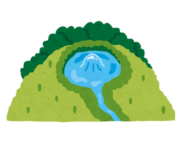 み行
み行【意味】 物事の起こるはじめ。 【語源・由来】 もとは「水(み)な本(もと)」から来た語。「な」は「の」の意。水の流れ出るもと、水源をいい、そこから転じたもの。
 み行
み行【意味】 船が安全に停泊できる設備を整えたところ。 【語源・由来】 みなとの「み」は「水」、「な」は古い連体助詞で「の」、「と」は「門」で、「水の門」の意。水(海)の出入り口をいった。『古事記』や『日本書紀』では、「水門...
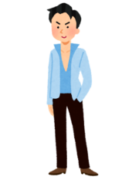 み行
み行【意味】 見かけ。外見。 【語源・由来】 「これを見てくれ」と言わんばかりに見せびらかす意から、外観の意ができた。