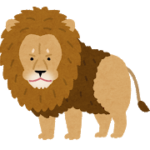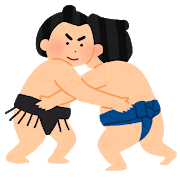「ししおどし」は、もともと田畑を荒らす鳥獣を追い払う目的で使用される装置の総称でした。
こういった装置としては、かかしや鳴子、添水(そうず)などがありましたが、特に「添水」が「ししおどし」として一般的に認識されるようになりました。
「ししおどし」の主な仕組みとして、一方が削られた竹筒に水を引き入れるものがあります。
この竹筒が満水になると、水の重みにより竹筒の一方が下がり、水が排出されます。
水が排出された後の反動で竹筒は跳ね上がり、その竹筒の底部が地面の石に当たることで音を出します。
この特有の音が風流としての価値を持つようになり、日本の庭園にも取り入れられるようになりました。
そうして、「ししおどし」は、ただの鳥獣を追い払う道具から、日本庭園の装飾や風流としての要素を持つものへと進化していったのです。
【鹿威し】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「ししおどし」の基本的な意味や成り立ち、用途や日本の文化との関連性をカンタンにまとめます。
| キーポイント | 詳細・説明 |
|---|---|
| 元の用途 | 田畑を荒らす鳥獣を追い払う目的で使用される装置の総称。 |
| 関連装置 | かかし、鳴子、添水(そうず)など。特に「添水」が「ししおどし」として一般的に認識されるようになった。 |
| 仕組み | 一方が削られた竹筒に水を引き入れ、満水になると重みで竹筒が下がり、水が排出。反動で跳ね上がり、音を出す。 |
| 日本庭園での利用 | ししおどしの特有の音が風流としての価値を持ち、日本の庭園に取り入れられるようになった。 |
| 進化 | 鳥獣を追い払う道具から、日本庭園の装飾や風流としての要素を持つものへと変わった。 |