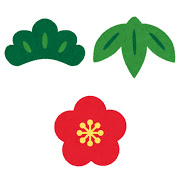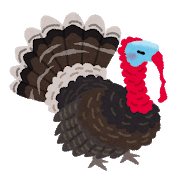「獅子」や「師子」は、元々サンスクリット語の「simba(シンハ)」が起源とされます。
このサンスクリット語の「simba」の首音を元に音訳して「師」とし、そこに「子」を付けることで「獅子(シーツィ)」という名称が生まれました。
さらに、この言葉の漢字表記として、獣の部首(偏)を足して「獅」という字が使用されるようになりました。
日本の歴史の中で、動物の鹿や猪を「シシ」と称していました。
この日本固有の「シシ」と、外国由来の「シシ」を明確に区別するため、外国から来たライオンを「唐獅子」と呼ぶようになりました。
さらに、東アジア地域で生まれた、実在しない想像上の「獅子」も「唐獅子」として呼ばれるようになりました。
このように、「獅子」や「師子」という言葉の背景には、異文化との接触や言葉の進化といった要素が絡んでいます。
しし【獅子・師子】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「獅子」や「師子」という言葉の基本的な意味や成り立ち、日本と異文化との関わりをカンタンにまとめます。
| キーポイント | 詳細・説明 |
|---|---|
| 起源 | サンスクリット語の「simba(シンハ)」 |
| 音訳の由来 | 「simba」の首音を元にして「師」とし、そこに「子」を付けて「獅子(シーツィ)」が生まれた |
| 漢字の成り立ち | 獣の部首(偏)を足して「獅」という字が使用されるようになった |
| 日本の「シシ」 | 日本では鹿や猪を「シシ」と称していた |
| 「唐獅子」の由来 | 外国のライオンと日本の「シシ」を区別するために「唐獅子」と呼ぶようになった。想像上の「獅子」も含む。 |
| 言葉の背景 | 異文化との接触や言葉の進化といった要素が絡んでいる |