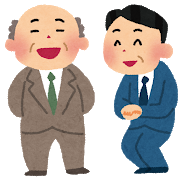「おちゃっぴい」という言葉は、遊女や芸妓が客がいないときや、はやらない遊女や芸妓を指す「お茶挽き」という言葉が転じて生まれた表現です。
この「お茶挽き」とは、遊女や芸妓が客が来ない暇な時間に、茶葉を臼で挽いて粉にする仕事をしていたことに由来します。
この行為は働いても金にならないことを象徴していたため、そのような遊女や芸妓は「お茶挽き」と呼ばれました。
時間が経つにつれて、この「お茶挽き」の言葉が変わって「おちゃっぴい」となり、意味も少し広がりました。
客を引きつけることができない遊女には、多弁でしとやかさに欠ける者が多かったとされています。
そのような特性が、おしゃべりで滑稽な娘やおませな娘にも共通していたため、次第に「おちゃっぴい」は、多弁で滑稽なまねをする娘やおませな小娘を指すようになったのです。
そうして、現代では、働いても金にならないことや、多弁で滑稽な娘を指す多義的な言葉として定着しています。
「おちゃっぴい」の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 「おちゃっぴい」の現代の意味 | 働いても金にならないことや、多弁で滑稽な娘を指す多義的な言葉。 |
| 起源 | 遊女や芸妓が客がいない暇な時間に茶葉を挽いていた行為から「お茶挽き」と呼ばれていた。 |
| 「お茶挽き」の元の意味 | 客が来ない暇な時間に茶葉を挽く仕事をしていた遊女や芸妓。働いても金にならないことを象徴していた。 |
| 発音・表現の変化 | 「お茶挽き」が「おちゃっぴい」という表現に変わった。 |
| 意味の拡大 | 元は遊女や芸妓に特定されていたが、多弁で滑稽な娘やおませな小娘も指すようになった。 |
| 定着 | 現代では、多義的な言葉として定着している。 |