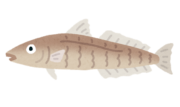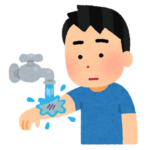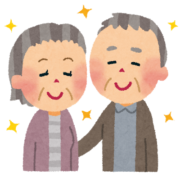「キス」という名前の魚は、日本各地で様々な名前で呼ばれていますが、その語源とされるのは「キシ(岸)」という言葉です。
キスは岸近くでよく見られ、容易に釣ることができる魚であるため、この名前がついたとされています。
特に関東地方で「キス」と呼ばれる一方で、関西・四国・九州地方では「キスゴ」とも呼ばれます。
この「ゴ」は名詞につく接尾語であり、魚の総称を表すものです。
そこから「岸の魚」を意味する「キシコ」となり、時間とともに「キスゴ(またはキスコ)」となり、最終的には「キス」に短縮されたとされています。
漢字で「鱚」と書かれるこの魚の名前は、魚へんに「喜」と組み合わせて作られました。
この「喜」の字は「キ」の音を持つ漢字の一つであり、その中でも特にめでたい意味を持つ漢字を選んだとされています。
このようにして、キスという魚の名前は、地域や文化を通じていくつかの変遷を経て、現在の形になったわけです。
きす【鱚】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、キスという魚の名前の語源、地域別の呼び名、漢字表記、そしてその名前がどのように変遷してきたのかをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・内容 |
|---|---|
| 語源 | 「キシ(岸)」が語源。岸近くでよく見られるため。 |
| 地域別の呼び名 | 関東では「キス」、関西・四国・九州では「キスゴ」 |
| 接尾語「ゴ」 | 魚の総称を表す。原名「キシコ」から変化。 |
| 漢字表記 | 「鱚」。魚へんに「喜」が組み合わせられている。 |
| 「喜」の選定理由 | 「キ」の音を持つ漢字で、めでたい意味を持つ漢字を選んだとされる。 |
| 名前の変遷 | 最初は「キシコ」と呼ばれ、時間とともに「キスゴ(またはキスコ)」に変わり、最終的に「キス」に短縮。 |