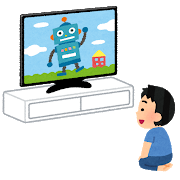「あかぎれ」または「皸・皹」とは、寒さや乾燥などによって手足の皮膚が乾燥し、裂けてしまう状態を指します。
この言葉の歴史は古く、平安時代の文献『和名抄』にも「阿加々利」という訓として登場しています。
さらに、万葉集にも「皸る(かかる)」という語が見られることから、「あかぎれ」の語源については「あ+皸り(かかり)」とする説が有力です。
ここでの「あ」は「足」を意味しています。
言葉が時を経て変化する過程で、その語源が少しずつ忘れ去られ、言葉自体も変わっていったようです。
元々「あ+かかり」という形で存在したとされるこの言葉が、「あか+かり」という誤った区切り方をされました。
この結果、「あか」は皮膚が赤く腫れることから「赤」と解釈され、「がり」は皮膚が切れることから「ぎれ(切れ)」と解釈され、現在の「あかぎれ」という形になったとされています。
さらに、漢字での表記「皸」「皹」は、これが中国で「あかぎれ」を意味していたことに由来しています。
このように、言葉の変遷を追うことで、「あかぎれ」がどのようにして現在の形になったのかが理解できます。
また、この変遷は日常生活の中での皮膚の変化や社会文化、さらには時代背景に影響を受けていることを示しています。
「あかぎれ」の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「あかぎれ」の語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 基本の意味 | 寒さや乾燥などで手足の皮膚が乾燥し、裂ける状態を指す。 |
| 古代の文献における言及 | 平安時代の『和名抄』に「阿加々利」として、万葉集に「皸る(かかる)」として登場。 |
| 語源の有力な説 | 「あ+皸り(かかり)」が語源。ここでの「あ」は「足」を意味する。 |
| 語源の変遷 | 元々「あ+かかり」であったが、誤った区切り「あか+かり」が行われ、「あかぎれ」に。 |
| 誤解された部分 | 「あか」が「赤」と解釈され、「がり」が「ぎれ(切れ)」と解釈された。 |
| 漢字表記 | 「皸」「皹」は、中国でこの症状を指す言葉であることから。 |
| 社会・時代背景の影響 | 語源や意味の変遷は、日常生活、社会文化、時代背景に影響を受けている。 |