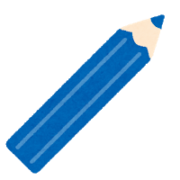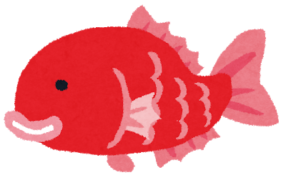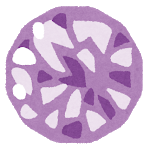薊(アザミ)の語源や由来には複数の説が存在します。
一つ目の説は、沖縄の八重山地方の方言で「トゲ」を意味する「アザ」という言葉に、「植物」を指す接尾語「ミ」が付いたものだという考え方です。
この説によれば、アザミの特徴的なとげとげしい外観が名前の由来になっている可能性があります。
二つ目の説は、アザミの花の色が「交たる(あざみたる)」とされるところから名付けられたというものです。
これは、花の色が特に美しく、それが注目された結果名前が付けられた可能性を示しています。
三つ目の説では、「驚きあきれる」「興ざめする」を意味する日本語の「あざむ」が語源だとされています。
アザミのとげに刺されて驚く、もしくは興ざめするような経験が、この名前の由来になったと考えられています。
漢字で「薊」を書くと、「草冠」+「魚」+「刀」からなる字になります。
これは、アザミのとげが魚の骨のようで、かつ刀のように刺す特性を表しているとも解釈されています。
総合的に見ると、アザミの名前はその植物の特性や印象に基づいている可能性が高く、いくつかの説がそれぞれの角度からその名前の由来を照らしています。
アザミ【薊】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 説の種類 | 名前の由来または特徴 | 説明と解釈 |
|---|---|---|
| 一つ目の説 | アザ(トゲ)+ ミ(植物) | 沖縄の八重山地方の方言で「トゲ」を意味する「アザ」に、植物を指す「ミ」が付いた。とげとげしい外観が名前の由来。 |
| 二つ目の説 | 交たる(あざみたる) | アザミの花の色が特に美しいとされ、その美しさが注目され名前が付けられた。 |
| 三つ目の説 | 驚きあきれる、興ざめする(あざむ) | アザミのとげに刺されて驚く、もしくは興ざめするような経験が名前の由来。 |
| 漢字の解釈 | 草冠 + 魚 + 刀 | 漢字「薊」は、アザミのとげが魚の骨のようで、かつ刀のように刺す特性を表していると解釈される。 |
| 総合的な見解 | 複数の要素に基づく名前 | アザミの名前はその植物の特性や印象に基づいており、いくつかの説がそれぞれの角度からその名前の由来を照らしている。 |