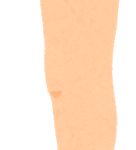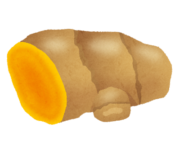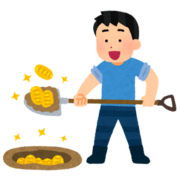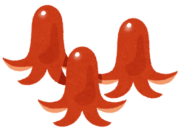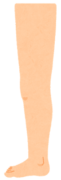団扇(うちわ)は、簡単に言えば風を起こすためや虫を払うための手元道具です。
竹の骨に紙や絹を張って作られ、日本では特に暑い季節によく使用されます。
語源については、「うちわ」という言葉は、元々「打つ羽」という意味から来ています。
この「打つ」という動詞は、ハエや蚊などの虫を払い除ける動作を指しています。
もともとは「打羽」とも書かれており、これが時が経つにつれて「うちわ」に変化したとされています。
また、この道具はただ風を起こすだけでなく、病魔を払い除ける魔除けの意味も含まれていたと言われています。
平安時代には「和名抄」という辞書に「うちは」という記載があり、貴人が顔を隠す目的で使用されることもあったようです。
団扇という漢字で表現することもありますが、この漢字表記は元々中国語の「団扇」に対する和名が「うちは」であり、その後この漢字が一般的に使われるようになりました。
ただし、「団扇」という表記は日本語の音や訓と直接関係がないため、戦後の国語政策によって「当用(常用)漢字表」から外され、現在では「うちわ」と仮名で書かれることが多いです。
うちわ【団扇】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、団扇(うちわ)の重要なポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 詳細・内容 |
|---|---|
| 定義 | 風を起こす、虫を払う手元道具。主に竹と紙や絹で作られる。 |
| 使用時期 | 日本では暑い季節。 |
| 語源 | 元々「打つ羽」から。ハエや蚊を払い除ける動作を指す。「打羽」から「うちわ」に変化。 |
| 追加の意味 | 魔除けや病魔を払い除ける意味も含む。 |
| 平安時代の用途 | 和名抄に「うちは」と記載。貴人が顔を隠す目的で使用。 |
| 漢字表記 | 元々中国語の「団扇」の和名が「うちは」。しかし、戦後の国語政策で当用漢字表から外された。 |
| 現在の表記 | 仮名の「うちわ」として多く書かれる。 |